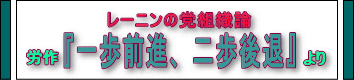
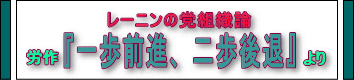
前の連載「『何をなすべきか』に学ぼう」で、我々はプロレタリア党の政治的任務およびそれによっておのずと規定される党の基本的な性格についてのレーニンの見解を見てきた。我々はひきつづいて労作『一歩前進、二歩後退』を通して、レーニンの党建設闘争から学ぶことにしょう。
1 党組織論の宝庫から何を学ぶか
レーニンは『イスラク』の3年間を通じて、経済主義をはじめとする一切の日和見主義、修正主義に反対してマルクス主義の革命的原則を擁護して闘いつつ、それをロシアの具体的歴史的現実に創造的に適用して綱領と戦術を仕上げ、組織計画を練り上げて、ロシアにおける新たな革命党を創建するための理論的、実際的な準備をあらゆる分野で綿密に進めていった。
こうしたレーニン=イスクラ派の党建設にむけての精力的な闘いと努力が実って、ロシア社会民主労働党の事実上の創立大会である同党の第二回大会は1903年7月に招集された。この「大会の主要な任務」はまさに「『イスラク』が提出し仕上げた原則上、組織上の基礎のうえにほんとうの党をつくりだすことにあった」(レーニン、『一歩前進、二歩後退』、全集七巻、33頁、以下同書からの引用は頁数のみを示す)。
レーニンは「『イスクラ』が党組織の基礎におこうと努力した基本的な思想は、本質的には次の二点に帰着する」として、次のように述べている。
「第一の、中央集権主義の思想は、組織上のあまたの部分的、細部的な問題全体の解決方法を、原則的に裁定するものであった。第二の思想――思想上の指導機関である新聞の特殊な役割――は、革命的突撃の最初の作戦基地を国外につくるという条件で、政治的奴隷制の環境のもとにあるほかならぬロシアの社会民主主義的運動の一時的な、特殊な必要を考慮したものであった。ただ一つ原則的な思想である第一の思想は、規約全体を貫かなければならなかった」(248〜9頁)。
プロレタリア党の組織の「ただ一つ原則的な思想である」中央集権主義の思想にもとづき、ロシアのマルクス主義的革命運動はこれまでのサークル的な分散状態に終止符を打ち単一の党へと組織的にも固い統合が実現されるはずであった。しかし、この大会を契機にして、党は再び革命的な一翼と日和見主義的な一翼への新たな分裂をとげてしまった。ボリシェヴィキとメンシェヴィキとへのこの周知の分裂は、レーニンの言うように、当初の「綱領の問題や戦術上の問題ではなくたんに組織上の問題」(208頁)をめぐっての意見の相違から生じたものであった。だが、それはやがて思想的、政治的にも、また組織的にも全く別個の二つの潮流へと発展していった。すなわち、大会後、実質的には二つの党が形成され、存在するようになったのである(両者は17年の革命まで同じ党名を名乗っていたのだが)。
レーニンは、大会から約十ヶ月後に出版された本書において、大会での討論とその後の推移を詳しく分折して、分裂の発端となったイスクラ少数派=メンシェヴィキ派の「組織問題における日和見主義」を徹底的にあばきだすとともに、プロレタリア党の革命的な組織原則を断固擁護し、それをきわめて豊富な内容で基礎づけ、展開している。そして、事実経過をふまえての具体的な叙述は、日和見主義派にしみついたサークル的見地や俗物根性と、革命派に脈打つ党的見地や党精神とを、実に生き生きと鮮やかに対照的に浮び上がらせている。
レーニンは本書の終りの方で党大会とその後の事態を総括して、分立した諸グループを解散して「単一の党的結びつき」を作り出すためには「いっさいのサークル的な利害、感情、伝統の残存物を一つのこらずはきさってしま」うことが必要とされたが、この移行過程において「古いこりかたまったサークル根性は、まだ若い党精神を圧倒した」のであると述べている。
もちろん、我々が当面している党建設の闘いの事情と当時のレーニンのそれとは明らかに異っている。だが、レーニンのこの指摘は我々にとって無縁のものであろうか。決してそうではない。我々もまたこの十年間の闘いにおいてサークル主義の残存物との不断の闘いを積み重ねてきたし、今もその過程にあるのではないだろうか。
当時も、そして現在に至るも浴びせられている「官僚主義的陰謀家集団的組織論」といったタワゴトを排してレーニンの党組織諭の核心をつかみとり、レーニンの闘いに貫かれている党精神を真に自らのものとして体得していくこと――これこそ、本書に学ぷべき我々の課題であろう。
2 規約第一条をめぐる論争
ポリシェヴィキとメンシェヴィキとへの分裂の発端となった党規約第一条(党員と資格要件)をめぐっての有名な論争について、レーニンは「実質上、すでに第一条をめぐる論争のなかに、組織問題における日和見主義者の立場全体が現われはじめていたのである」として次のように述べている。
「すなわち、彼らが行った散漫な、結束の固くない党組織の弁護、党大会および党大会のつくった諸機関から出発して上から下へ党を建設するという思想(いわゆる『官僚主義的な』思想)にたいして彼らがしめした敵意、どの教授にも、どの中学生にも、また『ストライキ参加者のだれにも』みずから成員とみなす権利をあたえることによって、下から上へすすもうという彼らの志望、党員に党の承認する組織の一つに所属するように要求する『形式主義』にたいする彼らの敵意、『組織関係をプラトニックに承認する』心がまえしかないブルジョア・インテリゲンツィアの心理への彼らの好み、日和見主義的な深慮と無政府主義的な空文句への彼らの譲歩、中央集権主義に反対して自治主義を支持する彼らの傾向、一言でいえば、こんにち新『イスクラ』のなかに爛漫と咲きほこっていて、最初になされた誤りを完全にまた一目瞭然と解明するのをますます容易にしている事がらのすべてが、すでにそこに現われはじめていたのである」(208〜9頁)。
この論争とは、周知のように、「党組織の一つにみずから参加する」ものだけを党員とみなす(レーニン)か、それとも「党組織の一つの指導のもとに規則的な個人的協力を行うものは、すべて」党員とみなす(マルトフ)か、という党員の概念(資格要件)をめぐるものであった。一見すると、両者の意見の相違はささいなものであるかのようである。だが、この「小さな意見の相違」が「巨大な意義」をもつにいたったのは何故なのか。レーニンは次のように説明している。
「この意見の相違は、いろいろな原則的な色合いを明らかにしているが、それ自体では、大会後に生じたような仲間割れ(実際には、遠慮なく言えば、分裂)をひきおこしうるものではけっしてなかった。しかし、どんな小さな意見の相違でも、それをあくまで固執するなら、それを前面におしだすなら、この意見の相違の根と枝葉とをあらいざらいさがしもとめはじめるなら大きなものとなりかねない。どんな意見の相違も、それがあるまちがった見解への転換の出発点となるなら、そしてこれらのまちがった見解が、新しい追加的な意見の不一致のために無政府主義的な行動とむすびつき、それが党を分裂させるところまでいくなら、巨大な意義をもつようになりかねないのである。/このばあいにも、まさにそういうふうであった。第一条にかんする比較的小さな意見の相違は、いまでは非常に大きな意義をもつようになった。というのは、まさにこの意見の相違が、少数派の日和見主義的な深慮と無政府主義的な空文句……への転換点となったからである」(262〜3頁)。
規約第一条をめぐる「論争問題の核心」(レーニン)は以上の通りであった。そこで、我々は、まず、この論争についてのレーニンの分折を通じて、レーニンの党組織諭を具体的にみていくことにしよう。
3 党員の概念(資格要件)
「党の綱領を承認し、物質的手段によっても、また党組織の一つにみずから参加することによっても党を支持するものは、すべて党員とみなされる」。
これがレーニンの規約第一条の定式全文である。ここに貫かれている党組織観はどのようなものか。レーニンは、「党は組織の総和(だが、単なる算術的な総和でなく、複合体)でなければならない」という命題を提出し、これを説明して次のように強調している。
「私は、これによって、党は階級の先進部隊としてできるだけよく組織されたものでなければならない、党はせめて最小限度にだけでも組織に服する分子だけを加入させなければならないという、自分の願望、自分の要求を、まったく明瞭また正確に言いあらわしているのである」(264〜5頁)。
レーニンのこの党組織観はまことに明瞭であり、説明は不用であろう。それは、プロレタリアートの解放闘争全体を指導するという革命党の任務と役割から自ずと導き出される組織上の当然の結論である。そして、このような組織思想によって裁定される党員の概念を規約(党員の資格要件)の形式で厳密かつ正確に定式化し、表現したものこそ、冒頭の規約第一条の草案にほかならないのである。
「党は組織の総和でなければならない」(この命題については別にまた検討する機会があるであろう)――すなわち、“党は組織から成り立っていなければならない”という観点からすれば、どの組織にも所属しない党員などが存在しえないことは自明であろう。とは云え、党組織への所属が党員の必須条件として規約に明記されなければならないのは何故か。マルトフらが主張したように、党員は「党諸機関の指導と統制の下に活動する」と謳うだけでも十分ではないか。この点について、レーニンはマルトルフらを批判してこう云っている。
「党員が党諸機関の統制と指導のもとに活動するということは、わかりきったこと」であり、こんなことを謳うのは規約を「空文句」で埋めることでしかない、問題は「党組織のどの一つにも所属しない党員にたいして、党機関は実際にその指導を実現できるか」ということにこそある(251頁)、そして「党組織に所属しない党員にたいする統制とは擬制にすぎない」(269頁)、と。
レーニンが自らの規約第一条を特徴づけて「私の定式化した第一条の思想は、『組織にはいれ!』という刺激にあり、現実の統制と指導とを確保することにある」(281頁)と述べているように、党組織への所属の裁定は単に統制と指導を確保するためのものではないが、しかし、このこと一つとってみてもその意義は明白であろう。
この点を全くあいまいにしたマルトフの定式は結局どこに行き着いたか。「党に組織された分子と未組織分子」、「指導に従うものと従わないもの」、「先進的な人々と矯正の見込みのないほど遅れた人々」との「混同」へ、である(265頁)。そして、このような混同に陥ったマルトフは、党員の概念を途方もなく拡大し、事実上、あらゆる人々を党員としてみとめるという無政府主義的な見地へとのめりこんでいった。実際、彼らは自らの無政府主義的な原則を擁護するためにありとあらゆる口実を並べたて、そして「なんらかの形で党を援助している人々」や、「自分は社会民主主義者であると考え、そう言明する一教授」、さらには「どのストライキ参加者、どのデモ参加者」等々をひきあいに出して、これらすべての人々に「党員と名のる権利を与えよ」と主張したのであった。
4 党、階級、労働組合
党員の概念をいたずらに広げようとするマルトフらの志向は、結局、党と階級、党と労働組合との混同へと帰着した。レーニンはこの混同こそ「組織解体的な思想をもちこむ」「真に危険なもの」であるとして、彼らの“論拠”を論破しつつ、それらの区別と相互関係を明らかにしている。まず、党と階級との関係からみていこう。
「いったいどういう理由で、またどういう論理によって、われわれが階級の党であるという事実から、党に所属する人々と党に同調する人々とを差別する必要はないという結論が出てくるようなことになったのか。まったく逆である。まさに意識の程度や積極性の程度に差があるからこそ、党への近さの程度にも差をつけることが必要なのである。われわれは階級の党である。だから、階級のほとんど全体が(そして、戦時や内乱時代には、完全に階級全体が)、わが党の指導のもとに行動し、できるだけ緊密にわが党に同調しなければならないのである。だが、資本主義のもとでいつかは階級のほとんど全体、あるいは階級の全体がその先進部隊の、その社会民主党の意識性と積極性までたかまることができると考えるのは、マニーロフ気質であり、『追随主義』であろう。
……先進部隊と、それに引きつけられる全大衆との差異をわすれ、ますます広範な層をこのすすんだ水準にたかめる先進部隊の不断の義務をわすれることは、自分をあざむき、われわれの任務の巨大さに目をとじ、これらの任務をせばめることでしかないであろう」(267〜8頁)。
レーニンが党と階級との区別の根底においているものが、『なにをなすべきか?』で展開されたあの「意識性」についての思想であることは明らかである。このことは、党と労働組合との関係についても本質的には全く同様である。レーニンは党と労働組合を混同あるいは同一視するマルトフらを批判して次のように述べている。
「組合が、社会民主主義組織の『統制と指導のもとに』活動しなければならないこと――このことについては、社会民主主義者のなかに二つの意見があるはずがない。だが、それを根拠にしてこのような組合のすべての成員に、自分は『社会民主党員である』と『言明』する権利を与えることは明らかに愚かなことであり、二重の害をおよぼす恐れがあるであろう。その害とは、一方では、同職組合運動の範囲をせばめ、これを基礎とした労働者の連帯性をよわめることである。他方では、それはあいまいさとぐらつきとにたいして社会民主党の門戸をひらくことになるであろう」(271〜2頁)。「党は、同職組合に自分の精神を注入し、これを自分の影響に従わせるように努力しなければならないし、また努力するであろう。だが、まさにこの影響を与えるためには、党は、これらの組合の完全に社会民主主義的な(社会民主党に所属している)分子と、十分な自覚をもたず、政治的に十分に積極的でない分子とを区別しなければならないのであって、……両者を混同してはならないのである」(272頁)。
マルトフらの主張が大衆の自然発生性に拝放し、革命的社会主義を組合主義(ストライキ主義)に低め、いやしめて、プロレタリア党の独自の意識的な役割や任務を否定した経済主義者の立場に転落するものであることは明白である。レーニンが後に語っているようにまさに『経済主義』は『メンシェヴィズム』に姿をかえ」(全集21巻341頁)て復活したのである。
「意識性」の問題を根底においた党、階級、労働組合の間の区別と相互関係についてのレーニンの見解は全く明瞭であり、今さら改めて論じるまでもないかのようである。だが、わが国の急進派の諸君をみてもわかるように、実際にはレーニンの見解はなかなか正しくは理解されていないのである。なるほど彼らは「党の必要性」について口先では山ほどおしゃべりしている。しかし、彼らはそれを「左派結集」や「統一戦線」等々と同列の問題として、もしくはその“ついで”に語っているにすぎない。彼らはポリシェヴィキ的な独自の革命党の必要について本当には何ひとつ理解していないのである。そして、彼らの誤りの出発点にあるものこそ党、階級、労働組合の関係についての無理解ないし間違った理解にほかならないのだ。
5 「上から下へ」の思想
規約第一条をめぐる論争の中で、レーニンが自らの定式を擁護して特に強調しているのは、この定式が「組織にはいれ!」あるいは「組織をつくれ!」という刺激をあたえる、ということである。レーニンはマルトフの定式を批判して次のように述べている。
「『われわれの定式化は、革命家の組織と大衆のあいだに一連の組織を存在させようとする志向を表現している』と、同志マルトフは言う。そうではないのだ。マルトフの定式は、組織にはいろうという刺激をあたえず、また組織にはいれという要求をふくまず、組織されたものと未組織者とを区別していないからである。マルトフの定式は称号をあたえるだけである」(280頁)。「ところが、私の定式化した第一条の思想は『組織にはいれ!』という刺激にあり、現実の統制と指導とを確保することにある」(281頁)。
みられるように、“党組織への所属”を党員であるための必須条件と規定したレーニンの規約第一条の定式の特質は、党員の範囲を限定し、党の統制と指導を実際に確保するというところにのみあるのではなく、まさに「党にはいれ!」「党をつくれ!」という刺激を与えるというところにもあるのである。そして、これは「上から下へと党を建設する」というプロレタリア党の組織論の重要な一側面と不可分に結びついており、こうした観点に貫かれているのである。レーニンはこう書いている。
「こうして」問題は、組織の原則を一貫して貫くか、それとも、離散状態と無政府状態を聖化するか、に帰着する。われわれは、すでに形成され、結束した社会民主主義者の中核――たとえば、すでに党大会を創設しており、あらゆる党組織を拡大し、ふやすべき立場にある中核――から出発して、党を建設するか、それとも、援助するものはみな党員であるという気やすめの空文句で満足するか?」(266頁)。「同志マルトフの基本思想は、まさしくまちがった『民主主義』、党を下から上へ建設する思想にほかならない。これに反対して、私の思想は、党が上から下へ、党大会から個々の党組織へと建設される、という意味で『官僚主義的』である」(435頁)。
レーニンがここで言っている「上から下へ」の党組織論の核心は、何よりもまず党大会を頂点とする党諸機関をしっかりと打ち固め、そこを出発点として党建設を進めていくことであって、文字どおりの官僚主義の思想とは無縁のものであることはいうまでもないであろう。マルトフらの誤りは、プロレタリア党を確固たる革命家の戦闘組織として形成するというこの肝心要の点を等閑視し、「下から上へつき進む」という悪しき「民主主義的」な観点にもとづいて、党のあいまいさやぐらつきを弁護したことにこそあったのである。レーニンはアクセリロードに反論し、強固な党組織の必要性を次のように強調している。
「党組織と認められた組織の成員だけを党員と認めるばあいには、『直接に』どれか一つの党組織に加入することのできない人々は、党組織ではないが、党に同調する組織で働くことができるではないか。したがって、仕事から除外し、運動への参加から除外するという意味での、捨てさってかえりみないということは、問題にならない。それどころか、真の社会民主主義者から成るわれわれの党組織が強固になればなるほど、また党内にぐらつきと浮動性とがすくなくなればなるほど、党をとりまいて、党に指導される労働者大衆の分子にたいする党の影響は、それだけいっそうひろく、多面的に、豊かになり、またみのり多いものとなるであろう」(266〜7頁)。
一切の動揺分子を排除し、真に革命的な分子のみからなる党組織を建設し、党の“純血”を維持することの意義は明らかであろう。
6 インテリ個人主義の反映――マルトフの規約第一条の定式
規約第一条の定式にあらわれたレーニンとマルトフの組織論上の対立的性格は、しばしば次のように解説されている。すなわち、レーニンの組織論が専制ロシアに特有のインテリ(エリート)を中心とした職業革命家の中央集権的で狭い陰謀組織をめざすものであったのに対して、マルトフのそれは西欧型の民主的で広汎な労働者的な党組織を志向するものであった、と。
だが、こうした対比は、ブルジョア自由主義的な見地に立った皮相浅薄な現象論以外の何ものでもない。第一条をめぐる両者の対立の本質は、レーニン自身が云っているように、まさに次の点に、すなわち「広汎なプロレタリア的闘争の擁護者が極端な陰謀組織の擁護者に反対したのではなく、ブルジョア・インテリゲンツィア的個人主義の味方が、プロレタリア的な組織と規律の味方と衝突した」(277〜8頁)という点にこそあったのである。
マルトフのルーズであいまいな結束の固くない党組織の擁護は労働者的な気分をではなく、実は「組織関係を精神的に承認する」だけで実際には組織に入りたがらないインテリゲンツィアの階級的な立場や性格、その気分や心理を反映したものにほかならなかった。レーニンはこの点について次のように書いている。
「口先では、マルトフの定式は、プロレタリアートの広範な層の利益を擁護しているが、実際には、この定式は、プロレタリア的な規律と組織をきらうブルジョア・インテリゲンツィアの利益に役だつであろう。現代の資本主義社会における特別の層としてのインテリゲンツィアを全体として特徴づけるものがほかならぬ個人主義であり、規律と組織にたいする無能力であることを、あえて否定するものは一人もないであろう(…)。とりわけこの点で、この社会層はプロレタリアートにおとるのである。この点に、プロレタリアートがしばしば痛感させられる、インテリゲンツィアの無気力と浮動性の原因の一つがある。そして、インテリゲンツィアのこの性質は、彼らの通常の生活条件や、非常に多くの点で小ブルジョア的な生存条件に近似している彼らの生計獲得条件(ひとりで、あるいは非常に小さな集団でする仕事など)と切りはなせない関連をもっているのである」(277頁)。
インテリゲンツィアに対するレーニンのこの特徴づけは、彼らの性格と心理を見事についている。彼ら(とりわけ急進的インテリ)は時として全く労働者的な装いをもって登場してくる(メンシェヴィキもそうだったが、経済主義者もまた「広範なプロレタリア闘争の擁護者」としてたちあらわれたように)。しかし、階層としてのインテリを特徴付けるものは、「自己の個性の完成がすべて」という骨の髄までしみこんだブルジョア的個人主義であり、彼らの心理は「大衆にとってだけ規律の必要を認め、選ばれた人士にとってはその必要を認めない」(カウツキー)という思い上がりと不可分である。レーニンは、このような急進的インテリ分子の流入が党内で日和見主義の潮流を発生させる一つの主要な基盤であることを指摘し、それへの不断の警戒と闘いの必要を強調している。
さて、規約第一条にあらわれたメンシェヴィキのインテリ個人主義的立場は、その後の中央諸機関の人的構成、選挙をめぐり、全くのサークル主義的な俗物根性をさらけだすなど、ますます度し難いものとなっていった。彼らは自らの要求が通らないとわかるや、選挙をボイコットし、大会後には大会決定を乱暴にふみにじり、“自主補充”という形で中央委員会や機関紙編集局を乗っ取るための策動に狂奔していった。そして、この“泥仕合”を正当化するために、彼らは自らの日和見主義的、無政府主義的立場を一つの原則、一つの体系にまで高めていったのであった。
次回より我々は、これに対するレーニンの批判を検討していこう。
7 規約はなぜ必要か
メンシェヴィキ派は大会後、レーニンに対して「専制君主」「超中央部」「一面的、一本調子、頑迷、狭量、疑いぷかい」等々のあらゆる悪罵を投げつけるとともに、レーニンの党組織論を「内的な統合を前面に押し出さずに、純機械的な手段により、個人の創意や社会的自主活動を組織的に抑圧することによって、実現され維持される外的・形式的な統一を前面に押しだす」「官僚主義的中央集権主義」である、と批判した(これは、今でも自由主義者達によって好んで加えられるレーニン批判の原型だ)。
レーニンは、彼らの「官僚主義」云々の非難が党の中央諸機関の人的構成に対する彼らの不満(規約第一条の採択では反イスクラ派の日和見主義者の支持で勝利したが、彼らが途中退場したため中央機関の選挙では敗北した)を包み隠すためのイチジクの葉、大会後の“腹だちまぎれ”の分裂・撹乱行動を正当化するための口実にすぎないことを指摘するとともに、彼らの持ち出した「原則的な意見の相違」なるものに逐一反駁し、党とサークルとの違いを対比しながら、党的な活動の形式と規律を確立することの必要性を強調している。
例えば、レーニンは、メンシェヴィキの“綱領や戦術における統一、そのための思想闘争こそ党の中央集権化にとって第一義的なものであり、規約は単にその内容をつつむ形式にすぎない”といった規約蔑視の主張に反論して次のように述べている。
「綱領問題と戦術問題とにおける統一は、党を統合し党活動を中央集権化するための必要条件ではあるが、まだ十分な条件ではない(……)。そのためには、さらに組織の統一が必要である。そして、この組織の統一は、家庭的なサークルの枠をいくらかでもこえた党のばあいには一定の形をもった規約なしには、多数派にたいする少数派の服従なしには、全体にたいする部分の服従なしにはありえない」(415〜6頁)。
「問題はわれわれの思想闘争がより高い諸形式、すなわちすべてのものにとって義務的な党組織の諸形式につつまれるであろうか、それとも古い離散状態と古いサークル根性との諸形式につつまれるであろうか、ということである」(417頁)。
「貴族的無政府主義は、狭いサークル的な結びつきを広い党的な結びつきでおきかえるためにこそ、この形式的な規約が必要であることを理解しない。サークル内部の結びつき、あるいはサークル相互間の結びつきに一定の形をあたえることは不必要であったし、また不可能であった。なぜなら、この結びつきは友情か、あるいは説明ぬき、理由ぬきの『信頼』のうえに維持されていたからである。党的な結びつきは、そのいずれのうえにも維持できないし、維持してはならない、それは、ほかならぬ形式的な、『官僚主義的に』(気ままなインテリゲンツィアの見地からすれば)書かれた規約を基礎としなければない。そして、この規約の厳守だけが、サークル的な頑迷や、サークル的な気まぐれや、思想闘争の自由な『過程』と呼ばれているサークル的な喧嘩の方法からわれわれをまもってくれるのである」(422頁)。
労働者階級の先進部隊としての革命党が中央集権化された一糸乱れぬ党的闘いを作り出すためには、思想的な統一と同時に組織的な統一が必要であること、またこの組織的な統一をかちとるためには党活動が全党員にとって「義務的な党組織の諸形式につつまれる」ことが不可欠であることは以上のレーニンの論述から明白であろう。そして、党規約とはこのような党の組織上の諸形式(規律)を法的に規定したものにはかならないのである。
このレーニンの主張のどこに官僚主義、形式主義があろうか。こうした非難はインテリの泣き言と自己弁護にすぎない。
8 党組織の基本命題
前回、我々は、党的な結びつきや組織形態を作り出し、維持するためには、純思想的な結びつきや“信頼関係”だけでは決定的に不充分であり、党活動が規約によって成文化された一定の義務的な形式(規律)に包まれる必要があることをみてきた。
このことは、例えば、党諸機関の性格について言えば、それは単なる「思想の権威」を意味するのではなく、まさに「権力の創設、思想の権威の権力の権威への転化、党の上級機関にたいする下級機関の服従を意味する」(393頁)と、レーニンは言う。つまり、党の各級諸機関は思想的および道徳的な権威にもとづかなければならないし、また党にそのような権威を持つように努めなければならないが、しかし、それは単なる“思想の権威”にとどまるものではなく、“権力の権威”すなわち位階制をもった一個の権力の創出を意味する、というのである。
“上級機関にたいする下級機関の服従”――このような命題は一見すると、党内で必然的に生じるであろう意見の不一致やそれに起因する党内闘争を機械的、権力的、官僚的な手段や方法で抑圧し、下級機関や下部党員の自主性や創意性や個性を圧殺するものであるかのようである。しかし、決してそうではないのだ。なぜなら、この命題は、例えば、党内での公然たる自由な思想闘争、党派闘争の展開と矛盾するものでも、またそれを排除するものでもないからである。
本書を一読すればわかるように、レーニンは党内闘争を排除、抑圧、否定するような発言をどこでも、またいささかでも行っていない。否、レーニンは、それが「不可避」であり、また「必要」でもあると認め、その「公然たる、自由な闘争」を擁護している。ただ、レーニンがそれと同時に強調しているのは、党内闘争が党的な一定のルールの枠内で、正当で忠誠な手段で行われるべきだということである。このようなレーニンの党内闘争についての見解は次の言葉に要約されている。
「党内の種々の色合のあいだの闘争は不可避であり、この闘争が無政府状態や分裂に導かないかぎりは、またこの闘争が、すべての同志や党員によって一致して承認された枠内で、行われるかぎりは、必要でもある」(369頁)。
「上級機関にたいする下級機関の服従」といっても、このような脈絡の中で理解するべきであって、それが何か機械的、盲目的、軍隊的な絶対服従を意味するものでないことは云うまでもないであろう。だが、しかし、この命題が否定され、個々の党員や党諸組織が自分の意思と異なるからといって、上級機関の決定(例えば、大会決定)に従わず、その実行をボイコットするなどの行動に走るならば、党は崩壊してしまうであろう。
レーニンがマルトフらの無政府主義的な言動を批判し、強調しているのは、まさにこのことにほかならない。そして、レーニンが本書を通じてこの他に擁護している諸命題も、全体に対する部分の服従、多数派に対する少数派の服従、党大会をはじめとする各級党機関の決定の実行、規約や規律の厳守等々といった、ごく当り前のものばかりである。それらは、レーニンも云うとおり、「考えられるかぎりのどの党組織のどの体系にもあてはまる初歩的な諸命題」(全集第7巻、509頁)にほかならない。一体、ここのどこに「超中央集権主義」や「純ブランキ主義」の色合いを見い出すことができるであろうか。
実際、これらの諸命題が否定されるならば、およそどんな中央集権的な党組織体系も成り立ち得ないことは明らかであろう。大会の決定の実行を拒否し、少数派の手に中央諸機関を引き渡せといった理不尽な要求をつきつけ、如何なる常軌を逸した党破壊的な闘争方法や手段も辞さなかったメンシェヴィキ派のやり方を批判し、レーニンが擁護したのは、実にこのような初歩的、基本的な組織原則にほかならなかったのである。
9 組織問題における追随主義
メンシェヴィキの面々は、「形式としての組織そのものはその内容をなす革命的活動の成長と同時にしか成長することができない」とかのもっともらしい理屈をこねまわしながら、ロシアの労働者はまだ「組織に服する準備ができていない」、今肝心なのは「プロレタリアートの自己教育」だなどと言いたてて、自らの日和見主義的な組織原則を弁護しようとした。
これに対して、レーニンは、「はかならぬわれわれの活動の形式(すなわち組織)がずっとまえから内容にたちおくれていること、しかもひどくたちおくれていること」が「われわれの弱点」となっており、「形式が未発展で強固でないこと」が「内容の発展のうえでさらに前進することを不可能にし、恥ずペき停滞をひきおこし、力の浪費に導き、言行の不一致に導いている」まさにその時に、彼らのように主張することは「組織上のたちおくれ」を「正当化」し、組織問題における自然発生性に拝跪し、追随する以外の何ものでもない、と批判。それとともにレーニンは「プロレタリアートは組織と規律を恐れない!」と強調し、次のように述べている。
「プロレタリアートは、その全生活によって、多くのインテリ分子よりもはるかに徹底的に、組織に服するように訓練される。……組織と規律の精神での、無政府主義的空文句にたいする敵意と軽蔑との精神での自己教育に欠けているのは、プロレタリアートではなくて、わが党内の若干のインテリゲンツィアである」(417〜8頁)。
この「全生活によって訓練される」プロレタリアートの組織性について、レーニンは、メンシェヴィキの非難の言葉(レーニンは党を、中央委員会という支配人をいただく「巨大工場」と考えている、云々)を逆手にとって、工場の果す役割を次のように指摘している。
「ある人にはお化けとしかみえない工場こそは、まさにプロレタリアートを結合し、訓練し、彼らに組織をおしえ、彼らをその他すべての勤労・被搾取人民層の先頭に立たせた資本主義的協業の最高の形態である。資本主義によって訓練されたプロレタリアートのイデオロギーとしてのマルクス主義こそは、浮動的なインテリゲンツィアに、工場の搾取者としての側面(餓死の恐怖にもとづく規律)と、その組織者としての側面(技術的に高度に発展した生産の諸条件によって結合された共同労働にもとづく規律)との相違をおしえたし、またいまもおしえている。ブルジョア・インテリゲンツィアがなかなか服しない規律と組織を、プロレタリアートはほかならぬ工場というこの『学校』のおかげで、とくにやすやすとわがものにしてしまう」(420頁)。
もちろん、レーニンがここで強調しているのは、「工場の規律の二つのちがった側面」(512頁)を明確に区別し、そのうえに立って「その組織者としての意義」(420頁)を正しく評価しなければならないということであって、それ以外ではない。ところが、ローザ・ルクセンプルグでさえもがレーニンのこの文章に、党を工場のようなものとみなし、工場の教育的意義を称讃しているとかの馬鹿げた批判を浴せかけたのであった(ローザ、「ロシア社会民主党の組織問題」)。
レーニンはメンシェヴィキ派の見解を「組織問題における追随主義」と規定したが、実際、彼らの主張はかつての経済主義者の「戦術問題における追随主義の哲学」を「組織の諸問題に適用」し、「復活」させたものにほかならなかった(経済主義者は「政治闘争の準備ができていない」と労働者を中傷してその革命的政治的任務を否定し、また戦術問題での意識性、計画性を否定して、「過程としての戦術」といった混乱物を主張した)。そしてまた、それは「無政府主義的個人主義の心理から生まれる自然で不可避的な産物」(419頁)以外の何ものでもなかった。
10 「自治主義」批判
メンシェヴィキ派の無政府主義的、追従主義的な組織論を批判してきたレーニンは最後に彼らの立場を特徴づけてこう語っている。
「中央集権主義に反対して自治主義を擁護する歴然たる傾向が、組織問題における日和見主義に固有な原則的特徴である」(425頁)。
革命党の組織の基礎におかれなければならない「ただ一つの原則的な思想」(249頁)である中央集権主義の否定に行き着いた(口先ではともかく実際には)メンシェヴィキの自治主義の思想や立場とは、それでは、どのようなものであったか。例えば、レーニンは、ロシア社会民主主義在外連盟(党の在外組織)の大会における連盟規約制定問題をとりあげて次のように述べている。
「マルトフとアクセリロードが連盟の大会で、部分は全体に服従しなくてもよい、部分は全体にたいする自分の関係を決定するにあたって自治的であり、この関係を定式化している在外連盟の規約は党多数派の意志や党中央部の意志に反しても有効であると、こっけいなほど熱心に論証したとき、彼らが擁護したものは、この自治主義(無政府主義でないとすれば)にほかならなかった」(425頁)。
この問題をもう少し具体的に見てみよう。
「連盟の大会ではつぎのような一般的問題が提起された。すなわち、連盟なり【地方】委員会なりが自分のために作成する規約は、中央委員会の確認を経ずとも有効であるか、また中央委員会の確認がえられないばあいにも有効であるか、という問題である。……委員会を組織する権利は、わが党規約第6条によって、無条件にほかならぬ中央委員会にあたえられている。規約(地方委の――引用者)は【地方】委員会の自治の範囲を規定するのであるが、この範囲をきめるうえでの決定権は、党の中央機関がもっているので(あって)、党の地方機関がもっているのではない。これはイロハである。そして『組織する』ということは、かならずしも『規約の確認』を内包しないという深遠な議論(……)は、まったく子供じみたものであった。だが、同志マルトフは、社会民主主義のイロハさえわすれてしまった」(390〜1頁)
さらに、レーニンは、この問題でのマルトフらに対するプレハーノフの次の反論を「自明の公理」と支持し、本書に引用している。プレハーノフは言う。
「もしそうなら」(すなわち、もし【地方】委員会が、その組織を創設し、その規約を作成する上で自治的であるなら)「委員会は、全体すなわち党にたいして自治的だということになろう。これは、もうブンド的な見地どころか、はっきり無政府主義的な見地である。実際、無政府主義者たちはこう論じている。個人の権利は無制限である、彼らは衝突してもかまわない、各人は自分で自分の権利の範囲をさだめる、と。だが自治の範囲は、グループ自身によってさだめられるべきものではなく、このグループをその一部分とする全体によって、きめられるべきものである。……つまり、自治の範囲は、大会が、また大会がつくった最高機関が決定する」(391〜2頁)。
長い引用となったが、この具体例からも明らかなように、自治主義とは一言で言えば、党全体の利益に自らの地方的、グループ的、部分的利益を優先させる立場、あるいはそのような範囲にまで「自治」と「分権」の拡大を主張する立場と規定することができよう。そして、レーニンは、この自治主義は「革命的翼と日和見主義的翼とへの区分のあるところでさえあれば……全世界のあらゆる社会民主党のうちに……見うけられる」組織問題における日和見主義の一般的、原則的な特徴である、と強調している。
これに対して、中央集権主義は全党的な利益に地方的、部分的利益を完全に無条件に従属させることを要求する。だが、しかし、このことは、下部組織の自治の排除を意味するのであろうか。次回はこの点について検討してみよう。
11 中央集権制と自治
プロレタリア党における中央集権と自治との関係はどのようなものか――我々は、「党内におけるブンドの地位」をめぐる論争をとおして、レーニンの見解をみてみよう。
ブンド(ユダヤ人プロレタリアートの民族主義的組織)はロシア社会民主労働党第二回大会で「文化的民族的自治」なる独特の連合制の組織原則を唱え、一種の共同戦線党的な党組織を主張した。これに対して、レーニンは中央集権制の原則に基づく「もっとも緊密な統一」、諸組織・諸サークルの単一党への融合を対置し、連合制に断固反対した。
「連合制が有害だというのは、それが分立状態や疎隔状態を法制化し、それを原則に、法律にまつりあげるからである。
……だからこそ、われわれは原則的に、入口から、連合制を否認し、われわれのいっさいの強制的な仕切りを否認するのである。………われわれ中央部は、各個の党員に直接手をのばす無条件の権利を受けとるであろう」(大会での演説から、第6巻500〜1頁)
そして、ブンドの連中が中央集権制は下部組織の自主性をそこなうと非難し、「中央部のこまかしい干渉からの自由」といった要求を提出したのに対して、レーニンは彼らの要求を嘲笑して、こう答えている。
「こうしたこっけいな要求を提出すること、それ自体がブンドがこの論争問題をどんなに混乱した形で考えているかを、しめしている。党のどんな組織やグループの問題であれ、それに『こまかしく』干渉するような中央部の存在を、党がゆるすなどと、ブンドは考えているのであろうか。……われわれといっしょにすすみたまえ、そうすればわれわれは、自主性についての正当な要求はすべて完全にみたされるということを、実地で諸君に証明してみせよう」(同前)。
中央集権制が下部組織や党員の自治や自主性を抑圧、排除するものでないことは明らかであろう。そして、もしそうでなかったなら、革命党は機能マヒに陥り、何ひとつその任務を果しえないであろう。なぜなら、千差万別の多様な諸条件の下で、それぞ初の状況に適応して宣伝・煽動・組織化の闘いを具体化し、党活動を遂行・貫徹していくためには、まさに各級組織と党員の最大限の自主性、創意性、積極性、イニシアティブの発揮が要求されるからである。
こうした意味での「自治制」やそれに伴う「責任の地方分散化」はプロレタリア党の中央集権の不可欠の構成要素なのである。レーニンは「プロレタリアートの運動と革命闘争との思想的および実践的指導の点では、できるだけ強い中央集権化が必要であるが、党中央部に(したがってまた一般に全党に)運動の事情を熟知させるという点、党にたいして責任を負う点では、できるだけ強い地方分散化が必要である」と強調し、「この責任の地方分散化は、革命的な中央集権化の必須条件であり、その欠くことのできない補正手段である」(同前247〜8頁)と指摘している。
しかし、繰り返すまでもないが、このことは中央部に服従する義務を決して否定するものではない。というのは、「どういう地方的問題でも全党的な利益に関係してくるばあいがあるし、おそらくは地方の利益に反してでも、全党の利益をはかって地方的問題に干渉する可能性を、中央委員会に与える必要がある」(党規約についての大会での報告から、同前507頁)からである。
中央集権制は不可避的に下部組織や党員の自治や個性や自主性を圧殺し、専制や官僚主義へと走り、下部の組織や党員に盲目的服従を強要し、彼らを無意思の「ねじや歯車」に変えてしまう内在的な傾向を秘めている云々といった見解は全くのたわごとにすぎず、組織や規律に服することを毛嫌いする個人主義的インテリの悲鳴でしかない。中央集権と自治は両立するばかりではなく、むしろ確固たる中央集権制の下においてこそ、本当の意味での自治(無政府的でバラバラでとるに足りない意義しか持ちえないものではない)を保証し、実現することができるのであり、それぞれの発揮する自主性、創意性、積極性等々もまた本当の意味で意義あるものになりうるのだ。
12 レーニンを継承せよ!
以上、我々はメンシェヴィキとの主要な論争点を通して、レーニンの党組織論をみてきたが、この大雑把な検討によっても、レーニンの党組織論は専制ロシアの特殊な状況の下で編み出された秘密陰謀団的な組織原理であって、普遍的な意義をもつものではない、むしろこうしたポリシェヴィキ型の党組織こそが不可避的にスターリニズムを生み出すのだ、等々といった現在流行の見解がどんな根拠もないタワゴトでしかないことは明らかであろう。
例えば、現代のメンシェヴィキ=社会党の仙波は、本書から次のようなレーニンの言葉を引用し、レーニンを官僚主義の肯定者として断罪する。
「民主主義対官僚主義、これはすなわち自治主義対中央集権主義であり、社会民主党の日和見主義者の原則に対比しての革命的社会民主主義の原則である。前者は下から上へすすもうとつとめ、したがってできればどこでもまた可能なかぎり、自治主義、『民主主義』を固執し、これは、(常軌を逸して熱中するもののばあいには)無政府主義にゆきつく。後者は上から出発しようとつとめ、部分にたいする中央部の権利と全権との拡張を固執する」(425〜6頁)
仙波はこれを引いて、鬼の首でもとったかのように勝ち誇って云う。「<民主主義>と対置され、<民主主義>の対極点において要求されている、このような<中央部の全権の拡張>の思想的組織的原則こそが、ポリシェヴィズムのなかにスターリン主義を、常時、純粋培養し、傅育する装直の役割を果したと想定することができるだろう」(仙波著『レーニン1902〜12、前衛党組織論批判』161頁)、と。
スターリン主義がロシアの経済的社会的関係からその上部構造(すなわち支配階級=国家資本主義官僚のイデオロギー)として説明されなければならないことはさておくとしても、レーニンに対する仙波の曲解ぶりはひどすぎる。レーニンがここでメンシェヴィキの「民主主義」に「官僚主義」を対置しているのは、メンシェヴィキの自治主義(形式的民主主義を絶対化し、ひけらかす)の立場を鮮明に特徴づけるための比喩的表現であり、官僚主義そのものを肯定し、擁護しているのでないことは全く明白であろう。ここでレーニンが強調しているのは、強固な組織的中核から出発して党組織を建設していくというあの「上から下へ」への党建設の思想であって、それ以外の何ものでもない。
しかし、このようなレーニン批判の手口は仙波の発明では決してなく、当時から今日に至るレーニン批判者の常套手段である。ローザでさえ、「自分の階級的利害を自覚したプロレタリアートの組織と切りはなせないようにむすびついているジャコバン主義者、これこそ革命的社会民主主義者である」(411頁)というレーニンの片言をとりだして、レーニン自らが「ジャコバン=ブランキスト型」の党組織をめざしていることの告白であるかの皮相な批判を投げつけたのであった。
しかし、本書や『何をなすべきか』でレーニンが一貫して主張しているのは、労働者階級の自然発生的、大衆的な運動や組織とは区別されたプロレタリアートの前衛分子からなる強固な革命党の組織と闘いなくしてはプロレタリア革命の勝利はありえないこと、またこの党の性格はマルクス主義の革命的理論で武装された厳格な規律ある中央集権的な組織でなければならない、ということ、これである。そして、メンシェヴィキやそのエピゴーネン仙波らはもとよりのこと、トロツキーやローザでさえもこのレーニンの党組織論の核心をどうしても理解できなかったのである。その結果はどうであったか。それはドイツ革命のあの悲劇の結末をひとつとってみても明らかであろう。
我々は、レーニンの党組織論の普遍的意義とその革命的原則を断固擁護し、レーニンの闘いに学びながら、労働者階級と深く結びついた真に大衆的な革命党の建設をめざして遭進していかなければならない。最後に、レーニンの次の言葉を引用して連載の結びとしよう。
「プロレタリアートは、マルクス主義の諸原則による彼らの思想的統合が、幾百万の勤労者を一つの労働者階級に融合させる組織の物質的統一でうちかためられることによってのみ、不敗の勢力となることができるし、またかならずなるであろう」(445頁)。
【完】
(この連載の執筆者は町田勝政治局員でした)。
「火花」594号(1983.6.19)〜606号(1983.9.18)