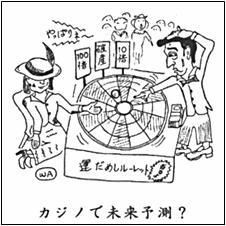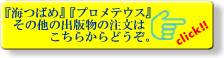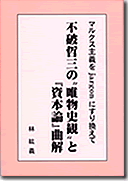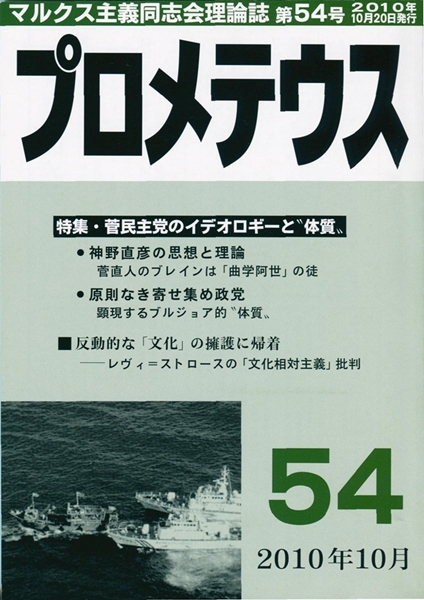|
||||||||||||||||||||
|
���P�Q�R�U�E�P�Q�R�V�������@�Q�O�P�S�N�P�O���P�X�� �y��ʃg�b�v�z���`�u����h�v�̓����\�\�g���ʑI���h�̌��z�ɂƂ���ā\�\�W�]�͍��`�����A���剻�����̓����̔ޕ��� �y�咣�z���{�́u�������P���Љ�v���z�\�\�J���ґS�̂��u�P���Ȃ��Ắv���蓾�Ȃ� �y�R�����z���� �y��`�O�ʁz���u���P�P����^�u���]�U���v�𐾂��\�\���u��̓����̈Ӌ`�Ċm�F�\�\����Ɏ��H���A��`���A�g�D����j �y�l�`�Z�ʁz�Љ��`�ɂ�����u���z�v�͂����ɂȂ���邩�\�\�����i�́u���l�K��v���\�\�u���l�ړ]�v�h�O�}�Ƃ̌��ʂ��g�����h�̌� �y���ʁz�u���J�g��c�v���ĊJ���ꂽ���\�\��������n�߂����{�́u���グ�����v�_ �y���ʁz�}���N�X��`���u�� �y���ʁz�؍��哝�̂ւ́g�Z�N�n���h�\�\�����́u���_�̎��R�v�_�ɒǐ������������ �y���m�点�z �@�{���͑��ƁA�u���l�K����v����W���܂����̂ŁA���ł̍������ɂȂ�܂����B���u�������ʂɌf�ڂ��܂����̂ŁA��������A��ɉ�����ċ��ɓ����Ăق����Ǝv���܂��B�Ȃ��A�{�����������Ƃ������߁A�����͎O�T�Ԃ����ď\�ꌎ������s�ɂȂ�܂��B ���w�C�߁x�o�c�e�Ō��{ ���`�u����h�v�̓��� �@���`�́u���剻�v���������_�ɒB������B�܂������邱�Ƃ́A���̓����͒n���I�ɁA���`�ɂ����āg�����h���A������������̂ł͂Ȃ��A�����S�̂̓����ƌ��т��Ȃ��Ȃ猈���Đ������Ȃ����A�܂������Ȃ��Ƃ������Ƃł���B����ɁA�u���剻�v�����\�\���Y�}�̐ꐧ������œ|���A��|���铬���\�\���u���剻�v�����Ƃ��āg�����h���A����������̂ł͂Ȃ��A�������ɂ��̌��E���Ď��{�̎x�z�ɔ����铬���ɁA�܂�J���҂̊K���I�ȓ����Ɂu�����]���v���čs���Ȃ��Ȃ�\�\�g���c�L�X�g�Ȃ�A�u�i���I�Ɂv�p������A�ƌ����̂����\�\�A�����܂��Ȃ��̂ƂȂ�A���p���邵���Ȃ��Ƃ������Ƃł���B �@���`�̓C�M���X���璆���Ɂu�Ԋҁv����Ĉȗ��P�W�N�A�u�ꍑ�x�v��ۏ���Ă����ƌ����邪�A���������́u����I�v���x�Ƃ����̂͂܂₩���ł����āA�����̋��Y�}�ꐧ�̐��ƈ�����A�g���ʂ́h�c������`�����݂��Ă����킯�ł͂Ȃ��B �@�������������ƍ��`�̊W���A�u�Љ��`�v�Ɓu���{��`�v����������̐��ȂǂƐ�������Ă��邪�����Ă���A�Ƃ����̂́A�����̖{�y�S�̂��܂��u���{��`�v�I���Y�ŕ����s������Ă��邱�Ƃقǂɖ����Ȃ��Ƃ͂��łɂȂ��A���Y�}�̐ꐧ�̐������邩��ƌ����āA����ȑ̐����u�Љ��`�v���Ӗ�����͂����Ȃ�����ł���B���������ǂ��u�Љ��`�v�ȂǂƌĂԂ̂͋��Y�}�̃A�z�������A��������Ƃ���u�Љ��`�v�ƌĂ�ŁA���{��`�̌��ׂ��u�Љ��`�v�̂����ɓ]�ł��悤�Ƃ��A�����ĂԂ��Ƃɗ��v�����o�������������炢�Ȃ��̂ł��낤�B �@���҂̊W�́A��̎��{��`�̐��́A�������g���Ɓh���{��`�̐��̘g���̐F�����̈������́g�̐��h�\�\����������A�g�������h�h�́\�\�Ƃ������W�ȏ�ł͂Ȃ��B �@���`�̃g�b�v�́u�s�������v�́A���Z�ƊE�⏤�H�ƊE�ȂǂɊ��蓖�Ă�ꂽ�I���ψ��̓��[�őI��Ă������A�ނ�͒������Y�}�⍑�Ǝ��{�Ɛ[�����т������͂ł���A����ȘA���̉Ǔ��x�z���A�ԊґO�̍��`�Ɣ�ׂāg�����`�I�h�ł���Ƃ͂������ɂ������Ȃ������̂ł���B �@�������A���`�́u���剻�v�v���͂�����搂��Ă��āA���N�W���A�����̎x�z�w�͂���ȗv�����t��ɂƂ��āu���ʑI���v�����邱�Ƃ����߂��̂����A���̓��e�͂���܂łƔ�ׂď������O�i���Ă��Ȃ����肩�A�����ƈ������̂ł����������B�܂�u��l��[�́v���ʑI���͂��̂����A�������҂ɂȂ��̂́A����܂Œ�����I��ł����u�I���ψ��v�����E���������̐l�������ƌ��肵���̂ł���B �@�u����h�v�́u�I���ψ��v�ɂ���đI���͂����Ȃ��A���nj��҂͒������Y�}���F�߂�҂������I����ɎQ�����邱�Ƃ��ł���A�܂�u�ꍑ�x�v�ƌ����Ă��A�w����͂������A���`�̘J���ҁA�ΘJ�҂��܂�������A�����{�y�Ɠ��l�ɁA�ǂ�ȁg����I�ȁh�������D����̂ł���B �@���ʑI���̌��z�ɐ�������A���҂��Ă�������h��w�������́A����ȋU��́u�����`�v�ɜ��R�Ƃ��A��Ăɗ����オ�����̂����A�������ނ�ɂǂ�ȓW�]������킯�ł͂Ȃ��B �@���`�����̖��剻�Ƃ��������̂͌��z�ł��낤�A�Ƃ����̂́A�����̎x�z�w�A���Y�}��R���͍��`�ɂ���Ȃ��̂�F�߂Ȃ����A�F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ł���B�ނ�͍��`�ɂ���ȑ̐����ł��āA���ꂪ�����܂������S�y�ɔg�y���邱�Ƃ�����A������Q�̂����ɂݎ��A��|���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B �@���`�̊w�������͌��z�ɂ��ڂ�A�g�{���́h�����`�����߂Ă��邪�A��X���悭�m���Ă���ʂ�A������g���ʂ́h���F�����`���ƁA�Ⴆ�Γ��{�Ȃǂ̍��Ƃ��A����ȍ��`�̐��x��A�܂��K�ߕ��̒������̂��̂Ƃ����A�債���Ⴂ�̂Ȃ��A�g���`�h�̍��Ƃł���B �@���`�ŁA����h��J���҂������ł��Ȃ��ƌ����Ȃ�A���{�����l�ŁA���I���搧�⋟�������x�̂��ƂŁA��X�͂��łɋv��������₷�錠����s���ɒD���Ă��āA�����㗧���ł���̂͋������ȂǂقƂ�Nj�ɂȂ�Ȃ��A�����Đ��}�������Ƃ����ד��̐��x�ɂ���č����S�̂̋����A�܂�J���ҁA�ΘJ�҂̃J�l��������ӒD���A���̂��Ă���悤�Ȏ����}�Ƃ�����}�Ƃ������s���Ȑ��}�����ł���B �@�V�������}�A���Ƃ��Γn�ӂ̐V�}�����������ł܂����āA�������̂�]�V�Ȃ����ꂽ�͓̂����I�Ȍo���ł͂Ȃ��������B �@�܂藧��₷�錠�������D���Ă��鐭�}��������ł�����̂́A���`�����łȂ��A���`�̋C�y�Ȋw������������鉢�Ắu���卑�Ɓv���܂����l�ł����āA����Ȉ����⏬�ȔF����W�]����o������A�ނ�̉^���������܂��s���l�܂�A���܂��邱�ƂقǂɊm���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B����͂��Ē����̊w���������A�u�V���厖���v�Őg�������Čo���������Ƃł�����B �@�C���e���B�́A���`�̊w����̓����ɂ��āA�u�����`�̊�@�v������A����ɑ��ė����オ�����̂��A�ނ�̓����͐^���̖����`�A�u���S�ȕ��ʑI���̎��{��v���v���铬���ł���A�Ȃǂƌ����͂₵�Ă���i�Ⴆ�A�r�㏲�A���o�V���P�O���P�R���j�B �@�������u���S�ȕ��ʑI���v���x�Ƃ͉����A�Ⴆ�Γ��{�ł���Ȃ��̂��u�����v����A���݂��Ă���Ƃł������̂��B �@�u���S�ȕ��ʑI���v�Ƃ͂����Ȃ���̂��͒m��Ȃ����A��X���\���N�ɂ��킽���āA���č����I���ɎQ�����ē������o�����炵�āA���{�́u���ʑI���v���u���S�v�Ƃ��������t�ŕ\���������̂ɂقlj��������ƌ������ƁA����͓O��I�ɔ�I�ŁA�u����h�v�ɂ͂����m�炸�A�J���ғ}�h�ɕs�����ŁA�g���ʓI�h�ł���A������r��������̂ł����Ȃ��������Ƃ͗]��ɖ��炩�ł������i���I���搧�A�J���ғ}�h�ɂƂ��Ď�����Q����s�\�ɂ������������x�A���}���������X������j�B �@�w�������̓v�`�u���I���݂Ƃ��āA�u���W���A�����`���A�u���S�ȕ��ʑI���v�Ƃ����������̂�������A����Ȃ��̂Ɍ��z������̂����A���������E�̑����̘J���ҁ\�\�Ƃ�킯���{�̘J���ҁ\�\�ɂƂ��ẮA����Ȃ��̂͂��łɃu���W���A�̎����o���\�Ԃ̈�ɂ����Ȃ��B �@����ɍ��`�ɂ͒����ɕԊ҂��ꂽ��A�u���W���A�����`���A���Ȃ킿�u���S�ȁv�ǂ��납�A�u���ʂ́v�I���������݂��Ă��Ȃ������̂�����A�ɂ߂Đ������ꂽ�A�}�t�̖����`�������݂��Ă��Ȃ������̂�����A�����炻��Ȏ��݂��Ȃ��u�����`���x�̊�@�v�������Ȃ��̂ł���B �@��X�͐��E�̑����̍��\�\�Ƃ�킯���Ă�A����Ɓg���l�ρg����v�����Ă���ƌ�����g�����`�h���Ɓ\�\�̓���������Ȃ�A�g���ʂ́h�����`��g���S�ȁh���邢�́A�g�{���́h�����`�Ƃ��������̂ɂǂ�Ȋ��҂����Ȃ����A��ׂ��ł͂Ȃ��A�J���҂͂�������z���Đi��ōs���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƌ�������B �@����܂Łu�Љ��`�v���ƂƌĂ�Ă��āA�X�O�N��ȍ~�A�g�X�^�[������`�̐��h�A�܂�g���Ɓh���{��`�̑̐�����g���R�h���{��`�̑̐��Ɉڍs���������̍��Ɓ\�\�\�A�����߂Ƃ��鏔���Ɓ\�\�̒��ł��A�g���S�ȁh�����`�͂��납�A�g���ʂ́h�����`�����������悤�ȍ��Ƃ͈�Ƃ��ĂȂ��B �@����ɁA�w�������̖��剻��]�͋�̓I�A���H�I�ɂ����z�ł���A�Ƃ����̂́A����͍��`�����Łg�����I�Ɂh�Ɏ������邱�Ƃ͌����Ăł��Ȃ�����ł���A�Ƃ����̂́A���`�������I�ɓƗ��������Ƃ����݂���Ȃ炻����\��������Ȃ����A���ʁA����͍l�����Ȃ����A�����͌����Ă���Ȃ��Ƃ͋����Ȃ��ł��낤����ł���B���`�́u���剻�v�v���͂��������S�̂̋��Y�}�ꐧ�x�z��œ|���A��|����v���ƌ��т��Ă̂݉\�Ȃ̂����A�ނ�͂��������W�]�ɂ��Ă͉�������Ă��Ȃ����A�܂��ނ�̊K���I���ꂩ�炵�Č�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �@�Ƃ͂����A���`�ɂ�����g���剻�h�^���́A�����̑S�̂̐����̐��ƁA������ꐧ�I�Ɏx�z���鋤�Y�}���͂ɂƂ��āA���̎x�z�̑S�̂�[�������A�h�蓮�����A�j��͂��߂��g�Q�ł���B�����炱���A�����̋��Y�}���͍͂��`�̖��剻�^��������A����ȁg�A���̈ꌊ�h������傫�Ȓ�h���A���Y�}�̌��͂����A���ꗎ����̂�S�z���A�����̂ł���B �@���`�͒����̐ꐧ�̐��̘e���Ɏh�����������ȃg�Q�ōςނ͂����Ȃ��A�����S�̂̐ꐧ�̐��ɓ˂��h����A�Z�����A���̉�̂ƕ���������炷�댯�ȓ����ɂ��A�`�����̕a���ۂɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��̂ł���B �@���`�́u���剻�v�Ƃ������ۑ肳���A�����S�̂́u���剻�v�̎����Ƌ��ɂ̂ݕۏ����̂ł���A�܂��č��`�̖{���̉���A���{�̎x�z����̉���Ƃ����J���҂̉ۑ���܂�����ȏ�ɁA�����̑S�̂̊v���ƁA�ہA�A�W�A�Ɛ��E�̘J���҂̓����Ƃ��̏����ƌ��т��Ă̂݉\�ł��낤�B �@�����̋��Y�}���͂̑œ|�͌����܂ł��Ȃ����A���́g���剻�h�Ƃ����ۑ肳�����A���ꂪ�J���҂̍L�ĂŁA�[�����犪���N�����Ă��铬���Ȃ��ɂ͕s�\�ł���A�W�]���J�����Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�A�����Ă������������͂��̖{����A�P�ɋ��Y�}�̌��͂̑œ|�Ƃ������g���剻�h�̓����ɗ��܂炸�A�����܂�������������A�J���ҊK���̎x�z�ƎЉ��`�̎����Ƃ����A����̎Љ�ɑ��݂��鍪��I�Ȗ����N���邵�A������Ȃ��̂ł���B �@�����̎x�z�K���͍��`�́u���剻�v�������������Ƃ��ł����A����Ӗ��ł���Ȃɂ��ǂ��l�߂��Ă���A�u���剻�v�^���̔��W������Ă���A�܂�ނ�͎���̌��͂��A���{�̎x�z�����A�i���������悤�Ƃ������قǁA�u���剻�v�ɂ��������ē��킴��Ȃ��̂ł���A�܂��܂�����̎x�z���͂����߁A��߂���Ȃ��̂ł���A�j�]�Ɍ������Đi�܂���Ȃ��̂ł���B �@����Ӗ��Łu���剻�v���Ȃ킿�ނ�̎x�z�̐��̒e�͉��͔ނ�̗��v�ł���A�ނ炪�������т邽�߂̗B��̓��ʂ̎�i��������Ȃ��A�������ނ�͎���ɂ���ȁu�]�T�v���������o���Ȃ��̂ł���A�������ł͂Ȃ��A�܂��܂��ꐧ�̐����������邵���Ȃ��̂����A���̂��Ǝ��̂��A�P�ɍ��`�����łȂ��S�����̘J���ҁA�ΘJ�҂̑��������������A���ݏo���Ă����̂ł���B �@���`�̊w���̌��N�́A�����̐ꐧ�̐���h�邪���A�V�������E�I�Ȋv���̓����J���\�������������Ă��邩������Ȃ��A���������`�́g���剻�h�����������������̂Ƃ��Ĕ��W����ɂ́A���ꂪ�����S�̂̓����ւƁA�����������̘J���ҊK���̓����ւƈ����p����A�����ɂ�����ꐧ���͂̑œ|�ɗ��܂炸�A���E���̎��{�̎x�z�ɔ����铬���ɓ]�����Ă�������ɂ����Ăł���ɂ����Ȃ��B
�@���{�́u�����헪�v���ꂵ����̏����H�ł����āA�u�o�ϐ����v�̂��߂ɁA�ǂ�ȐϋɓI�Ȗ������ʂ����������Ȃ����A���Ŕ́u�������p�v�قǂɁA���{�����̔������Ƌ����A�ނ́u�����헪�v�̕s�т���\�I���Ă�����̂͂Ȃ��B �@��̓I�ɏグ���Ă���u�U�̒��v�Ƃ́A�u�Ǝ��E�玙�x���T�[�r�X�̏[���v�Ƃ��A�����̋N�Ƃ��x������Ƃ��A�_�ѐ��Y�Ƃł̌o�c�҂��琬����Ƃ��A�Z�N�n���h�~�֊�Ƃ��w������Ƃ��A�}�t�̂��ƁA�ǂ��ł������悤�ȁu����v�����ł���B �@���ہA�咆��Ƃ̏����Ǘ��E����������R�O���ɂȂ�A���{�̖{�����ς��Ƃł����{�͍l����̂��B���̏ꍇ��������ł�����̂�����A���{�́i�u���W���A�����́j�l���邱�Ƃ͑S���܂�Ȃ��A�}�t�̂��Ƃ���ł���B �@�����̎Љ�I�Ȓn�ʂ̌����A�����₻�̑��̎��ۓI���ʂ̈�|��A�J���ҁi�Ƃ�킯�����J���ҁj�ւ̕K�v�Ȏ{�݁i���������X�j��z����A�K��h���Ƃ������J���`���̔p�~��A�g�Ƒ����x�h�̉��P�ƕ����̎�����A���̑��A���{�̎x�z�Ǝ����}�̐������͂̂��ƂŃT�{�葱�����ė��Ă���A�����̏d�v�ȉ��v��I�グ���A���邢�͖������Č����A���{�̕\�ʂ����͔h��ȁu�����̂��߂́v����͂��ׂăC���`�L�ł���A�U���ł����āA�����́A�L�Ăȏ����J���҂̍���Ȑ�����J���������ق�̂킸���ł����P���A�����グ����̂ł͑S���Ȃ��B �@���{�́u�S�Ă̏������P���Љ�Â���{���v�Ƃ�������X�������̂��ł����グ�����A�����������{�S����]�ނȂ�A�S�Ă̍������A�S�Ă̘J���҂��u�P���v���ƂȂ����Ă͑S���s�\�ł��낤�B �@������œ����K�̏����J���҂͎R�قǂ���̂ɁA����ȏ����̂��߂ɂ��߂āu����J����������v���������邱�ƂقǂɁu�������P������v���Ƃ͂Ȃ��̂����A�����̏������Ί�ɂ��A�u�P������v����ȍ��{�I����͈��{�̊ᒆ�ɂ͂����炳�������݂��Ă��Ȃ��B �@�������ł͂Ȃ��A���{�͏����������ł��u�P���v���Ƃ̂ł���A�����̎��ۓI�ȉ��v���T�{�葱���Ă���B���{�͏������u�P�₩���v�����Ɩ]�ނȂ�A�Ⴆ�Ώ������u�Ɠ��z�ꐧ�v�ɔ���t����̂��������Ă���u�z��ҍT���v����g��w�h�D���̍��ʓI�N������p�₷�邱�Ƃ�A�܂��u�I��I�v�w�ʐ��v���x�̓������������Ɏ��s���ׂ������A�܂������W���Ă��鎩���}���́u�j���������S�v�_�܂�u�Ƒ��̉��l�Ɛ�Ǝ�w�̖����v�Ƃ��A�u�Љ�I�Ȏd���ɂ����Ƃ�������������̏�ł͂Ȃ��v�Ƃ�����������ׂ��f�łƂ��ĕ��ӂ��Ă�����ׂ����낤�B �@�u�Ƒ��̉��l�v�ƌ����Ă��A�Љ�I�ɖ{���ɕ����Γ��ŁA�l�i�I�Ɏ������Ă���j�������Ȃ���A�ǂ�Ȃ܂Ƃ��Ŗ{���́g�Ƒ��h�����݂��Ȃ����A�����Ȃ��̂ł���B �@���{�́u�S�Ă̏��������M�ƌւ�������A�P�����Ƃ̂ł���Љ�v�Ƃ��������A�����������̑S�̂��A�J���ҁA�ΘJ�҂̑S�̂��A�u���M�ƌւ�������v���Ȃ��ŁA�炢����J���̍��ʘJ���ɋꂵ�݁A��]���Ă���Љ�ŁA���������K���Łu�P���v���Ƃ��ł���͂����Ȃ��B���{�̌������Ƃ́A���̐^�S���^�������Ȃ��A��X�����P�Ȃ���悾���̌��t�ł����Ȃ��B �@�����āu���q����Љ����A�J���͕s����₤���߂̏������p�v�ƌ��������z�@�́A�����l�߂�A������J���͂́g���ԁh��g�s���h����������E��ȂǂɁA�������s����Ȓn�ʂ̂܂ܕX�I�ɓ������A�炭����Ȏd���ɋ�藧�Ă悤�Ƃ��������ł������蓾��̂ł����āA�����̎̕���y���̂�����̕\���ł�������B �@�J���҂́A�����͈��{�����̂��ƂŁA�u�P���v���Ƃ͌����Ă��蓾�Ȃ����ƁA���̔��݂̂��^���ł��邱�Ƃ����o���ׂ��ł��낤�B
�@����X���U�A�V���̗����A�}���N�X��`���u��̑�P�P����S������Q�V���̑�c�������W���ĊJ�Â���A���E�Ɠ��{�̐����o�Ϗ���������钆�A�����Ĉ��{�����Ƃ����R����`�I�Łg�댯�ȁh�������o�ꂷ��Ƃ����̒��A��X�̓������u���]�U���v�Ɍ����đ傫�������A�V���Ȍ��ӂ��ł߂Ēf�ł��铬����W�J����o���_�̑��Ƃ��āA�����̏d�v�ȕ�c�_���Ȃ��ꂽ�B���ł́A���E�Ɠ��{�̐����o�Ϗ�A���_���A����ɂ͑g�D�I�ȓ����ɂ��Ă̋�̓I�ȑ��ʁ\�\�g�D�����A�@�֎������i�w�C�߁x�j�A�o�Ŋ����i�G���w�v�����e�E�X�x��P�s�{�j�A�C���^�[�l�b�g�̗��p�A�O�E�L���A�������j���X�\�\�ɂ��Ă�������A����ɂ͂����̑S�Ăɂ킽���ĔM�S�ȋc�_���s��ꂽ���A�����ł��̑S�Ă��Љ�邱�Ƃ͕s�\�ł���B�c�_�⌈��A�m�F���ꂽ���Ƃ͍���̓����̒��Ő�������A�ѓO����A���邢�͋@�֎����ɂ����f����čs�����낤�B��X�́A�Љ��`�^���ɂ�����ɂ߂ďd��ŁA����I�ȗ��_���\�\���N�̘J���҃Z�~�i�[�Ō�������A����̑��ł��c�_���ꂽ�A�Љ��`�Љ�ɂ����������̉��l�K��ƁA����ɂ��u�J���ɉ����Ă̕��z�v�Ƃ������\�\�ɂ��āA�����𖾂炩�ɂ���i�{���l�ʁ`���ʂɌf�ځj�B�ȉ��A���ō̑����ꂽ�ɂ߂Ď��H�I�Ȗ��̈ꕔ�ƁA���̕����ɂ��đ��łȂ��ꂽ��\�ψ���̐������f�ڂ��A�ǎ҂̌����Ɖ�X�̓����ւ̎Q�����Ăт�����B �@���q�Ϗ�Ɠ��u��̉ۑ� �@���ł́A����ڂ̐����o�Ϗ�◝�_���̌�����c�_�̌�A����ڂ̖`���A��\�ψ�����\���ėт���A���j�I�A���ۓI�Ȍ����܂��āA�ȉ��̂悤�Ȏ��H�I�����̕��������ꂽ�B �@�u�����܂ł��Ȃ����Ƃł��邪�A�q�ϓI�ȏ�́A����E����V�O�N���ւāA�V�����u���W���A�卑��������s�ŁA�댯�Ȏ��{��`�I�鍑��`���ƂƂ��ēo�ꂷ�邱�Ƃɂ���āA�V�������E�I�Ȋ�@�̎���Ɍ����Đ��n������B�����Ă܂��A���u���E�ɂ����铮�h�ƌ����̊g����܂��A���E�̃u���W���A�卑�̗��Q�����݁A���E�I��@��[��������d�v�Ȍ_�@�ƂȂ��Ă���B�����̃u���W���A�卑�Ƃ��ẮA����Ȓ鍑��`�卑�Ƃ��Ă̓o��́A�A�W�A�E�����m�����̌x���S��R�g��`���������炵�n�߂Ă��邵�A�����Ȃǂ̎x�z�ƃw�Q���j�[�������āA�卑�̑Η������W���Ă���B���V�A���܂��A���̒鍑��`�I��S���̂ĂĂ͂��Ȃ����A���Ẵu���W���A���Ƃ��܂����l�ł���B�������A�鍑��`�A�R����`�̔��W�͓����ɍ����ɂ����閯���`�́A�g�@����`�h�̌�ނ␊�ނł���A�ꐧ��t�@�V�Y���Ƃ����������̐��ւ̏Փ��̋��܂�ł���A�܂�͂P�X�R�O�N��ւ̉�A�ł���B����������A���S�������`����邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ��Ă��A���̐����͕K�R�ł���A�]��ɖ��炩�ł����āA�J���ҁA�ΘJ�҂ɂƂ��ĐV���������̎���̎n�܂�ł�����B �@�������Ď��{��`�ƃu���W���A�x�z�̊�@�͍���܂��܂��[���A�g�傷�邵���Ȃ����A���̂��Ƃ������܂��ɐ��E�̂�����Ƃ���ɂ�����A�J���ҁA�ΘJ�҂̒f�ł��锽���ƊK���I�A�v���I�ȓ����̕K�R���ł���A���̎n�܂�A���W�A�[���ł��邵�A�����łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@��X�͍������A���o�����J���ҊK�����厑�{�̎x�z�ɔ����A���̒鍑��`�����ɔ����āA�f�łƂ��ē��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����オ����Ă����邱�Ƃ��m�F���A��X�̐�����ł߁A�������čs���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B��X�̓����̈Ӌ`�͂܂��܂��傫���A����I�ł���B��X�͍��������{��h�Ƃ̓����Ƃ����A���݂̒i�K�ɂ����錈��I�ɏd�v�ȓ����ɑS�͂��グ�Ď��g�݁A����ɘJ���҉���Ɍ����Ĕ�Ă����ׂ��H�i�Ƃ��j�ł���v�B �@�����đ�\�ψ�������������̕����́A�u���������]�U���ցv���������t�̂��ƁA�J���ҊK���̌����I�ŁA�f�ł��铬���Ɣ������g�D����Ă��Ȃ��\�\�ނ��낻�̐����������ł���\�\�Ƃ�����̓I�ȏ̒��ŁA���{���{��`�̕��������p�̐[���ƁA����ɕ��������킹��悤�ɒ�����绂��n�߂��A�u���W���A�I�����ƌR����`�I�A�鍑��`�I�����ƒf�łƂ��ē����������ƁA���j�ɂ���ĉۂ��ꂽ�ۑ�ƐӖ���S�����߂Ɂg���R��`�h����|���A�n�ӂ���A��̓I�Ȋ��������߂邱�ƁA�}���N�X��`���u��́u�P�Ȃ�T�[�N���v�ł͂Ȃ��A�u�v���I�ŁA���H�I�ȃT�[�N���v�Ƃ��ďo�������Ƃ������_������x�m�F���A�����r���āA�g�D�̐����A�����A���������A���u��̑S�̂����H�I�ŁA�����I�ȑg�D�ɒE��A�ϐg���Ă������ƁA����܂ł��d�����Ă����w�K��Ȃǂɉ����āA�u�J���҃Z�~�i�[�v�Ƃ�������i�����p���āA�p���I�őg�D�I�ȓ����𐄂��i�߁A�V�����J���ғ}�����グ�Ă������ƁA�Ȃǂ��m�F�����̂ł������B �@��X�͂��������ۑ�ɂ��Ă̑�\�ψ���̕������Ɍf�ڂ��āA�ИJ�}��g�D���āA�\���N�ԁA�c��E�I�������֎Q��������A���u��ֈڍs�����Ӗ��ƈӋ`�𖾂炩�ɂ��A�S���̓ǎ҂݂̂Ȃ���ɁA���������u��̓����ɎQ�����A�Ƃ��Ɉ��{�����ɔ����A����ɂ܂����{�̎x�z�ɔ����ē����A�J���ҊK���̋��ɓI�ȉ���Ɍ����ċ��ɓ����悤�ɌĂт�����B�ȉ��͑�\�ψ���̕ł���B �@����X�̗��r�_ �@��X�́A�}���J������ИJ�}�Ɉڍs���A�c������`�̘g���ł̓����A��������p���ē����𐄂��i�߂�Ƃ�������I���������A���߂Ă��̈Ӌ`���m�F���A�܂����Ȃ��Ă݂�K�v������B��X�͂P�O�`�P�T�N�ɂ킽�鐭���������I�������Ɍ��R�ƎQ�����Ă����B����͉�X�ɂƂ��ău���W���A�����`�̂��ƂŁA�ǂ������Ă����̂��Ƃ����A��{�I�ɏd�v�Ȗ��ł������B�V�����̘A���͈ꌾ�ł����ăQ�o���g�����H���ɌX���čs�������A��X�̓u���W���A�����`�̉��œ����`�ԂƂ��ċc�����i�߂Ă����B �@�������A��X�̋c����͍s���l�܂�A���̓������~�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�������A���܂����ƌ�����B���̌����͂������������B���I���搧�����������A�I�����x�����������i�������̈����グ�����̈�������j�Ȃǂ����������A��ԑ傫�������̂͋��i��Ƃ��ċ������j�̖��ł���A�����傫�ȕ��S�Ƃ��Ď؋����Ⴞ����ɐςݏd�Ȃ��Ă������B���������x���Ȃ�����������Ƃ�ꂽ�Ǝv�����A���̑I�������̍s���l�܂�ɂ���āA���u��i�����I�T�[�N���j�Ɉڂ�Ƃ����]����]�V�Ȃ����ꂽ�̂ł������B �@�]���̎��ɂ�����A���u��̊�{�I���ꂪ�c�_�ɂȂ�A�����g�D���T�[�N�����Ƃ������Ƃ����ɂȂ������A��X�͊�{�I�ɃT�[�N���ƌ����Ă��P�Ȃ�T�[�N���ł͂Ȃ��A�u�v���I�T�[�N���v�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��������A�m�F���Ă����B�u�v���I�v�Ƃ͎��ۓI�ȓ����Ƃ������Ƃł���A�V���������̉��ł����ɓ������J���Ă������̖��Ȃ̂��A�ƒ�N���ꂽ�Ǝv���B���̒��ŁA��������d�����邱�Ƃ���������A�Ƃ�킯�u���{�_�v�`���̘J�����l�����d�������ׂ��Ƃ��ꂽ�B����ɑ��āA�w�K��̃T�[�N���Ɉڂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����悤�ȕ��͋C�Ŏ����ʂ��������B�������A����������d������ƌ����Ă��A����͉�X���g��������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���_�̌�����ʂ��ĘJ���҂��҂��I���O���A�g�D�����Ă����ۑ�ƌ��т�����ׂ��Ƃ������Ƃł������B �@�s���̕����ɂ��ẮA���ł́A���ł̋c�_�Ȃǂ����āA���̂悤�ɂ��܂Ƃ߂��Ă���̂ŁA�ȉ��ō��킹�ĕ��Ă����t �y�ИJ�}����̋c������`�̐��x�ɏ������A���̘g���œ����Ƃ����H���͍��܂����B��X�̐�p����{�I�ɊԈႪ���Ă�������ƌ����̂ł͂Ȃ��A�c������`�����łɂ����Ȃ�Ӗ��ł��u�����`�v��̌�������̂ł͂Ȃ��A����Ƃ͔��Ε��ɕώ����Ă��܂�������ł���A����ɂ܂��܂��ώ���������ł���i���������x�A���I���搧�A���}���������X�j�B �����ĉ�X�́g�c���`�H���h�̍s���l�܂�ƍ��܂ɒ��ʂ��āA��{�I�ɂR�̎��H�I�ȑI���ɒ��ʂ����̂ł������B�܂�c������`�ɓK�����A������u���p�����v�����ɍ��܂��A���邢�͂��̓��������ꂽ�̂�����A�@�V�����I�Ȃ��邢�̓A�i�[�L�X�g���̓����ɁA���Ȃ킿�}�i�I�A���ړI�A�e�����Y���I�ȘH���ɖ߂��Ă������A�A���邢�͓������~�߂āu�P�Ȃ�T�[�N���v�Ƃ��āA���邢�͒P�Ȃ�l�Ƃ��āA����H�I�A�g�T�ώғI�h�i�g�ϏƓI�ȁh�A�t�H�C�G���o�b�n�I�B���_�̗���j�ɗ����A�B����Ƃ��c���`�I�Ȃ����ł͂Ȃ��A�������u���W���A�����`�̐��ɂ�͂�K�������A�ʂ́A�V���������̓������o���A�������p�����邩�A�Ƃ����I���ɒ��ʂ����\�\�q�ϓI�Ɍ��ā\�\�̂ł��������A��X�u�I���v�����͇̂B�̘H���ł������B ���Ȃ킿�A���u��̓����́A�u���W���A�����`�i�c���`�j�𗘗p���铬���͍��܂����̂�����u���ڍs���v�̓��A�Q�o���g�����̓��A�e�����Y���̓������Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ����Ƃ��āA�}�i��`�̘H���Ɂu�߂�v���ł��Ȃ��A���邢�͖����`�̂��Ƃł́g���@�I�ȁh�����̎�i���D���A�܂��e�����Y�����Ȃ��Ƃ���Ȃ�A�u���W���A�ƍقœ�����i���Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ɛ�]���ē������铹�ł��Ȃ��A������������`�Ōp�����铹��Nj����Ă����Ƃ��납��ďo�������̂ł������B���������̉ߒ��ŁA������`�Ŋv���������ѓO����Ƃ����]���ɓK�����邱�Ƃ��A����𗝉����邱�Ƃ��ł����A�܂�����������ӎu���Ȃ��A���ۏ�A�A�̓��ɂ܂Ō�ނ��������o���B �m���ɊK���I�Ȑ��������̏�Ƃ��āA���̌P���Ƃ��āA�I�����c��������u���W���A�����`�̓T�^�I�ŁA�W�ꂽ�\���ł���A�g���́h�A���F���ꂽ���K�����\���鏔���}�̓����̏�ł���A�J���҂̐��}�������ɎQ�����A���������Ӌ`�́\�\���ɘJ���҂𐭎��I�ɒb���グ�A���W���A�g�D���Ă�����ł��Ӌ`�́\�\����Ӗ��ł�����]�����Ă��������邱�Ƃ͂Ȃ��B����������������ۂɕߏo���ꂽ����ƌ����ā\�\�v���I�A�K���I�ȓ}�h��͂��ł��邾���ߏo�����߂ɍ������A�����`�������セ�̔��Ε��ɂ܂��⏬�����A��k�߁A�ے肵�Ă����̂̓u���W���A�K���ɂƂ��Ă͈�̕K�R���ł���\�\�A����́A�u���W���A�����`�̈�ʓI�ȏ����̂��Ƃł̓�����������Ă���Ƃ������ƂƓ����ł͂Ȃ��B��X���g���@�I�Ɂh�����Ȃ��Ƃ����Ȃ�e�����Y���ɂ����ڂ��Ă����ȊO�Ȃ����A�����܂ł��Ȃ��A�ނ��댻�i�K�ł̓e�����Y�������͗L�Q�ł���A�S�Q�����Ĉꗘ�Ȃ��A�J���ҊK���̓����̔��W�ɂƂ��ă}�C�i�X�ȊO�̉����̂ł��Ȃ��B��X�͈�т��Ă��̗�����������Ă����̂ł���B�z ��X�̌�������͓���I�ȓ����Ƃ��Ă���ė����̂����A����ȊO�ł����낢��͍�����Ă����B�c�Ăɂ��R�قǂ̗�����������A���_�W���u���W��Ȃǂ�g�D���i���N�͂R�����j�A���邢�́A�����w�K��Ƃ����`�ʼn������͍s�����B����ɘJ���Ҋw�Z�A�J���҃Z�~�i�[���������B ���u���W���A�����`���̐V���ȓ��� �����Q���҂͂Ȃ��Ȃ��蒅�����A���ꂪ�g�^���h�Ƃ��ĒNj�����A�g�D�����Ƃ����Ƃ���ɂ܂Ői�܂��A���ǂ͒��r���[�ɂȂ����B���̋c�Ăł́u�i�P���j�J���҃Z�~�i�[�v��V�����������ꂽ�g�^���h�̎�i�ł����搂��Ă���i�V�����������ꂽ�Ƃ����̂͑傰�����Ɣᔻ���Ă����邪�j�B�������܂ł��A�Z�~�i�[�͓����̎�i�̈�ƈʒu�Â��Ă������A�N�P��Ƃ������Ƃ�����A�p���I�ȁg�^���h�Ƃ��ēW�J���Ă����Ȃ��ʂ��������B���N���R�ɂP���̘J���҃Z�~�i�[�ƂȂ������A�т̓����������Ƃ��̊��G���܂߂Č����A���ɂ��₷���A���������₷���Ɗ������B����Ȍo�����܂߂āA�P���Z�~�i�[���g�^���h�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����ƒ�N���Ă���B ��X�̎Q�l�ƂȂ蓾�铬���̂����Ƃ��āA���j�I�ɂ������I�ɂ��F�X����B�Ⴆ�A�����J�́g����i�e�B�[�p�[�e�B�j�^���h������A����͋c����ł͂Ȃ����g�^���h�Ƃ��ēW�J����Ă���B�V�����ɂ͕��������Ƃ����c�������Ƃ��̂����������������B���邢�͘J���^�����傫������オ���ė����Ȃ�܂��l�X�ȓ����̓W�]���J���Ă��邾�낤�B�ŋ߁A�E���i�C���e���j������̎w�������O�r������ᔻ���Ă��āA���₪�����́u�v���헪�v�̂��߂ɎO�r�̘J���^���ƘJ���҂𗘗p�����ƒ������Ă����B����̓��̒��́u�v���헪�v�ŁA�O�r����̓I�ɂǂ̂悤�Ɉʒu�Â����Ă������͒m��Ȃ����A�O�r�����_�Ƃ��āu�Љ��`����v�̘H���i�ނ�̒��ł���ΐ�Ύ����ꂽ�g���������h�����A�]���Ă܂��ނ�́u�v���헪�v�j�������i�߂悤�Ƃ��A�����č��܂����Ƒ������邱�Ƃ��ł���Ǝv���B �ȏ�̗Ⴊ���̂܂ܒ��ڂɉ�X�̂����Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă��A�u���W���A�����`�̂��ƁA�I�������ȊO�̕��@�łǂ̂悤�ɓ����čs�����A��������o���A�����̓����J���čs���Ƃ������Ƃ����A��X�̌��ݒ��ʂ��Ă���ۑ�ł���B����̋c�_�̒��ł́A�Љ��`���i���ڂɁj�f���Ă��ׂ����Ƃ����ӌ������������A�W�c�I���q���̖��ɂ����Ɓi�Ћ���X���̉�ȂǂƋ��ɁA�������āH�j���g�ނׂ����Ƃ����ӌ����������i����Η��ɒ[�̊ԈႢ�ł��낤�j�B �I�������ɎQ������ȊO�̂����ŁA�ʂ̌`�ŁA��X�̓������p�����ׂ����낢��Ȍ`���l������B�v�����Ō����A�g�\�r�G�g�^���h�Ƃ��A�t�����X�v�����ɂ́g�N���u�^���h�Ƃ����̂��������B�g����^���h�͉E�h�̉^�������v�����łȂ��Ă��N���Ă���B���ĉ�X�͑n���w��́g�ܕ��^���h�i��ʂɏ@���Ƃ����̕z�������j�ɂ��Ă���ׂ������Ƃ��������i�u�ϗ��̉�v�Ƃ������c�̂�����A�ނ�́u�����̘b�������̉�v�Ƃ������悤�Ȍ`�Ől�X��g�D���āA�@���I�^����W�J���Ă���j�B�܂��A�J���^�������g���Ă���A����ƌ��т��Ă�邱�Ƃ��d�v�Ȍ`�ɂȂ肤��B �ꌾ�Ō����āA���݁A�J���^������ނ��A�J���҂̍L�ĂȖڊo�߂��܂����܂�Ă��Ȃ��i�K�ŁA�����ɂ��Ċv���^����o���A�g�D���Ă������Ƃ������ł���B��`��@�֎����Ƃ��̊g�啁�y�A�w�K��ɑg�D���Ă����������X�Ƌ��ɁA��O�ɌĂт����A�ނ�����W���铬���̖��ł���B��X�͏�ɁA�ǂ̂悤�ɂ��Ď��H�I�ɓ����J���Ă��������l���A�H�v���A�W�J���čs���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B���݁A��X�͈��{�����ɑ��铬���A���̑œ|��ڎw���������Ăъ|���Ă���A�����Ƃ̓����͌����I�Ȍ_�@�Ƃ��ďd�����Ă������A�����I�Ȉ��{�����Ƃ̓����͓��ʂȈӋ`�������Ă���B�������A�����I�ɂ́A�J���ҊK���̏ƁA��X�̗͗ʂ��炵�āA�u���{�����œ|�v�͉�X�ɂƂ��Č����I�ȓ����ɂȂ�Ȃ��̂ł���i�X���[�K���Ƃ��ĂȂ�Ƃ������A���͓����Ƃ��Ắj�A�܂���X�̓����͒P�Ɂu�ΐ��{�����v���⏬������Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���i���̍Ō�̓_�ł́A�Љ��`���u���ڂɌf���ē����v�ƌ����l�����������A�������v���^����]��ɒ��ۓI�ɗ������Ă���A���ʂƂ��Ă�����[�֓I�ȉ^���ɋA�������A����ւ��Ă��܂��낤���������Ă���j�B ����I�Ȋ����������������āA��X�̓����ƌ��т��Ă����ׂ����Ƃ������R�̈ӌ����u�ʐM�v�ŏЉ�����A���������F���͏d�v���Ǝv���B�P�Ȃ锽���{�����ł͂Ȃ��A���邢�͂��������������_�@�ɂ��A��X�̍��{�I�Ȏv�z��l����A�����̓����w�����������I�ȓ������K�v�ł���B�����������Ƃ͊e�x���ł��낢��Ȍ`�ōs���Ă����B�Ⴆ�A�_�ސ�͂Q�̎x�����܂߂Ė��N���̏W����s���Ă���B�����łɌ����A��\�ς���N���ė����������̕��@���u���܂����v�ł������Əq�ׂ����A�������_�ސ�̂������u���܂����v�̊���������B �c�ẮA�Z�~�i�[�����̋�̓I�ȃC���[�W�𖾂炩�ɂ��邽�߂Ƃ��āA���݂̏�̒��ł́A�u������`�ƏW�c�I���q���v�Ƃ��������̂��l������ƌ��������A����͂�������̗�ɂ����Ȃ��B���������e�[�}�ł��Ƃ������Ƃ́A���ʂ���u�W�c�I���q���ӂ��悤�v�Ƃ������ƂƂ͈Ⴄ�B�����ł͂Ȃ��āA���ڂ̐��������Ƃ��ĂłȂ��A���ʁA�g�Z�~�i�[�h�Ƃ����`���ŁA�܂�w�K��c�_�⌟���Ƃ����`���ŘJ���ҁA�ΘJ�҂ɐڋ߂��A�ނ��g�D���čs�����Ƃ�����|�ł���B �u������`�v�Ɓu�W�c�I���q���v���͎��ۂɂ͒��ڂɁA���I�Ɍ��т����̂ł͂Ȃ����A���Y�}�Ȃǂ̃v�`�u�����͂ɂ���āA���Ƃ���Ɉ��ʊW������Ă���B����͔ނ�ɂ���āA�P�X�U�O�N�̈��ۉ���������A�݂̔�������R����`�i���ۂɂ���āA�u���{�̓A�����J�̐푈�Ɋ������܂�A�푈���鍑�ƂɂȂ�v�]�X�j���\���A�ے�������̂Ƃ��ĊW�Â���ꂽ�̂Ɠ��l�ł���B�u���g��v������́A�v�`�u���}�h��s����`�҂炪���ە��ӓ������u�����`�i�쓬���v�ɂ���ւ��A���܂������ƕ��𗧂āA�̂̂��������A����������͔ނ炪��K�I�ɂ���Ă��邱�ƁA�ނ�̊K���I�ŕ��ȗ��ꂩ��o�Ă�����̂ł����āA�������l�ł���B�����u������`�v���W�c�I���q�����ƌ��т�����̂́A���̍��������{�́g�����哱�h�H���ɂ���āA�]���Ă܂��u�t�c����v�Ȃǂɂ���āA�g���@�K�I�Ɂh�A�u���߉����v�ɂ���Ă��Ƃ����Ղɍs���邱�ƂƊW����ɂ����Ȃ��̂����A�v�`�u�����́i�s����`�҂⋤�Y�}�Ȃǁj�ɂ͌���I�œ��I�Ȋ֘A������悤�Ɏv����̂ł���B �g������`�h�i�u���@�͐��{�邽�߂ɂ���v�A�Ƃ��������Y�}��s���h�̌��z�������͂��팾�j�����ɑ傫�ȉe���͂������A���{�����ɔ����鐨�͂̃X���[�K���Ƃ��A���̉^�����K�肷��ŔƂ��Ȃ��Ă���A�]���āA�����������Ɨ��߂ċc�_���邱�Ƃɂ���āA��X�͈��{�����Ƃ̓����𐄂��i�߂�Ƌ��ɁA�v�`�u�����͂Ƃ̓��������s���A�ނ�̓��a����`����ȗ���𖾂炩�ɂ��A�J���҂��҂��������A�g�D���čs���̂ł���B����͈�̋�̓I�ȃC���[�W�ł��邪�A�P���Ȑ��������Ƃ͈Ⴂ�A���݂̋q�ϓI�A��̓I�ȏƏ����̒��ő�O�ɑi���A�g�D���Ă�����̂����Ƃ��ĉ�X�͕]������̂ł���B �W�c�I���q���u�s�g�v�̗e�F�����{��������邱�ƂƁA�u�t�c����v�ł����Ă�������s���邱�Ƃ͓�̕ʂ̖��ł����āA�W�c�I���q���́u���{��푈�̂ł��鍑�ɂ��邽�߂̂��́v���A�����炱��������g���@�K�I�Ɂh���̂́u�K�R�ł����ē��I�Ɍ��т��Ă���v�Ȃǂƌ����͈̂�̃h�O�}�ɁA���킲�Ƃɑ�����̂ł���B ��X�̃Z�~�i�[����X�́g�^���h�̌`�ԂƂȂ蓾��̂́A�Ⴆ�u�W�c�I���q���v�Ɂg�����I�Ɂh�i���Y�}�I�ɁA���邢�́u�X���̉�v�I�ɁA�܂�v�`�u���I�ȁA�瑊�ɁA�h�O�}�I�Ɂj������Ƃ��������̂łȂ��A���ۂɏW�c�I���q�����Ƃ͉����A����ɂ́u������`�v�Ƃ͉�����^���ɍl���A�������A�c�_�����Ƃ��Č���邩��ł���A�����������̂Ƃ��Ă��������ۂɂ�����̂Ƃ��āA�J���ғI�Ő^�ɔᔻ�I���ꂩ��c�_���A���炩�ɂ��A�����������Ƃ�ʂ��ĘJ���ҁA��҂����W��������̂ƂȂ蓾�邩��ł���B ����X�̓����́g�N�w�I�ȁh��b���m�F���� �������������̒��ŁA�c�Ăɑ��āA������`���Ɣᔻ����Ă��邪�A�S�O�ł���B�ŋ߁A�N�w�̖��ő�\�ς𒆐S�ɋc�_�������Ƃ��������B���́u�t�H�C�G���o�b�n�E�e�[�[�v�������o���āA�ϔO�_�ƗB���_�̑Η���]��P���Ȍ`�Ř_���Ȃ��悤�ɒ��ӂ𑣂����B�}���N�X�͗B���_�ɂ��F�X����Ƃ��āA�t�H�C�G���o�b�n�̗B���_�����グ�Ĕᔻ���Ă���B����͏d�v�Ȗ��������Ă���Ǝv���A�ŋ߂��̒Z���e�[�[��ǂݒ����Ă݂��B�t�H�C�G���o�b�n�̗B���_�Ƃ����̂́u�ϏƓI�ȗB���_�v�i�ϏƁF�悻���݂����ɑΏۂ�����j�ɂȂ��Ă���A�܂�A�ނ͎��H�I�Ȋ����Ƃ������̂�]�����Ă��Ȃ��B�B���_�ɂ����ꂱ�ꂠ��A�F���_�ł��A�q�ςɑ���P�Ȃ锽�f�_�Ƃ������̂�����B�q�ϓI���݂������āA���_�͋q�ςɏ]�������f����Ƃ����̂͂����B���������ꂾ���ł́A�ϔO�_��ł��j��A���|���Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��ƃ}���N�X�͌����̂ł���B ���邢�́A�Љ��`�͗��j�I�ȕK�R�ł���A�q�ϓI�K�R���ł���Ƃ����g�B���_�I�ȁh���j�ρi�B���j�ρj�ɂ��čl���Ă݂Ă��A���[�j�����ᔻ���Ă������A�X�g�D���[�x�Ƃ������V�A�̎��R��`�I�\�\�����̓}���N�X��`�I�ł����������\�\�����o�ϊw�҂̗Ⴊ����B�ނ͌��ǃu���W���A�I�l�Ԃɑ����A���V�A�̎��R��`�I�u���W���A�}�i�J�f�b�g�j�̃��[�_�[�ɂȂ����B�X�g�D���[�x�́A���{��`�͋q�ϓI�K�R�ł���Ƌ������Ď�̓I�Ȍ_�@�����Ȃ��������߂ɁA�u���W���A�ɓ]�������Ƃ�������B���V�A�ł͎��{��`���܂����݂��Ȃ��̂�����A�܂��u���W���A�ɂȂ��Ď��{��`�W������A�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����ϔO�ɗe�Ղɓ��B�����Ƃ����킯�ł���B�Љ��`�͂������̂����A����͂������j�́g�K�R���h�Ƃ��Ď�̓I�Ȏ��H�Ȃ��ɁA����g�����I�Ɂh����Ă���i�u�ʕ�͐Q�đ҂āv�j�Ƃ����킯�ł���B ���ł��u���W���A���R��`�҂�v�`�u���C���e�������́A�Љ��`�⋤�Y��`�����j�I�ȕK�R�Ȃ�A�ǂ����Ă݂Ȃ���́\�\�܂��X�̂��Ƃ����\�\�Љ��`�̂��߂ɓw�͂��A�����̂��A�u�K�R�v�Ȃ̂�����A����ȕK�v�͂Ȃ��ł͂Ȃ����A��J���ē����K�v���Ȃ�����̂����X�Ƃ����Κ}�ΓI�Ɍ����̂����A�����l�Ԃ̂ǂ�Ȃ悫�Љ���A�]���ĎЉ��`���܂��\�\���̎����ɂ́A�m���ɗ��j�I�ȏ���������Ƃ͂����\�\�v���I�Ȑl���⎩�o�����J���҂̌����I�A���H�I�ȓ����������Ă����\�ł���A�Ƃ������Ƃ�m��Ȃ������ł���B �t�H�C�G���o�b�n�̗��ꂪ�Ȃ��ᔻ���ꂽ���ƌ����A�ނ͌����Ƃ����̂͊ϔO�I�ɔ��f����Ă���A���ꂪ�@�����Ƃ������_�ɗ��܂��āA�@���̓]�|���͌������E�̓]�|���ł��邱�Ƃ����Ȃ���������A���̌��ʂƂ��āA�P�ɏ@���I�F����p����������̂��ƍl���āA�@���I�ȔF���ݏo��������ϊv������H�I�ȗ���ɂ܂Ői�܂Ȃ���������ł���B�}���N�X�́A���͍���I�ɂ͏@�����̂ł͂Ȃ��Č����ł���A���̌����Ƃ̂������Ƃ����͎̂��H�I���ł���Ƌ������Ă���A�ꌾ�ł����A�t�H�C�G���o�b�n�̗���́u�ϏƎ�`�v�ł���Ɣᔻ����Ă���̂ł���B�l�Ԃ́g�ΏۓI�h�A���H�I�ȑ��݂ł���A�܂��ɂ����������݂Ƃ��Đl�Ԃł���ƁA�}���N�X�͎��̂悤�ɋ������Ă���B �w����܂ł̂�����B���_�\�\�t�H�C�G���o�b�n���܂߂ā\�\�̎�v���ׂ́A�ΏہA�����A�����������q�̂́A�܂��͊ϏƁk�����l�̌`���̉��ł̂ݑ������A�����I�Ȑl�ԓI�����A���H�Ƃ��Ď�̓I�ɑ������Ă��Ȃ����Ƃł���B����̂ɁA���̔\���I�ȑ��ʂ͒��ۓI�ɁA�B���_�ɑΗ����ĊϔO�_�ɂ���ā\�\�������ϔO�_�́A���R�̂��Ƃ����A�����I�E�����I�������̂��̂�m���Ă��Ȃ��\�\�W�J����Ă����B�t�H�C�G���o�b�n�͊����I�ȁA�v�ғI�q�̂���^�Ɂk�����I�Ɂl��ʂ��ꂽ�q�̂�v������B�������ނ͐l�ԓI�������̂��̂�ΏۓI�Ȋ����Ƃ��đ����Ă��Ȃ��B�c�c����̂ɔނ͊v���I�Ȋ����A���H�I�ɔᔻ�I�Ȋ����̈Ӌ`�𗝉����Ȃ��B�x ������A�t�H�C�G���o�b�n�͈�ʓI�ȗ��_�I����ɗ��܂��Ă��āA�ϏƓI�A�ϑz�I�ł����Ď��H�I�ł͂Ȃ��Ɣ���邱�ƂɂȂ����B�}���N�X�̓t�����X�̗B���_�����������`�ł��̂悤�Ɍ������̂ł���A�t�H�C�G���o�b�n�̗���͎s���i�u���W���A�j�̗���ł����ĘJ���҂̗���ł͂Ȃ��ƌ������ᔻ�����̂ł���B�܂�t�H�C�G���o�b�n�͐l�Ԃ��A�l�Ƃ��Ē��ۓI�ɂƂ炦�Ă��āA�����I�ȎЉ�I�Ȑl�ԂƂ��ẮA���H�I��̂Ƃ��Ă͗������Ă��Ȃ��Ƃ����̂ł���B �ϏƓI�A�I�łȂ��āA���H�I�łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂́A�g�F���_�h�ɂ����Ă������ł���B�P���Ȕ��f�_�ł͂Ȃ��āA�l�Ԃ����ڂ̌������A���ۂ�{���Ɂi�T�O�I�Ɂj��������ɂ́A��̓I�Ȍ_�@���K�v�ł���B�_���������Ƃ������l�ł���A�����܂Ō����⎖������o������͓̂��R�Ƃ��Ă��A���ۂ��q�ׁA���q���邾���ł́\�\���ꂾ���ł́A�����܂�Ώۂɂ����I�ɁA���R�����I�ɁA���R�ƊW���Ă��邾���ł���\�\�A�܂��{���̔F���ɁA�܂�{���̘_���ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���A����Ɏ�������I�ȊW�Ƃ��Ăǂ������A�������邩�����ŁA���̂��߂ɂ͎������g���H�I�Ɂh�������A���͂��A�������A�T�O�Ƃ��Ď����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B �}���N�X�̃t�H�C�G���o�b�n�ᔻ�̊j�S�́A��X���A���H�I�ɐ�����̂��A����Ƃ��������g�q�ώ�`�h�ɁA�ϏƎ�`�I�ɐ�����̂��Ƃ������A�܂��ɐl�ԓI���݂̍���ɂ��������ł���i�l�Ԃ̎��H�I�ȑ��ʂ͗B���_�ɂ���ĂłȂ��A�ϔO�_�ɂ���Ăނ���ϋɓI�ɓW�J����ė����Ƃ����}���N�X�́A����Ӗ��ł́g�����ׂ����t�h���m�F���邽�߂ɁA�t�H�C�G���o�b�n�E�e�[�[�����Љ��߂ēǂ݁A���̈Ӗ����n�l���ׂ��ł���j�B ����������X�̎��H�I������������邽�߂ɁA�c�Ắu���R��`�v�̈�|��搂��Ă���B������c�Ă̗��ꂪ�����I���Ƃ����ᔻ�͓������Ă��Ȃ����A�����ԈႤ�B���{��`�̔ᔻ�I�A���o�I������Nj��̒��ŁA�n�߂ĎЉ��`�̓W�]�����܂�Ă���̂����A���������W�]�͒P�Ȃ闝�z��`���A��z�I���i�ϔO�I���]�X�j�ƌ������Ƃ͂ł��Ȃ��B��X�͎��{��`�Љ�̒��ɐ����Ă���l�ԂƂ��āA��X�̎��H�I�Ŋv���I�ȗ���̍�����m�F����K�v������B �܂��Ō�ɁA�c�_�̒��ŁA��X�̓����̑����Ƃ��āA�u������`�I�v�^���ł��������Ƃ���{�I�Ȍ��ׂł���A���ꂩ��̕����]�����K�v�ł��邩�̈ӌ����o���ꂽ���A����ɑ��ẮA���u��u������`�I�v�ł��������琨�͂��L�т��A�����܂ł��Z�N�g�ɗ��܂�̂��Ƃ������悤�ȑ����ɂ͔��ł���A��X�͂��Ă���������Ӗ��ł́u������`�I�v�\�\�������A�u���W���A�I�ȁi�u�s�ꌴ����`�v�j�A���邢�͏@���I�ȁi�C�X��������L���X�g���̌�����`���X�j�u������`�v�Ƃ͉����䂩����Ȃ����\�\�ł���A���������ĉ�X���u������`�v���Ƃ����̂��͕�����Ȃ����A��X�͘J���҂̊K�������̗���ɒ����ł���A�܂��v���I�Љ��`�A���Y��`�̌�����ێ����A�}���N�X��`�̍������������Ƃ����_�ł́u������`�v���̂��̂ł����āA���Ԃ���ŞB���ȁA�v�z�I�ȓ��I����⋭���ӎu�̈�v���Ȃ��悤�ȓ��a����`�̑g�D������Ă��A���C���^�[�̗�������܂ł��Ȃ��i������݂̋��Y�}�A�X�^�[���j�X�g�����l�ł��邪�j�J���҂̉�������ɂƂ��ă}�C�i�X�̈Ӌ`���������Ȃ��̂ł���B�u��X�͑��C���^�[�̕���̋��P�����߂Ƃ���A�����̊v���^���̌o���܂��ē����Ă���̂ł���v�Ƃ������m�Ȕ��_���Ȃ��ꂽ���Ƃ��A�t�������Ă��������B
�@���P�A��X�̑O�ɒ�N���ꂽ���_�ۑ� �@�Љ��`�ɂ����镪�z�̖��Ɗ֘A���āA�����i�́u���l�K��v�������ɍs�����Ƃ����e�[�}�����̂Q�A�R�N�A��X�ɂƂ��Č��������ׂ��d�v�ȗ��_���A�]���Ă܂��c�_���d�˂��A��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ۑ�Ƃ��đ��݂��Ă����B�l����́A����ɐ�s����u�i�L�p�J���ɂ��j�ߋ��̘J���̈ړ]�v��肪���������̏o���_�ł������Ə،��������A�тƂ��Ă͂��̎��o�͊������B���������Ȃ��Ă݂�Ƃl����̌��������Ƃ����������Ǝv���i���Ȃ��Ƃ��A�d��Ȋ֘A�����g�O����h�ł������j�A�Ƃ����̂́A��X�������\�\�������A���_�I�ȉ����ɗ��܂�̂����\�\��Nj����Ă����u�����i�̉��l�K��v�������ɍs���̂��Ƃ����e�[�}�́A�u�ߋ��̘J���̉��l�ړ]�v�Ƃ����ϔO�Ɓ\�\���̎~�g�����Ɓ\�\�[���W���Ă��邱�Ƃ����܊m�F����邩��ł���B �@���������Љ��`�ɂ���������i�́u���l�K��v�\�\���ڂɘJ�����ԁi���̐��Y�ɕK�v�ȎЉ�I�J���̒����j�ŌX�̏����i�́u���l�v��\�����A�K�肷��\�\�Ƃ����ۑ�́A��\���N�O�A�܂�l�����I���́A�g�s���`�I�h�Љ��`�Ƃ������u���W���A�T�O���Z�����A�͂т��鎞��I���̒��ŁA�����A��X���\�\�����傰���Ɍ����A���E���ʼn�X�݂̂��\�\�A�ނ�ɔ����A�u����͉\�ł��邵�A�܂��Љ��`���Љ��`�ł��邽�߂ɂ́A����͎�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ǝ咣�������Ƃ���n�܂����̂ł���B �@�����́A�X�^�[������`�I�i�܂肦���́j�g���Y��`�h�^���̎����{���̎���A�\�A�M�̉�̂Ⓦ���v����\�A���Y�}���͂̕���Ȃǂ̐��E�j�I�ȑ厖��������������ł���A����ȑ傫�ȗ��j�̓]���_�̒��ŁA�u�Љ��`�v�������������ƂƎ������ɁH�M�����݁A���`������Ă����\�A�Ȃǂ��n�߁A���E���̑����̃X�^�[������`�҂����A�܂苤�Y�}�̘A���\�\�g�X�^�[���j�Y���h�������������ł��Ȃ��āg�u���W���A�h�ɓ]�������A���\�\���A�Љ��`�̕��z���܂��u���l�K��v�ɂ���ĂȂ����̂ł͂Ȃ��A����Ȃ��Ƃ͕s�\���A�u�s��o�ρv�̓����ɂ���āA�܂�X�~�X�̌����u�_�̌��������v�ɂ���āA���������`�ł̂݉\�ł���A�u�s��o�ρv�̂܂܂ɔC����ׂ����A���ꂪ��Ԃ��܂�����Ă����A�Ȃǂƈ�ĂɌ����͂₵�A�u�s���`�I�Љ��`�v�Ƃ������ϑz��A���{��`�ɂ��Љ��`�̋~�ςƂ��������b�ɖ����ɂȂ��Ă����̂ł���B �@��X�͂���ȃX�^�[������`�҂����ɔ������A���ꂪ�ł��Ȃ��Ƃ����̂́A�ނ炪�u���W���A�ɑ����A�]���������炾�ƌ��_�������A���������̎��́\�\�����Ă��̌�A�l�����I�߂����̒����Ԃ����Ɓ\�\�A���ۂɁA�Љ��`�ɂ���������i�́u���l�K��v�ɂ��āA�]���ČX�̏����i�������ɕ��z����邩�́g�@���h�ɂ��Ę_���I�ɖ��炩���A��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B �@��������X�͈��N�̘J���҃Z�~�i�[�ɂ����āA����ΐ^�����ʂ��炱�̖����N���A�ꉞ�̉����ɓ��B�����̂����A���������{���l�i�u�ߋ��̘J���v�j�́u�ړ]�v�Ƃ������i�L�p�J���ɂ��j���A�]���āu���{���l�v�̖����������邱�Ƃ��ł��Ȃ������A�܂肻�̖�������u�I�グ����v�Ƃ����`�ŁA�Ƃ肠�������_���o�����Ƃ������Ƃł���B �@��������X�́A���N�X���̑�P�P����̋c�_��A���̋c�_�̑��������܂��āA���̖��ɂ��Ė��m�Ȍ��_���o���A�������ׂ��Ƃ������Ă���ƍl����B �@���Q�A���r���\���l�̏ꍇ�Ɣ��B�������ƎЉ�̏ꍇ �@�������Ǘ��������r���\���E�N���[�\�[�̏ꍇ�ƁA�Љ��`�Љ�̏ꍇ�́u���z�v�@�����{���I�ɂ͈�v����Ƃ��Ă��A����I�ȈႢ������A���̋�ʐ����܂����m�ɖ��炩�ɂ���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@�l�X�͎��{��`�I���Y�Ƃ͋ɓx�ɔ��B�������ƎЉ�ł��邱�Ƃ�Y���̂ł���A���ꂱ��̐��Y��i�Ƃ����A�����i�Ƃ����A�O�ꂵ���Љ�I�ȕ��Ƃɂ���Ă̂ݐ��Y����A�܂��u���z�v����Ă��邱�Ƃ�Y���̂ł���B���������}���N�X�̍Đ��Y�\���i�P���Đ��Y�j�̂U�O�O�O�̘J���i�ҁj�����Y��i�Y���A�R�O�O�O�̘J���i�ҁj�������i�̐��Y�ɏ]�����邱�Ǝ��́A�ł������I�Ō���I�ȎЉ�I���Ƃł���B �@�����ĕ��ƂƂ͎Љ�I�ȕ��Ƃł����āA�Ⴆ�Όl�I�ȕ��Ɓ\�\�Ƃ������A����̘J���̕����\�\�Ƃ��������ƂƖ{���I�ɕʂȑ��ʂ�����Ƃ������Ƃ�Y��Ă���A���邢�͌��Ȃ��ł���B �@���r���\���̂悤�ɌǗ������l�̏ꍇ�ɂ��ẮA�}���N�X���w���{�_�x�̖`���Ř_���Ă���B�����Ń}���N�X�́A���͒P�ɔތl�̘J���̕����A�z���ɂ����Ȃ��Ƃ��Ď��̂悤�ɘ_���Ă���B �@�u�ނƂĂ����낢��ȗ~�]�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���A���������ē�������A�Ƌ�������炦�A���}���炵�A��������ȂǁA���낢��̎�ނ̗L�p�J�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�c�c�K�v���̂��̂ɔ����āA�ނ͎����̎��Ԃ𐳊m�Ɏ����̂��낢��ȋ@�\�̊Ԃɔz������悤�ɂȂ�B�ނ̑S�����̂����łǂꂪ���傫���͈͂��߁A�ǂꂪ�������͈͂��߂邩�́A�ڎw���L�p���ʂ̒B���̂��߂ɍ������Ȃ���Ȃ�Ȃ�����̑傫���ɂ���Ē�܂�B�o�����ނɂ����������v�i�S�W�T���A�P�O�Q�ŁA���X�P�Łj�B �@���r���\���Ǝ��{��`�I�Љ�i��ʂɁA���B���������̎Љ�j�̈Ⴂ�́A���r���\���̏ꍇ�A�ތl�̕K�v�J���̕����Ƃ��Č���邱�Ƃ��A���B�����Љ�ł͑����̘J���҂̎Љ�I�ȕ��ƂƂ��Č���A���������`�ŎЉ�S�̂̐��Y���̐��Y�ɕK�v�ȘJ���̕������A�z�����Ȃ����\�\�����Ă���ɑΉ����āA�����i�́u���z�v���\�ƂȂ�A�Ƃ����Ă������ł́A���{��`�ƎЉ��`�̏ꍇ�A��̍��{�I�ȋ�ʂ�������̂����\�\�Ƃ������Ƃ����ł���B �@���r���\���̏ꍇ�Ō����ƁA�Ⴆ�Δނ͐����čs�����߂ɁA�����A�U���Ԃ͋���߂邽�߂̓�������i��ʓI�Ɍ����Ȃ�A���Y��i�̐��Y�ł���j�A�܂�����ɂR���Ԃ͐��C�ɏo�ċ��ɏ]�����A�������Đ������A�����Ă������߂ɂP�O�C�̋���߂����i�����i�̐��Y�ł���j�Ƃ��悤�B�ނ̈���̘J���ʂ͂X���Ԃł���B �@�����A�������Ə����̂��ƂɁA�X�l�̋����̎Љ����A�����\�\�܂�X���ԁ\�\�A�U�l������߂邽�߂̓������邱�Ƃɐ�O���A�����A�c��̂R�l���X���ԁA����߂邱�Ƃɐ�O���A���������Љ�I�ȕ��Ƃ̂��ƂɂX�O�C�̋���߂����Ƃ��悤�B �@���ʂƂ��āA��̏ꍇ�Ƃ��A�P�l������̋��͂P�O�C�ł���A�l�X���������A�����Ă������߂Ɏx�o�����J���ʂ������ł���B�Ⴂ�͑��J���ʂ��P�l�ɂ���ĒS��ꂽ���A�X�l�ɂ���ĕ�������A���Ƃɂ���ĒS��ꂽ���Ƃ������Ƃ����ł���B�X�l�̋����̂̏ꍇ�́A�U�l�͓������炸�A����߂邱�Ƃɂ͒��ڂɂ͉���W���Ȃ������ɂ�������炸�A���ꂼ��P�O�C���̋��ɑ��镪�z���邱�Ƃ��ł��邪�A����͔ނ̓�������J��������߂�J���Ɓu���I�Ɂv����ł���A�]���đ��J���̒��ł̔�d�ɏ]���ċ��̕��z���邱�Ƃ��ł��邩��ł���B�ނ̓�������J���̂R���̂P�́A�J�����Ԃŕ]������Ȃ�A�����㋛��߂�J���ł��邪�A�����A����߂�R�l�̘J���̂R���̂Q�́A�����㓹�����邽�߂̘J���ł���B�u���l�K��ɂ�镪�z�v�Ƃ́A��{�I�ɂ����������e�ɂ���ė�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B �@�܂��X���A�Љ��`�Љ�ɂ�����i��悪�p�₳��A�J���̉�����������ꂽ��́j�A�����i�i��������j�̕��z�̂��ƂƂȂ鐶�Y���i�����ł͏����i�j�́u���l�K��v�̊T�O�Ƃ́A�ȒP�Ɍ����A���̂悤�Ȃ��Ƃł���ɂ����Ȃ��B �@�����̂̂X�l�̍\�������A�X�J�����̑��J���ɂ���Ċl�����ꂽ�X�O�C�̋����A�݂Ȃ��ꂼ��\�\���Y��i�ł��铹���������l�������A�����i�ł��鋛���ɏ]�������l�������\�\�����ɂP�l�P�O�C��������ƌ������Ƃ͒N�̖ڂɂ��P���ŁA���R�̂��ƂƂ��Č����B����̓��r���\�����P�l�œ�����܂����A���ꂩ�狛���Ɏ�肩�����ĂP�O�C�̋�����ɂ����̂Ɠ������Ƃɂ����Ȃ��̂����A�u�ߋ��̘J���v�Ƃ��A���́u�ړ]�v�Ƃ��������h�O�}�Ɏ��t���ꂽ�l�X�i�܂�u���W���A���N�����j�ɂ́A���̊ȒP�Ȑ^���ɖڂ��s���Ȃ��̂ł���B �@���̋����̂ł́A�R�l���X�O�C�̋���߂����̂����A�P�l������R�O�C�ł͂Ȃ��P�O�C�����ƒ�Ɏ����A�邱�Ƃ������Ȃ��̂����A����͂X�O�C�̒��ɂ́A�����������l�X�̘J�����܂܂�Ă��邩��ł���A�]���Ďc��̂U�l���܂��P�O�C����铖�R�̎��i�����邩��ł���A�Ƃ����̂͂U�l���܂��A�R�l�Ɠ������̒��ۓI�Ȑl�ԘJ�����A�Љ�I�ȕ��Ƃɂ���ĒS��������ł���B�R�l�̘J���̂R���̂Q�́A�����I�Ɂi�u���l�K��v�Ƃ��Ắj��������J���ł���A�܂����̂R���̂P�������������J���ł������̂́A�U�l�̘J���̂R���̂Q����������J���ł���A�R���̂P�������I�Ɂi�u���l�K��v�Ƃ��Ắj����߂�J���ł������̂Ɠ��l�ł���B �@���R�A���B�������{��`�̏ꍇ�\�\�}���N�X�Đ��Y�\���i�����ł́A�g�����́h�Ƃ��Ē��ۂ���Ƃ����C�����s���Ă���B�}�\�Q�Ɓj �@�}���N�X�̍Đ��Y�\���i�P���Đ��Y�j�ɂ���čl�@���Ă���{�I�ɓ����ł���B �@�����Y�͂X�O�O�O�ł���A�U�O�O�O�����Y��i�A�R�O�O�O�������i�Ƃ��Đ��Y����Ă���B����������܂ł́A�ꌩ���āA�R�O�O�O���u�������J���v�̉��l�ł���A�c�肪�u�ߋ��̘J���v�̉��l�A���̈ړ]���Ă������l�ł��邩�Ɍ����A�܂��������Ȃ���Ă����i�X�^�[������`�҂͂���ȕ��Ɍ����͂₵�Ă����j�B �@�������U�O�O�O�̘J�������Y��i�Y�����̂ł����āA�c��̂R�O�O�O�̘J���͏����i�Y�����̂ł���A���܂蕶��Ƃ��Č����Ă���u�������J���v�Ƃ́A�����i�̐��Y�ɔz�����ꂽ�J���Ƃ������Ƃł����Ȃ��̂ł���A�܂��u���J���v�Ƃ́A���Y��i�̐��Y�ɏ[�p���ꂽ�J���Ƃ������Ƃł����Ȃ��B�Ƃ���Ȃ�A�����ł́u�������J���v�Ƃ��A�u���J���v�Ƃ������ϔO���Ӗ��������͖̂��炩�ł���B�����i�Y����J�����u�������J���v�ł���A���Y��i�Y����J�����u���J���v�A�ߋ��̘J���ł���A�Ȃǂƌ�����͂����Ȃ�����ł���B �@�����X�̃u���W���A�̖ڂɂ́A���Y��i�̂��߂̘J���́u�ߋ��̘J���v�Ƃ��āA�܂莑�{���l�i���̑O��Ƃ��Ă̔�p���i�j�Ƃ��Č��ۂ���̂����A�����o�ϊw�͂���ȃu���W���A�����̈ӎ��f���A�g���_���h���邾���ł���B �@���Y��i�Ƃ��čĐ��Y���ꂽ�U�O�O�O�́i�J���ʂ̊܂܂��j���Y���́A�g�p���l�Ƃ��Ă͐��Y��i�ł��邪�A�u���l�v�Ƃ��ẮA�S�O�O�O�̐��Y��i�ƂQ�O�O�O�̏����i���Đ��Y���ꂽ���̂ł���B �@���l�ɁA�R�O�O�O�̏����i���܂��A�g�p���l�Ƃ��Ă͑S�ď����i�ł��邪�A�u���l�v�Ƃ��Ă͏����i�͂P�O�O�O�݂̂ł���A�c��̂Q�O�O�O�͐��Y��i�ł���B �@�]���ău���W���A�Љ�ł͐��Y��i�̂��߂Ɏx�o���ꂽ�Q�O�O�O�̉��l�i�J���ʁj�ƁA�����i�Ɏx�o���ꂽ�Q�O�O�O�̉��l���u�����v����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂����A�Љ��`�ł͂����R�O�O�O�̏����i���X�O�O�O�̘J���i�ҁj�ɕ��z�����A�܂�u�J���ɉ����ĕ��z�v����邾���ł���B �@�]���āA�Љ�̑S�̂ɂ����Ă͖��͊ȒP�ł���A���Y��i����邱�Ƃɏ]�������U�O�O�O�Y����J���҂͂R�O�O�O�̘J���҂̐��Y���������i�̂R���̂Q���A�܂�Q�O�O�O�J�����̕��z���鎑�i�����̂ł���A�R�O�O�O�̏����i�Y�����J���҂͂��̑S���ł͂Ȃ��R���̂P���A�܂�P�O�O�O�J�����̏����i����鎑�i��L���邾���ł���B �@�l�͂��������A���̊��ԁi�N�X�j�A�x�o���ꂽ�i�g�Ώۉ��h���ꂽ�j�J�����X�O�O�O�ł͂Ȃ��ĂR�O�O�O�ł���ƌ�����邪�A����͗�́u�������J���v�̊ϔO�\�\�X�^�[������`�҂����������͂₷�Ԉ�����ϔO�\�\�ɂƂ���Ă��邩��ł���B�������R�O�O�O�Ƃ͑��J���̓��̏����i�̐��Y�̂��߂Ɏx�o���ꂽ�J���ɂ������A���Y��i�̂��߂̘J����������Α��J���́A�R�O�O�O�łȂ��ĂX�O�O�O�ł���B�u�������J���v�̊ϔO�́A�����N�X�Ɏx�o�����A�����̑��J���Ɨ�������Ȃ�A���̌��t���Ӗ����������邪�A�����i�Ɏx�o���ꂽ���̂Ɖ��������A�s�����ȊϔO�ɂ����Ȃ��B �@�����ł��łɕt�������Ă����A�}���N�X�́w���{�_�x��Q���̍Đ��Y�\���̗��_�ɂ����ẮA��{�I�ɁA���Y��i�i���{�j�́u�L�p�J���ɂ�鉿�l�ړ]�v�Ȃǂƌ��������Ƃ́A���R�ł͂��邪�S�����ɂ��Ă��Ȃ��i�q�ϓI�ɁA���ɂȂ�͂����Ȃ��j�B �@�����i�Y����J���͂R�O�O�O�ł���A�܂�����������J���i�ҁj���R�O�O�O�ł����āA�������āu���l�_�v�ɂ��܂��K�����Ă���Ƃ������ϔO�́A�ꌩ���Ă܂Ƃ��ł���A���ɂ����Ƃ��Ɏv����̂ő��l�̎��ɓ���₷�����A�������Љ�͂܂��U�O�O�O�̐��Y��i�̐��Y�ɂ��J�����x�o���Ă���\�\������Ȃ��\�\�̂ł����āA���ۂɂ͎Љ�͂����̐��Y��i���N�X����Ă���̂ł����āi�l�I����ł͂Ȃ��A���Y�I����ł��邪�j�A�O�L�̊Ԉ�����ϔO�́A�������Y��i�̐��Y�̂��߂̘J�������A�Y�p�����Ƃ���ɑ��݂�����ɂ����Ȃ��i�ǂ����Łu�X�~�X�̃h�O�}�v�ɒʂ���ϑz�ł��낤�j�B �@�����ɂ́A�Љ�͂U�O�O�O�̐��Y��i�Y����J���ƁA�R�O�O�O�̏����i�Y����J���ɁA���J�������Ă���̂ł����āA���������g���Ɓh�̒��ŁA�����i�̔z�����܂��g���@���I�Ɂh�ѓO���Ă���̂ł���B���Ȃ킿�X�l�ɂ��Č����Ȃ�A�e�l�̓��r���\���Ɠ��l�ɁA�l�I�J���Y��i�̂��߂ɂR���̂Q���A�����i�̐��Y�̂��߂ɂR���̂P���x�o���Ă���A�܂肻��ȕ��Ɏ���̘J�������Ă���Ƃ������Ƃł���B�����炱���A���Y��i�Y����J���ƁA�����i�Y����J�����g���Ɓh�̒��Ŏx�o�����Ƃ��A���Y��i�y�я����i�̌����������͔z�����s���邵�A�s���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���i�������Љ��`�ł́u�����v�Ƃ������A�����i�́u�z���v�������́u���z�v���s����ƌ����ׂ��ł��낤���j�B �@���Y��i�Y����J���҂ɂ��Č����A���̘J�����u���l�v���猩��A���Y��i�̂��߂ɂR���̂Q�ł���A�����i�̂��߂ɂR���̂P�ł��邵�A�܂������i�Y����ꍇ�������ł���A�����炱���A���Y��i�Y����J���̂R���̂P�ɑ�����������i�Ɍ�����L����̂ł���A�����A�����i�Y����J���҂͎��琶�Y��������i�ɑ��ĂR���̂P����������L���Ȃ��̂ł���B�܂�X�O�O�O�̘J���ɑ��āA�S�Ă̐��Y�҂͂��̘J���̂R���̂P�����A�����i�ɑ��Č�����L����̂ł��邪�A�����ł͂��ׂĂ��g���l�@���h�ɓK�����Ă���̂ł����āA����ȊO�͉����Ȃ��ƌ����Ă������Č��������ł͂Ȃ��B �@���ꂪ�Љ��`�Љ�ɂ�����u���l�K��i�����i�Y����̂ɗv�����J���ʁj�ɂ��v�A�����i�̕��z�̊�{�I�ȓ��e�ł���A�@���ł���ɂ����Ȃ��B �@���S�A�S�̂̏ꍇ�ƁA�X�̏����i�̉��l�K��͕� �@��X�̋c�_�͂�������n�܂����̂����A�����������ɗ��܂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�Ƃ����̂́A����͑S�̂Ƃ��Ă̏����i�̕��z�͊ȒP���Ă��Ƃ��Ă��A�X�̏����i�̏ꍇ�͂ǂ��Ȃ̂��A�X�̏����i�́u���l�K��v�͂����ɂȂ����̂��A�Ƃ�����肪�ȒP�ɂ͉�������Ȃ������A�܂藝�_�I�ɐ����ł��Ȃ���������ł���B�����i�������̈��ނȂ�\�\��X�̑z�肵���X�l�̋����̂̂悤�ɁA�������Ȃ�\�\�����͊ȒP���Ăł������B����������ł͏����i�͐獷���ʁA�����A���\��������A���邢�͖�����ƌ�����قǂɑ��ʂł���B �@�����������W�����Љ�ł́A�ʂ̏����i�͌ʓI�ɋK�肳��邵���Ȃ��̂ł���A�Ƃ����̂́A�����i�́u���l�K��v�́A�����i�̐��Y�̂��߂ɕK�v�Ȑ��Y��i�́u���l�v�i�J���j�ƁA���ڂɏ����i�ɔ�₳�ꂽ�J���̘a�ȊO�ł͂Ȃ��̂����A�X�̏����i�̉��l���́A���̑傫���͐獷���ʂł���A�܂���̌_�@�̔䗦���܂��݂ȈႤ���낤����ł���B �@�����Y�ɂ��Ę_����Ȃ�A�u���l�K��v�̖��ɂ͂ǂ�ȍ�����Ȃ��B���������Y���́A���������Ă܂��X�̏����i�̐��Y�ɂ����Ắ\�\������Y��i�̏ꍇ�ł���{�I�ɓ��������A��X�͎Љ��`�ɂ����镪�z�@���̔������ۑ�ł��邩��A�����i�ɂ��Ę_���邱�Ƃɂ��ā\�\�A��̂��Ƃ����ɂȂ�B �@��́A�X�̏����i�̉��l�i���Y�ɕK�v�ȘJ���ʁj�̑召�ł���B���傫�ȘJ���ʂ̏����i�͏������J���ʂ̏����i�����傫�ȘJ���ʂɂ���āu�����v�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��i���z����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��j�Ƃ������Ƃł���B�Ⴆ�Ώ�p�ԂP�䂪�Q�O�O�̉��l�ł���A�g�ш��Q�ł������Ƃ���Ȃ�A��p�Ԃ͌g�тP��̂P�O�O�{�̘J�����Ԃɂ���āu������v���Ƃ��ł���A���邢�͂P�O�O�{�̘J�����Ԃƈ����ւ��ɂ̂ݎ�ɂ��邱�Ƃ��ł���Ƃ������ƂɂȂ�B �@�����炱���A�Љ��`�̕��z�ɂ����Ă͂܂��u���l�K��ɂ�镪�z�v�ƌ������ƂɂȂ邵�A�Ȃ炴��Ȃ��̂ł���B�Љ��`�ł̌����́A�Љ�ɗ^���������̎����̘J���ɂ���Đ��Y���ꂽ���Y���������̂��̂ƂȂ�A�Ƃ������Ƃł���B�������A�Q�O�O�́u���l�v�̏�p�Ԃ���ɂ���l�́A�N�ԘJ�������ɂQ�O�O�ł���Ƃ���Ȃ�A��p�Ԃ������Ď�ɂ����琶���Ă������Ƃ��ł����A�쎀���邵���Ȃ����A�g�т��u�������v�����̌l�͂܂��P�X�W�̘J���ʁi�ɑΉ���������i�j�ɑ��錠���������Ă��邩��A�]�T�������Đ������A�����Ă������Ƃ��ł���B�O�҂͂������Ȃ��u���[���ł��g�ށv�����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�i�����Łu���[����g�ށv�Ƃ����̂͂��Ƃ��ł����āA�Љ��`�ł͕ʂ̌`����邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��j�B �@������A���ӂ��ׂ����Ƃ́A�X�̐��Y���͂��̎��R�I�ȁu�L�@�I�\���v���A�܂�u���l�v�\���̔䗦���قȂ��Ă���A���ς��炸��Ă���ƌ������Ƃł���B �@�Ⴆ�A�R���P�O�L���Ə�p�ԂP��́u���l�K��v�͔@���A�Ƃ�����������Ă݂悤�B �@���҂Ƃ��A���ڂɂ��̐��Y�Ɏx�o���ꂽ�J���͂P�O�Ƃ��悤�B�������R���Y���邽�߂̐��Y��i�Ɏx�o����Ă���J���ʂ͂P�O�Ƃ��A���������Ԃ̕��͂T�O�Ƃ���ƁA�R���P�O�L���͂Q�O�̘J���ʂƂ��ċK�肳��邪�A���������ԂP��͂U�O�Ƃ��ċK�肳��邵�A���ꂴ��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�B�����J���ʂɂ���Ē��ڂɂ͐��Y����邪�A�R���P�O�L���͂Q�O�̘J���ʂɂ���Ď�ɓ���邱�Ƃ��ł��邪�A�����Ԃ̕��͂U�O�̘J���ʂɂ���āu�����v�K�v������\�\�������꓾��A���邢�͂��̘J���ʂɂ���ĕ��z����邱�Ƃ��ł���\�\�Ƃ������Ƃł���B �@�R���Y���鐶�Y��i�̘J���ʂ͌����I�Ȃ��̂ł���A���Y��i����ɂ����Ď�����Ă���A�܂���p�ԂY���邽�߂̐��Y��i�̘J���ʂ������ł���A�������������̌v�Z�͏����ɋZ�p�I�Ȃ��̂ł����āA�T�O���͂����肵�Ă���Ȃ�A�ǂ�ȎЉ�ł��A�����ł��Ȃ��Ηe�Ղɂ�邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�����Ă��������v�Z���Z�p�I�ɉ\�Ȃ̂́A���Y��i�Y����J�����A�����i�Y����J�����\�\�܂��̎Љ�I�ɕK�v�Ȑ��Y���Y����J�����\�\���I�ɓ���ł����ʓI�ɈقȂ邾���́A���ۓI�l�ԘJ���ɊҌ�����Ă��邩��ł���A�������̂��Ƃɂ����Ȃ��B �@�P��̏�p�ԂY����J�����A���ɃR���̈��ʂY����J���Ɠ������Ă��A���ۂɂ͏�p�Ԃƌ��������J���ʂ̓R���̉��{�A���\�{�ɂ��Ȃ肤�邵�A�܂��Ȃ��ē��R�ł���A���ꂱ���������I�ł���A�Ƃ����̂́A��p�ԂɊ܂܂��\�\���̐��Y�ɕK�v�ȘJ���ʁ\�\�́A������p�Ԃ����邽�߂̘J���ł��邾���ł͂Ȃ��A����ɉ����āA���̏�p�Ԃ̐����ɕK�v�Ȑ��Y��i�́u���l���J���ʁv���܂��Đ��Y����A�v���X����Ă��邩��ł���B��p�Ԃł͂��̕����̔�d���R���������ΓI�ɑ傫���̂ł���B�����Ă����������҂̌��u�́A���j�I�Ȃ��̂ł������i�����Ă��ꂪ���Ɏ��R�I�Ȍ_�@�ɂ����̂ł������Ƃ��Ă��\�\�Ⴆ�Γy�n���Y���́u���l�v�͖L�x�̈Ⴂ�ɂ���ĈقȂ蓾��j�A�_�Ƃ̋@�B����Ȋw�Z�p�̉��p�E�K�p��o�c�̑�K�͉����X���i�݁A���Y�����㏸����Ȃ�A����ɔ�Ⴕ�ċ}���ɏk�܂�A�k�����Ă������A�s�����Ƃ��ł��邾�낤�B �@���T�A�u�������J���v�Ɓu�ߋ��̘J���v�i���{���l�j�y�ь�҂́u�i�L�p�J���ɂ��j�ړ]�v�_�̋��U���i�u���W���A�I�ϔO�j �@���������F�����甽�Ȃ��Č���A�u�������J���v�Ƃ��u�ߋ��̘J���v�Ƃ������ϔO���A�ǂ�Ȃɕs���ĂȂ��̂ł��邩���A�J���҂̊ϓ_���炷��Ȃ狕�U�̊ϔO�ł������邱�Ƃ����Ăɖ\�I����Ă���B�Ƃ����̂́A���Y��i�Y����J�����A�����i�Y����J�����݂Ȍ����I�ł���A���Ɏ��I�ɓ���̒��ۓI�l�ԘJ���Ƃ��Č��ݓI������ł���A���̈Ӗ��ł́u�ߋ��̘J���v�Ƃ��������̂͑��݂���]�n���Ȃ�����ł���A�]���Ă���Ȃ��̂��u�L�p�I�J���v�ɂ����̂��A���ɂ�邩�͒m��Ȃ����u�ړ]�v�����͂����Ȃ��̂ł���B�u�ߋ��̘J���v�Ƃ��������̂́A�����u���W���A�Љ�ł́u���{���l�v�Ƃ������`�ő��݂���̂����A����Ȃ��͉̂ʂ����ĎЉ�I�S��i���_���q�̈��j�ł͂Ȃ����ƁA��X�͋^���Ă�����ׂ��ł��낤�B �@�u���{�v�Ƃ́\�\�u�ݕ��v�Ƃ��������I�Ȍ`������Č����Ƃ͂����\�\�{���I�ɎЉ�W�ł����āA�g���m�h�̊W�ł͂Ȃ��A�]���āg���̓I�ȁh�W�ł͂Ȃ����ƁA�P�ɂ����������̂Ƃ��ĕ\�ۂ���A�g���ہh����Ă���ɂ����Ȃ����Ƃ��m�F����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B �@�u���l�ړ]�v�_�́A�u���l�v���A�]���āu���{�v�����A�����u���̓I�ȁv���̂Ƃ��āA�܂莩�R�I�A�����I�Ƃ������Ӗ��ł́u���̓I�ȁv���̂Ƃ��đz�肷��A�܂�g���_���q�I�ȁh�ӎ��A�u���W���A�I�ȋ��U�̈ӎ��ɁA����ɂƂ���Ă���B �@�u�ߋ��̘J���v�Ƃ��Č��ۂ��Ă�����̂́A���ۂɂ́A���Y��i�Y����J���ł����Ȃ����A����͕��Ƃɂ���Č����ɑ��݂���J���ł����āu�ߋ��̘J���v�Ƃ��������̂ł͂Ȃ��B����ȕ��ɗ�������̂́A���{��`�Љ�ɂ�����A���x�ɔ��B�����A�Љ�I�ȕ��Ƃ��\�\�܂茻��̎Љ�����������Ƃɂ���Ă̂ݐ��藧���A���W���Ă������Ƃ��\�\�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��l�X�̂��팾�ł��낤�B�ނ�̓u���W���A�̗�����A�������ʓI�u���W���A�̗���������I�ɁA����ɂ͈ӎ��ɂ����č������邱�Ƃ������Ăł��Ȃ��̂ł���B �@���ہA�u���W���A�̈ӎ��ɂ́A�܂�ʎ��{�̗��ꂩ��́A�u���{�v�́u�ߋ��̘J���v�Ƃ��Č��ۂ���̂ł���A�����ɂ����������̂Ƃ��Č���Ă���B���{�͂܂����{����A�܂萶�Y��i����o�����邪�A���{�ɂƂ��Ă݂͂ȁu�ߋ��̘J���v�̐��ʂł���A���́u�~�ρv���ꂽ���̂ł����Ȃ��B�����ď��i�̉��l�i���i�j���A���{���l�i��p���i�j�Ɨ����̍��v�Ƃ��ĕ\�ۂ����B �@�������ʎ��{���u���{�v�i�u�ߋ��̘J���v�j�Ƃ��Ĉӎ����A�F��������̂́A�Љ�S�̂́A�u���W���A�Љ�S�̂̊W�̒��ōl�@����Ȃ�A�u�ߋ��̘J���v�Ƃ��������̂ł͂Ȃ��A�����̘J���ɁA�Љ�I�ȑ��J���̓��́A���Y��i�Y����Љ�I�ȘJ���ɂ���ċK�肳��Ă���ɂ����Ȃ��B����́u�ߋ��̘J���v�Ɋւ�邱�Ƃł͂Ȃ��A�����̔N�X�̎Љ�I���J���Ƃ��̔z���ɂ��������ɂ����Ȃ��̂ł���A���������ϓ_���炷��Ȃ�A�u�ߋ��̘J���v�́A�܂莑�{���l�́u�ړ]�v�Ƃ��������Ƃ́A���ۂɂ͒��ȃu���W���A�I���z�ɂ����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ邵�A�Ȃ炴��Ȃ��B�ނ�͘J���҂̐��Y�����x���A�g�p���l���u���{�v�Ƃ��āA�����̎��I���L���Ƃ��čĂю�ɂ���̂ł���A���邱�Ƃ��ł���̂����A�u���W���A�̖ڂɂ́A���ꂪ���{���l�́u�ړ]�v�Ƃ��Ĉӎ������̂ł���B �@�ʑ��I�Ɂu�ߋ��̘J���v�ƌĂ�Ă������̂́A���ۂɂ́i�u���l�v�Ƃ��Ă݂�Ȃ�j���Y��i�Y����J���ł���A�u�������J���v�Ƃ����Ă������̂́A�����i�Y����J���ł����Ȃ��B�]���āA�g�p���l�Ƃ��Đ��Y��i�Y����J���ҁi�������T����̘J���ҁj���u���l�v�i�J���ʁj�Ƃ��Ă͏����i�ɑ��āA���̘J�����������̌��������̂ł���A���������i�Y����J���ҁi��U����̘J���ҁj�́A����̐��Y���������i�ł͂����Ă��A�u���l�v�Ƃ��Đ��Y��i���Đ��Y�������ɑ��Ă͌����������Ȃ��̂ł���B �@�]���̊ϔO�i�X�^�[������`�҂̊ϔO�j�ł́A���������i�Y����J���݂̂��u�������J���v�Ƃ��čl�����Ă���A���Y��i�Ɂg�Ώۉ��h�����J���́A������u�ߋ��̘J���v�Ƃ��āA�u�i�L�p�J���ɂ���āj�ړ]�v����Ă������{���l�ƌ��Ȃ���Ă����B�������A�Đ��Y�������̂��g�p���l�̑S�̂ł����āA�P�ɏ����i�����łȂ��Ƃ���Ȃ�A�u���l�v�ɂ����Ă����l�ł����āA�N�X�̑��J�����u�������J���v�Ƃ��ď����i�ɂ����Ɏx�o����Ă��āA���Y��i�ɂ͎x�o����Ȃ��Ƃ������ϔO�͓r�����Ȃ��̂ł���A���Ƃɂ���ĎЉ���藧���Ă���悤�ȁA�ǂ�ȁg�ߑ�I�h�Љ�̌����Ƃ����v���Ȃ��̂ł���B �@�������āA�u���l�K��ɂ�镪�z�v�̊T�O�ɓ��B���邽�߂ɂ́A�������܂��A�u�L�p�J���ɂ�鉿�l�ړ]�v�Ƃ��������U�̈ӎ�����������邱�Ƃ��K�v�ł���A�܂����������ӎ���������������ŁA���̖��̉����\�\�������A����������͗��_�I�ȉ����ɗ��܂�̂����\�\�͋ɂ߂ėe�Ղł���A�P�������Ȃ��̂Ƃ��Č����̂ł���B �@���ėт́u�L�p�J���ɂ��v���l�ړ]�Ƃ����ϔO�ɔ����������A���������̎��_�ɗ����Ĕ��Ȃ���A���͂ނ���u���{�̉��l�ړ]�v�Ƃ����ϔO���̂��̂ł���A���ꂪ�ǂ������Ӗ��Ɠ��e���Ƃ������Ƃł������B�u�L�p�I�J���v�ɂ��ړ]�Ƃ��������Ƃ��A�����ʎ��{�́g�_���h�Ƃ��ĉ��ɈӖ�������Ƃ��Ă��A����Ȍ��E�̒��ł݂̂̂��Ƃł����āA�Љ�I�ȑ����Y�ƍĐ��Y�Ƃ����ϓ_���炷��Ή��̈Ӗ����Ȃ����ƁA�Љ�I�ȑ����Y�̘_���ɂ����āA����Ȃ��̂������o���̂͂܂�Ńs���g�O��ł���A�L�Q�ł����Ȃ����Ƃ��A��X�͊m�F����K�v������B �@�������l�X�͌X�̎��{�Ɍ����܂܂̌��ۂɌ��f����āA�u�ߋ��̘J���v�̈ړ]�Ƃ����ϑz���痣��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B���������ϑz�́A��ɂ͋��߂������ɂ́A���̓�����܂�����Ă���łȂ��Ă͋���߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����A���R�����I�Łg���o�I�ȁh�ϔO����o�����邩��ł���A����Ƀu���W���A�Љ�ɂ����Ă��A�u���W���A�I���Y�̏o���_�ł́A���{���A�܂萶�Y��i���\�\�����i���܂��\�\�Љ�I�Ȑ��Y�������͍Đ��Y�̑O��Ƃ��āA�u���{�v�Ƃ��āA����邩��ł���A�܂����{�͎Љ�I�ȁu���l�v�Ƃ��āA�ێ�����A���́g�����h���p�����Ă����\�\���ȑ��B�������Ă����\�\����ł���B �@���r���\���ɂ��Ẳ�X�̗�ł��A�ނ͂܂���������̂ɂU���Ԃ��₵�A���ꂩ��R���Ԃ������ċ���߂����̂ł����āA�܂��ɔނ̋���߂�Ƃ����u�J���v�ɂ����ẮA��������Ƃ����J���͑O��Ƃ��āA�]���ċ���߂�Ƃ����J���Ɂu�ړ]�v���Č��ꂽ�̂ł���B �@���������r���\���̏ꍇ�ɂ����Ă����A�ނ́u�ړ]�v�ƌ������Ƃł͐����ł��Ȃ��s���ɏo�邩������Ȃ��B�Ⴆ�Γ�������̂ɂU���ԂłȂ��ĂP�W���Ԃ�v����Ȃ�A�ނ͂��̂��߂ɓ�������J�����R���Ԃɕ���������Ȃ��̂ł����āA�܂�����Ԃ�̐��Y�ɔ�₵�A���̌�łP���܂�܂�����߂�ɂ��₷�Ƃ������������Ȃ��ł��낤�A�Ƃ����̂́A���͖����߂�Ȃ��Ă͕����Ă��܂��ĐH�ׂ��Ȃ�����ł���A�ǂ����Ă��������߂�ɂR���Ԃ������Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł���B �@�v����ɁA���r���\���i�Ǘ������l�j�̏ꍇ�ɂ́A����g�c���т́h�J���������A�z�����Ȃ���邩������Ȃ����A�Љ�I�Ȑ��Y���s����Ȃ�A�g�����т́h�z�����A�܂�g���Ɓh���s����̂ł����āA�������邱�Ƃ��A���߂�����邱�Ƃ��g�������s�I�Ɂh�Ȃ����̂ł���A�Ȃ���邱�Ƃ��\�ł���B���̂��Ƃ��������꓾��Ȃ�A�Љ��`�ɂ����鉿�l�K��̗��_�̗����͗e�ՂɂȂ�ł��낤�B �@�u���l�ړ]�_�v�͌��Ǖs�����ȏz�_�ɋA���������A������Ȃ������B �@�����i�̉��l�K��ɂ����Ė��ƂȂ�̂́A���̏����i�Y����ɗv�������Y��i�́u���l�v�݂̂ł����āA���̐��Y��i�̐��Y�̂��߂ɂ���Ɂi�܂艄�X�Ƃ����̂ڂ��āj�K�v�Ƃ��ꂽ���Y��i�́u���l�v�͂����������W�ł���B �@�Ⴆ�A��p�Ԃ̐��Y�̂��߂ɂ́A�J���ΏۂƂ��Ă̓S�|�i���j�ƁA�J����i�Ƃ��Ă̋@�B�i�`�j���K�v�ł������Ƃ��悤�B�����Ă��̓S�|�̂��߂ɂ͓S�z���A�����ċ@�B�i�`�j�̐��Y�̂��߂ɂ́A�S�|�Ƌ@�B�i�a�j���K�v�ł������Ƃ��悤�B�����������ł͓S�z����S�|�Y����J����A�@�B�i�`�j�Y���邽�߂ɕK�v�ȓS�|��@�B�i�a�j���X�̂��Ƃ͍l������K�v�͈�Ȃ��̂ł���A�Ƃ����̂́A��p�ԂY���邽�߂ɕK�v�ȓS�|�Ƌ@�B�i�`�j�́A���łɍĐ��Y���ꂽ�J�����Ԃɂ���āu���l�K��v����A������Ă��邩��ł���B �@����͖{���I�ɁA�@�B��S�|��S�z�̉��l�K����A�u�ߋ��̘J���v�ɂ���āA�܂艿�l�̈ړ]�ɂ���čs�����Ƃ͕s�����ł���B���ۂ����������Ƃ͕s�\�ł���A�Ƃ����̂́A���ǂ͏z�_�ɂȂ邾���ł���A���l�����l�ɂ���āi�����ɂ́A���i�����i�ɂ���āj�K�肷��Ƃ������ƂɂȂ邵���Ȃ�����ł���B �@�Ⴆ�A�S�z�i����́u�������J���v����̂݉��l�K�肳���H�j����o�����āA���ɁA�u�ߋ��̘J���v�܂�u�ړ]���ꂽ�J���v�\�\�S�z�ɑΏۉ����ꂽ�J���\�\�Ɓu�������J���v�Ȃ���̂��v���X���A����ɏ����A���l�ɂ��ď�p�Ԃɂ܂Ŏ���A�������ď�p�Ԃ̉��l�K�肪�\�ɂȂ�悤�Ɍ�����A�������A�ŏ��̓S�z�̐��Y�\�\�̌@���X�\�\���܂��@�B���X��K�v�Ƃ���̂ł����āA�S�z�Ύ��́A���̉��l�K��̓A�v���I�����Ȃ킿���O��ł͂Ȃ��i������u�������J���v�����łł���킯�ł͂Ȃ��j�B �@���Y��i�̉��l���܂��u�Đ��Y�v�����Ƃ���̂ƁA���ꂪ�u�L�p�J���ɂ���Ĉړ]�����v�Ƃ��邱�Ƃ͓������Ƃł͂Ȃ��̂��A�Ƃ����������A�܂�u�ړ]�_�ҁv�̌��������������o����邩������Ȃ��B �@�܂�A�N�X�̎Љ�I�ȘJ���ɂ���āu���Y��i�̉��l���A�܂�w�ߋ��̘J���x���ړ]�����v�i�L�p�J���ɂ���āA�Ƃ������Ƃ͖��Ȃ��Ƃ��āj�ƋK�肷�邱�ƂƁA�u���Y��i�̉��l���܂��w�Đ��Y�����x�Ƃ��邱�Ƃ͌��Ǔ������Ƃł͂Ȃ��̂��v�A�Ƃ������g�^��h�ł���B �@�������Đ��Y�����̂͐��Y��i����ł͂Ȃ������i���܂����l�ł���A�������ė��҂��ĔN�X�́\�\�����Ԃ́\�\�Љ�I�ȑ����Y���`������̂ł���B���Y��i�͎g�p���l�Ƃ��Ă����łȂ��A�u���l�v�\�\���I�ɓ���̒��ۓI�l�ԘJ���\�\�Ƃ��Ă��N�X�ɐ��Y�������͍Đ��Y���ꂽ���̂ł���A�܂������������̂Ƃ��ĈȊO�ɂ͑��݂��Ă��Ȃ��̂�����A����Ȑ��E�Ɂu�ߋ��̘J���v�Ƃ��A����Ȃ��̂́u�ړ]�v�Ƃ����������̂���������͂����A������͂����Ȃ��̂ł���B�u�ߋ��̘J���v�Ȃ���̂���̂����ɂ��Ē��ۓI�l�ԘJ���ɊҌ��ł���̂��A����Ȃ��Ƃ͕s�\�ł��낤�B����͔N�X�̌����̘J���ɂ���āu�Ώۉ������v����ŁA���ۓI�l�ԘJ���ł��邵�A���蓾��̂ł���B �@�����N�X�̘J���ɂ���āA�u���l�v���܂��Đ��Y����A�K�肳���̂ł͂Ȃ��ƌ����Ȃ�A�g�p���l���܂��A�N�X�̍Đ��Y�ɂ���ĐV�����g�p���l�Ƃ��čĐ��Y����Ȃ����A���꓾�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ邵���Ȃ��B �@���������ۂɂ́A�N�X�̎g�p���l�͔N�X������Ƌ��ɁA�Đ��Y�����̂ł����āA����͐��Y��i�ɂ����Ă����ł͂Ȃ��A�����i�ɂ����Ă������I�ɓ��l�ł���i�l�͂����A���̌�҂̂��Ƃ�Y��邩�A�m�F���邱�Ƃ�ӂ�j�B �@���J�����Љ�I�ȕ��ƂƂ��čs���Ă���Ƃ��A�����Đ��Y��i�������i�����̐��Y���A�L�ĂȎЉ�I���Ƃ̒��ōs���Ă���Ƃ��A���Y��i�̉��l�́u�ߋ��̘J���v�̈ړ��ł���A�����i�̉��l�݂̂��u�������J���v�̌��ʂł���Ƃ������A�X�^�[������`���̍��ׂƂ�����́A�}���N�X��`�́u���l�v�̗��_�̍�����������A���������A���Ӗ��Ȃ��̂ɓ]��������ȊO�́A�ǂ�ȈӖ����g�����h�������Ă��Ȃ��B���Y��i�̉��l���ߋ��̘J���̈ړ]���Ƃ����Ȃ�A�����i���܂����l�ł��낤�A�Ƃ����̂́A�����i���܂����Y��i��p���Đ��Y����Ă���̂ł����āA���̈Ӗ��ł́u�ߋ��̘J���v�̈ړ]�ł����邩��ł���B�g�p���l�Ƃ��ď����i�ł͂Ȃ����Ƃ����Ă����_�ł���A�Ƃ����̂́A�����Ŗ��ɂȂ��Ă���͎̂g�p���l�ł͂Ȃ��A���l�i�������l�j������ł���B �@�u���l�ړ]�_�v�́A�u���W���A�́u��p���l�w���v�Ƃ����`�ŗ��_�I�A�g�w��I�h�Ȍ`��������ӎ��Ɩ��ڕs���ł���A�܂�u���l�v�i�ނ�ɂƂ��ẮA���̂��̂Ƃ��Ắu���i�v�ł��邪�j�Ƃ͎��{���l�i�s�ώ��{�Ɖώ��{�j�v���X�����ł���Ƃ����ӎ��ł���B�u���W���A�ɂƂ��ẮA���Y��i�Ƃ��āA�����Ă܂������i�Ƃ��čĐ��Y���ꂽ�x�́A�u���W���A�̏��L����u���{�v�Ƃ��āA���́u�ړ]�v�Ƃ��Ĉӎ������̂ł���A�]���Ă��́u���l�v���܂��u�ړ]�v�����̂ł��邪�A����̓u���W���A�̖ڂɉf�錻�����̂��̂ł���B �@���U�A�u���l�ړ]�_�v�̖����Ǝ��Ɠ����\�\���Y�I�J���͂R�O�O�O�łȂ��X�O�O�O �@���l�ړ]�_�҂ɂ��ƁA�N�X�̑��J���i�ҁj�͂X�O�O�O�łȂ��ĂR�O�O�O�������ł���A�Ƃ����̂́u�������J���v�͂����R�O�O�O�����ł����āA�c��̘J���̂U�O�O�O�́u�������J���v�ł͂Ȃ��A�u�ߋ��̘J���v�A���J��������ł���B �@�R�O�O�O�̘J�����A���ۓI�l�ԘJ���ɂ���ĂR�O�O�O�̉��l��n�����A�����A��̓I�L�p�J���͂X�O�O�O�̎g�p���l�Y����Ƌ��ɁA�U�O�O�O�́u�ߋ��̘J���v���A���Y��i�̉��l���A���{���l���u�ړ]����v�̂ł���B�X�O�O�O�̂����A�R�O�O�O�������u�������J���v�̐��ʂł���B�܂�U�O�O�O�̉��l�������Y��i�́A�g�p���l�Ƃ��Ă͍Đ��Y���ꂽ���A���l�Ƃ��čĐ��Y����Ȃ������̂ł���B �@�������X�O�O�O�̎g�p���l���R�O�O�O�̘J���ɂ���Đ��Y���ꂽ���̂ł���Ƃ����̂́A���ꖵ���ł����āA����ȗ������u�����v�ł��邩�ɍՂ�グ����Ȃ疳�Ӗ��ȃh�O�}�ɂȂ邵���Ȃ��̂͗]��ɖ��炩�Ȃ悤�Ɏv����B �@�R�O�O�O�̘J�������Y�������̂͌��Ǐ����i�ł���A�������ꂾ�����Ƃ������ƂɂȂ邪�A�����������ł͂X�O�O�O�̎g�p���l�Y�����ƌ�����̂ł���B���������i���Y�ɂ����ẮA�g�p���l�̐��Y�Ƃ͓����ɉ��l�̐��Y�ł��邵�A�����łȂ��Ă͘J�����l���͂킯�̕�����Ȃ����팾�ɂȂ邵���Ȃ��B���l�̐��Y�ł͂Ȃ��A�g�p���l�̐��Y�����蓾��ȂǂƂ����ϔO�͓r�����Ȃ����̂ł����āA�u���l�@���v�����ꂩ��ے肵�A�~�g���邱�ƂȂ����Ă͂Ƃ��Ă������Ƃ��Ē�o���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��悤�Ɏv����A�����X�^�[������`�҂����i���Y�}�̘A���j�͕��C�ł���ȃh�O�}��U��܂��̂ł���A�����U��܂��Ă���B �@�����Ă����u�ߋ��̘J���̈ړ]�v�i���l�ړ]�j�������Ȃ�A���Y��i�̉��l�����łȂ��A�����i�̉��l�̈ړ]������Ȃ��Ă͎����т��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ƃ����̂́A���{�ɂƂ��Ắu�ړ]�v����A�Đ��Y�����͕̂s�ώ��{�i���Y��i�̉��l�j�����łȂ��ώ��{�i�����i�̉��l�j�����l������ł���B���{�͔N�X�̍Đ��Y�̏o���_�ł͐��Y��i�������i���u���{�v�Ƃ��ď��L���A�O�Ă���̂ł����āA�����͔N�X�̏I���ɂ͂܂������̎茳�ɖ߂��Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B �@�����Ă��̏ꍇ�ɂ́A�u���l�ړ]�v�_�̌��E���A�������\�I����Ă��܂��A�Ƃ����̂́A���l�Ƃ��Ă̏����i�i�ώ��{�j�͒��ڂɁu�ړ]�v����̂ł͂Ȃ��A���ڂɂ͘J���҂̏����ւƓ]�����A����ɘJ���҂̘J���ɂ���Č����I�ɍĐ��Y�������̂Ƃ��Č��ۂ��邩��ł���A���̉��l�́u�ړ]�v���ꂽ���̂Ƃ��āA�u�J���v�ɂ���āi���ۓI�l�ԘJ���ɂ���Ă������j�}��ꂽ���̂Ƃ��Č���A�u�L�p�J���ɂ���Ĉړ]���ꂽ���́v�Ƃ��Č���Ȃ�����ł���B �@�������āu���l�ړ]�v�_�̃h�O�}�ɌŎ��������A�u���l�@���v�͂킯�̕�����Ȃ����_�I���ׂƕs�����ɍs�����������Ȃ��A�Љ��`�Љ�ɂ�����u���z�@���v�Ȃǂǂ����ɐ������ł��܂������ł͂Ȃ��A���{��`�Љ�̍��@���I�ȗ����������S���s�\�ɂȂ邾�낤�B�X�^�[������`�ҁi���Y�}�̘A���j�͓r���ɕ��邵���Ȃ��A���ǎ��H�I�A���_�I�Ɏ���j�]���A�������Ȃ��u���W���A�̌R��ɉ���̂ł���B �@�J���҂ɂƂ��Ď��{��`�̌����̔F���\�\�]���Ă܂��Љ��`�̗��_�̗����\�\�͒P���Ŗ����ł���B�X�O�O�O�̉��l�Ǝg�p���l�i�X�O�O�O�̉��l�����g�p���l�j���N�X�Đ��Y�����Ƃ���Ȃ�A����͔N�X�X�O�O�O�̘J�����x�o���ꂽ�̂ł����āA����ȊO�ł͂Ȃ��B�����i�Y���邽�߂ɂR�O�O�O�̘J�����x�o���ꂽ����A�N�X�́u�������J���v�́A�܂葍�J���͂R�O�O�O�ł����Ȃ��Ƃ������ϔO�́A�Љ�I�ȕ��Ƃ̎Љ�ɂ��āA�����������Ă��Ȃ����Ƃ�\�I���Ă��邾���ł���B�����R�O�O�O�̏����i�邽�߂ɁA�R�O�O�O�̏����i�̐��Y�ɕK�v�ȘJ�������łȂ��A�U�O�O�O�̐��Y��i�Y����J�����K�v���Ƃ����Ȃ�A����͎Љ�I�ȑ����Y�̂��߂ɁA�N�X�X�O�O�O�̘J�����u���z�v����邵�A����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł����āA����͗]��ɒP���Ȍ����ł���A�^���ł���ɂ����Ȃ��B �@�u���W���A�ɂƂ��ẮA���̑ΏۂƂȂ�̂́A�����i�Y����J���ł���A�Ƃ����̂́A���ڐ��Y�҂����悵�ĈӖ�������̂͏����i�ł����Ȃ�����ł���B�ǂ�ȊK���Љ�ɂ����Ă��A�x�z�K���͏����i�����D���A��悷�邱�Ƃɂ���ĕx��ł����̂ł���B������Y��i�����D���邱�Ƃɂ���ĕx�ނƂ����Ȃ��Ƃ͌���Ȃ����A����́u������x����ł̂��Ɓv�\�\�Ⴆ�A�u���n�I�Ȓ~�ρv���X�\�\�ł����āA�p���I�ɍs�����Ƃ͕s�\�ł������A�Ƃ����̂́A�����Y�҂����͂������Y��i�����D�����u���Y�̖��v�ɂȂ�A�J���͂��Đ����邵���Ȃ��A�u���W���A�������Ăѐ��Y��i�����D���悤�Ƃ��Ă��ł��Ȃ�����ł���B�����炱���A�u���W���A�ɂƂ��ẮA�����i�Y����J���������u�������J���v�\�\���\�ȑΏہ\�\�Ƃ��Č��ۂ���̂����A�����w�b�|�R���_�Ƃ����́A����ȃu���W���A�ӎ��f���đ������Ă�̂ł���B�u���W���A�Љ�ł́A�������ꕔ�̘J���҂͐��Y��i�����Y���ď����i�͐��Y���Ȃ��̂����A�u���W���A�����́u���J���v�ɂ���āA���������J���҂����\�\�J���҂̑S�̂��\�\��悷��̂ł���A���邱�Ƃ��ł���̂ł���B �@�N�X�̑����Y�͏����i�Y����R�O�O�O�̘J���̌��ʂł͂Ȃ��A�X�O�O�O�̘J���̌��ʂł��邱�Ƃ��m�F���邱�Ƃ͋ɂ߂ďd�v�ł���B����́A�J���҂�����̉���Ɍ������đO�i���Ă������߂Ɍ������Ƃ̂ł��Ȃ����o�̈�ł����āA�X�O�O�O�̘J�����R�O�O�O���Ȃǂƌ����͂₷�A���̃h�O�}�ɁA���팾�Ɂ\�\�܂�u���l�ړ]�v�_�ȂǂɁ\�\�Ƃ���Ă���Ȃ�A�Љ��`��������铬�������܂��A��̂��邱�Ƃقǂɖ��炩�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł��낤�B�Љ�p�����A�܂��J���҂��������A�����čs�����߂ɂ́A�R�O�O�O�̏����i�Y����J�������łȂ��A�U�O�O�O�̐��Y��i�Y����J�����S�����l�ɕK�v�ł����āA�����������Ƃ͂�葽���̏����i����菭�Ȃ��J���ŁA���L���Ɋl�����邽�߂̂��̂ł��邱�ƁA�����i�Y����J�����A���Y��i�Y����J�����\�\����Ƃ�����Љ�I�J�����\�\�A���I�ɓ���ŁA�����ʕ����̘J���ł��邱�Ƃ��A�����Ĕ���J���ł��邱�Ƃ��\�\����̂ɁA�S�Ă̘J������l�X�̕����Ɩ����ʂ��A�]���Ă܂��e�l�̐l�i�Ǝ��R���\�\�m�F����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B �@���V�A�u���Y��i�̉��l�K��v�̖�� �@��p�Ԃ̉��l�K��́A�J���ΏۂƂ��Ă̓S�|�i���j�ƁA�J����i�Ƃ��Ă̋@�B�i�`�j�́u���l�K��v�i�J�����ԁj�ƁA���ڂɏ�p�ԂY����J�����Ԃ̘a�Ƃ��Ă݂̂ɂ���ĂȂ����Ƃ������Ƃ́A�S�z�Y����J����A�@�B�i�`�j�Y���邽�߂̓S�z��@�B�i�a�j���X�Y����J�����ǂ��ł������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�����͎Љ�I�ȑ����Y�̒��ɁA�܂�Љ�I�ɕK�v�ȑ��J���̒��Ɋ܂܂�Ă��邪�A���������i�̐��Y�̂��߂ɒ��ڂɎx�o����Ȃ��̂ł���A�]���ď����i�̉��l�K��Ƃ͖��W�ł���Ƃ������Ƃɂ����Ȃ��B �@�������A���Y��i���܂����l�K�����邵�A��邱�Ƃ��ł���Ƃ����Ȃ�A����͐������B�������Љ��`�Ő��Y��i�̉��l�K��Ƃ��������͉̂��ɉ\���Ƃ��Ă��A���̈Ӗ��������Ȃ��̂ł���B�Ƃ����̂́A���Y��i�͒��ڂɎg�p���l�Ƃ��āA���̗ʂƂ��ĘJ���i�J���ҁj�ƊW���邩��ł���A�܂����Y��i�̌X�l�ւ̕��z�Ƃ��������Ƃ͑S�����ɂȂ�Ȃ�����ł���B �@���W�A���ނ́u�L�@�I�\���v�̊T�O�ƃ}���N�X�̕\�� �@�}���N�X���܂��A���Y��i�Y����J���ƁA�����i�Y����J���̔�d�����d�v�ȈӋ`���悭�������Ă����̂ł����āA�ނ͎��{��`�ɂ�����A���̓���Ȍ��ی`�Ԃ��A���{�̗L�@�I�\���Ƃ��āA���Ȃ킿�s�ώ��{�Ɖώ��{�̔䗦�Ƃ��ĕ\���������A�����������ł́A���Y��i�Y����J���Ə����i�Y����J���̔䗦���A���R�I�ȗL�@�I�\���Ƃ����T�O�Ō��y���Ă���B�}���N�X�̒P���Đ��Y�̕\���ł́A�U�O�O�O�R�O�O�O�܂�Q�P�ł���i�������s�ώ��{�Ɖώ��{�̔䗦�ł́A�U�O�O�O�P�T�O�O�łS�P�ł��邪�j�B �@�����Ă���Ƀ}���N�X�͌X�̎��{�ƓI���i�̗L�@�I�\���̈Ⴂ�Ɋ�Â��A�u���l�̐��Y���i�ւ̓]���v�ɂ��Ă����A���͂��s���Ă��邪�A����͋q�ϓI�ɁA�X�̐��Y���̗L�@�I�\�������ϓI�ȗL�@�I�\���Ƃ́\�\���R�I�Ȃ��̂Ƃ��Ă��\�\�قȂ��Ă���A����Ă��邱�Ƃ��琶���Ă���A���{��`�I���ۂł���B �@���X�A���Y�͂̌���������́u���l�v���v�Ɓu���l�K��v��� �@�J�����Y���̌���܂�u���l�v���v�i���Y���Y����J�����Ԃ̒Z�k�j�̖����A�܂��e�Ղɉ������邱�Ƃ��ł���i�u���l�ړ]�v�_�ł́A�����č����I�ɉ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂����j�B �@��X�̗�ɂ����āA�����i�̏ꍇ������Ę_���邱�Ƃɂ��悤�B���R�I�ȗL�@�I�\�����Q�P�Ȃ�A���Y��i�̐��Y�͂��Q�{�ɂȂ����Ȃ�i�܂�K�v�J�����Ԃ������ɂȂ����Ȃ�j�A�����i�̐��Y���̏㏸�́A����܂ł̘J�����Ԃ��R���̂Q�Ɍ�������Ƃ����`�Ō���邪�A�����i�̐��Y�͂����ڂɂQ�{�ɂȂ����Ȃ�i�܂�K�v�ȘJ�����Ԃ����������Ȃ�j�A���ڂɏ����i�͔����̘J�����ԂŐ��Y�����Ƃ����`�Ō��ۂ���B������Y��i�̏ꍇ�����l�ł���B���������i����̐��Y�͂��Q�{�ɂȂ�A�����ł̘J�����Ԃ������ɂȂ�����A���Y��i����̕K�v�J���͂U���̂P�����k�����āA�U���̂T�ɂȂ邾�낤�B �@���P�O�A��X�̐V�����T�O�̈Ӌ` �@�������ĉ�X�͎��{��`�ɂ�����u���l�K��v�Ɋ�Â�������{�I�ɉ������A���Y�}�́g�u���]�h�����i�u���W���A�I�]���ɑ������j�ڂ����A���̖{����\�I�����̂����\�\�ނ�͎Љ��`�ɂ�����u���z�v�����{��`�Ɠ����`�ŁA�܂�u�s��o�ρv�̉^���ɂ���ĂȂ������Ȃ��Ƒ������Ă��\�\�A�������Љ��`������������������ɂ́A�J���ҊK���̓u���W���A�I���@��p�����āA����̎x�z�ɂӂ��킵���������������A�e�Ղɂ��̖����������čs�����낤���A�s�����Ƃ��ł��邾�낤�B �@��X�́A���{�́u���l�K��v�Ƃ��A���{���l�i�u�ߋ��̘J���v�j�̈ړ]�Ƃ����������U�T�O�ƌ���I�Ɍ��ʂ��A���̃u���W���A�I�{���������炩�ɂ��邱�Ƃɂ���āA�͂��߂āA�Љ��`�Љ�ɂ����镪�z�̖������������邱�Ƃ��ł������A���̒��S���Ȃ��T�O�Ƃ́A�X�̏����i�������Ɂu���l�K��v���꓾��̂��A�܂�J�����Ԃŕ\�����꓾�邩�Ƃ������ł������B��X�́A�N�X�́\�\���̊��Ԃ́\�\�g�p���l���������l���A�N�X�̘J���҂̑��J���ɂ���Ă̂ݐ��Y�������͍Đ��Y����A�܂�����\�\�l�I�ł���A���Y�I�ł���\�\���꓾��̂ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��A����ɔN�X�̂ǂ�Ȏg�p���l�Ɏx�o����A�g�Ώۉ��h�����J�����A�Љ�I�Ȍ`�Ŏx�o���ꂽ���J���̈�A�ꕔ�Ƃ��āA���ꂼ��ʓI�ɂ͈قȂ�Ƃ��Ă��A���I�Ɉ�l�ł��邱�Ƃ��m�F���A�܂��ɂ��̂��Ƃɂ���āA�����i�̉��l�K��̊T�O�ɓ��B�����̂ł���A�������̂ł���B �@�������ĉ�X�����N�̘J���҃Z�~�i�[�Ŗ��炩�ɂ����T�O���܂��A�����т����A���Ăō����I�ȉƂ��Ċm�肳�꓾���̂ł���A�Ƃ����̂́A�����i�Y����ꍇ�ɕK�v�Ȑ��Y��i�̘J�����Ԃ��܂��A�����i�Y����J���Ɠ����ł���\�\�ǂ�Ȏ�ނ̗L�p�I�J���Ƃ��ւ��Ȃ��A���邢�͂����ɋ��ʂ́A���ۓI�Ȑl�ԘJ���Ƃ��Ď��I�ɓ����ł���A��ʂ��꓾�Ȃ��\�\���炱���A�g�|��h���A�g�]���h���邱�Ƃ��\�ɂȂ邩��ł���B�����i�Y���邽�߂̐��Y��i�̉��l�K����u�ߋ��̘J���v�₻�́u�ړ]�v���X�̊ϔO������ɂ��čs�����Ƃ͕s�\�������A�Ƃ����̂́A���������ꍇ�A���Ƃɂ���Đ��ݏo�����Љ�I�Ȑ��Y���Y����J���̎��I�ȓ��ꐫ���ۏ��꓾���A�]���Ă܂��ʓI�Ȕ�r���ł��Ȃ�����ł���B�X�̏����i�́u���l�K��v�i�J�����ԁA�J���ʁj���K�肷�邽�߂ɂ́A���̗ʓI�ȈႢ���m�肳��邽�߂ɂ́A�X�̏����i�́u���l�K��v�̏������̘J���̎��I�ȓ��ꐫ���O��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��͖̂��炩�ł��낤�B �@��X�́A���Y�}��X�^�[������`�҂��A�Љ��`�ł̕��z���A���{��`�Ɠ��������ł�邵���Ȃ��A�s��o�ς́g�@���h�i�u�_�̌��������v�j�ɔC���邵���Ȃ��A�Ȃǂƃu���W���A�Ǝ��{��`�o�ςւ̑S�ʓI�q��Ƌ��]�ɑ����Ă���Ƃ��A�ނ�̂��팾��O��I�ɖ��炩�ɂ��A�Љ��`�I���z�̊�{�I�ȊT�O�Ɠ��e�𖾂炩�ɂ��Ă����Ӌ`�͌���I�ɑ傫���A�d�v�ł����āA�����狭�����Ă��������邱�Ƃ͂Ȃ��B �@�������A��X�̗��_�͎Љ��`�ɂ����镪�z�̗��_�ł����āA���̐��i��A�����H�I�ɂǂ������Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�������J���ҊK�������{�̎x�z�̈�|�ƁA���̌�̎Љ�ɂ��Ĉ�w���ĂȊϔO�������Ƃ́A���̓�����E�C�Â��A���łŁA�����I�Ȃ��̂ɂ��邾�낤���A�܂��J���ҊK����������x�z�K���ɍ��߂��Ƃ��ɂ́A���̎x�z��L���Ɏg���ĉ����Ȃ����炢�����̓W�]�Ǝw�j�Ƃ�^���A�ނ炪�m�M�ƗE�C�������đO�i���邱�Ƃ��\�ɂ��邾�낤�B �@�k�Ȃ��A���̏��_�́A���N�̘J���҃Z�~�i�[�ɂ�����`���E�^�[�̕Ƌc�_�̑S�Ă���W�����A�w�v�����e�E�X�x�T�T�E�T�U�����������킹�ēǂ܂�A���������A��X�́u�Љ��`�Љ�ɂ����鉿�l�K��v�Ɋւ���T�O�ɂ��Ă̋c�_�⌋�_�̎�����I�ȏd�v���ƈӋ`�����������[���������A�m�F���Ă���������Ǝv���l |
|||||||||||||||||||