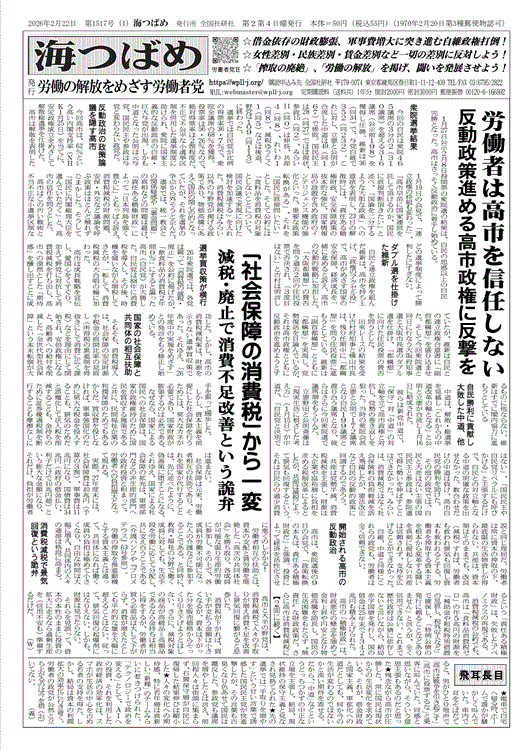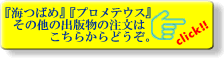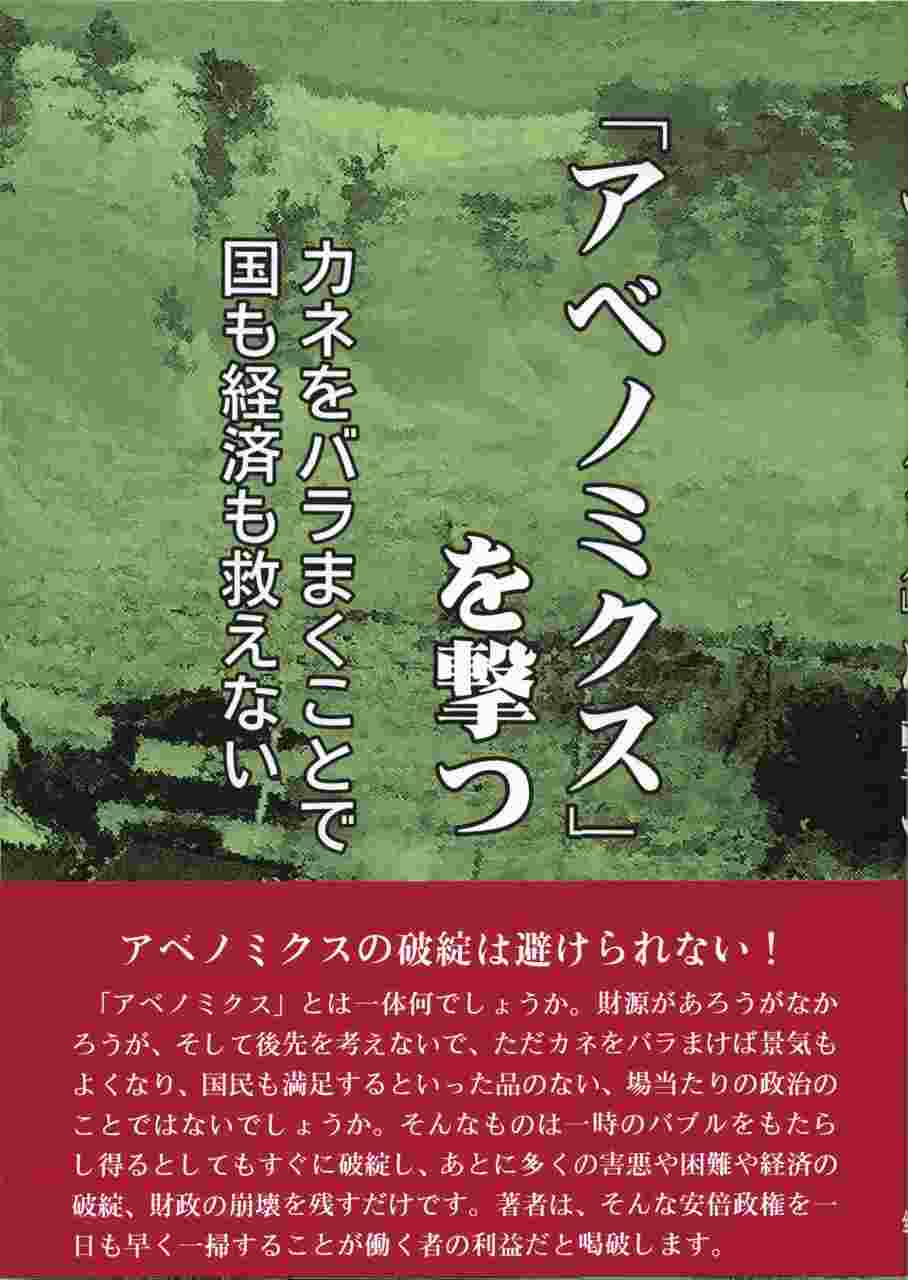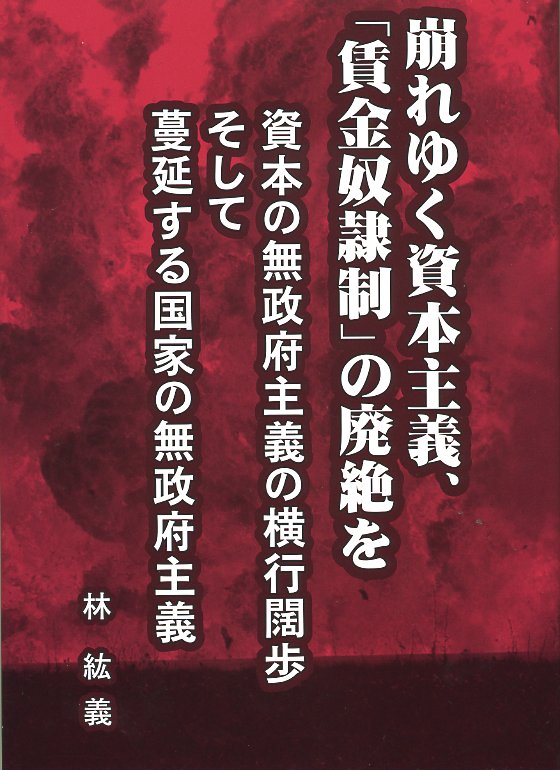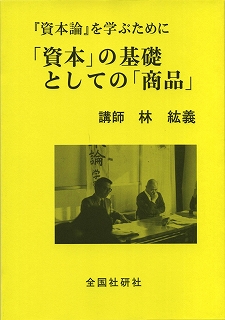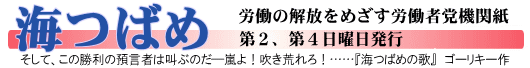 |
||||||||||||
| 購読申し込みはこちらから | ||||||||||||
|
●1517号 2026年2月22日 【一面トップ】労働者は高市を信任しない ――反動政策進める高市政権に反撃を 【一面サブ】 「社会保障の消費税」から一変 ――減税・廃止で消費不足改善という詭弁 【コラム】 飛耳長目 【二面トップ】 「中道」の壊滅的敗北 ――労働者の階級的政党の闘いが必要 【二面サブ】 トランプ「石炭はクリーンで美しい」 ――温室効果ガスの根拠を〝反知性主義〟で否定 ※『海つばめ』PDF版見本 【1面トップ】労働者は高市を信任しない反動政策進める高市政権に反撃を1月27日公示2月8日投開票の衆院選の結果は、自民の思惑以上の自民完勝となった。高市はさっそく反動政治に着手し始めている。 ◇衆院選挙結果今回の自民は衆院465議席の3分の2(310議席)を超える316議席(公示前198)を獲得し圧勝。維新は36(同34)で、与党自維で352(同232)。これに対し、立憲と公明が合流した中道は49(同167)で惨敗。国民民主は28(同27)でほぼ現状、参政15(同2)、みらい11(同0)は伸長、共産4(同8)、れいわ1(同8)、減税ゆうこく1(同5)などは後退。野党は109(同113)に終わった。 選挙では自民党が比例の得票率36・7%で、衆院全議席の68%を獲得。投票率は56・26%なので、絶対得票率は2割程度だ。不正で不公平な小選挙区制を併用した選挙制度に助けられ、衆院に国家主義的な反動政治の自維・巨大与党が出現。しかも中道となった公明は元与党、国民民主や参政は与党と変わらない政党だ。 ◇反動政治の政策論議を隠す高市今回高市は、62%という高い内閣支持率(NHK1月25日)を当てに、安定政権成立をめざして解散総選挙を仕掛けた。 高市は解散を表明した1月19日の会見で、「連立政権の枠組も変わった」、「高市早苗に国家運営を託して頂けるのか、国民に直接判断頂きたい」と述べ、「国論を二分するような大胆な政策」への意欲を表明し、23日の解散時には、「責任ある積極財政、安全保障政策の抜本的な強化、国家情報局の設置を含め政府のインテリジェンス機能の強化といった、重要な政策転換がある」、それを「国民に直接問いたい」とした。そして公約には「食料品を消費税の対象としないことについて、国民会議で実現に向けた検討を加速する」を入れた。消費税減税はみらい以外の与野党が掲げる政策であり、物価高騰にあえぐ国民の関心の的となっていたが、それを選挙の争点から外そうと企んだ。 選挙では、統一教会との関係疑惑や「裏金問題」の真相などの問題は避け、「責任ある積極財政」によって「日本列島を強く豊かに」ともっぱら訴え、消費税減税の財源問題、安保・外交など議論を呼ぶ政策はほとんど触れずごまかした。そうして「国民に内閣総理大臣を選んでいただく」と、高市の信任を問うとした。 高市はこの汚い戦術と不当不正な小選挙区制などの選挙制度によって勝利したにすぎない。 ◇ダブル選を仕掛けた維新自民と連立政権を組んだ維新は、高市を持ち上げ、「政権のアクセル役」で、高市がめざす国家の安全保障、経済成長を一緒に進めると訴え、高市の反動的戦略に加担した。 「大阪都構想」の賛否を問う過去2回の住民投票で否決され、「3度目はない」と吉村は明言していたが、維新は自民との連立政権合意書に「副首都構想」を盛り込ませた。そして今回衆院選と同日に行なう大阪府知事選と大阪市長選のダブル選を仕掛け、「都構想」に向けた住民投票の賛否を問うとした。 出来レースの結果を受け吉村府知事と横山市長は、残り任期中に「都構想」を問う住民投票に進もうとしている。維新は「副首都構想」とともに「都構想」を実現し、党勢復活を目論んでいるが、それは高市政権とともに反動政治を進めようとするものに他ならない。維新はすでに閣内協力に進もうとしている ◇自民勝利に貢献し大敗した中道、他中道は、解散・総選挙を見越し「これからの中道改革の軸となる」と公明と立憲が合流し1月16日に結成された。 彼らは新党中道で、「保守」対「中道」の対立軸を立て高市政権と対抗し、党勢の巻き返しを狙った。当時の衆院会派立憲と公明で172議席となり自民199議席と渡り合う議席となり、彼らはさらに今回衆院選で議席増をもくらんだ。 立憲野田と公明斎藤は「現実生活に根ざした考え方」(1月15日)が中道だ、「自民党と決別ではない」、「国民民主や自民党リベラルにも呼びかける」と主張するだけで、自民との対立軸となる中道の明確な政策を出せなかった。数合わせだけの中道は負け、高市自民党の勝利を助けた。 その他の政党では、自民と大差はない主張の国民民主と参政は、参院選で得た勢いを伸ばすことはできなかった。みらいは、消費減税ではなく社会保険料の負担軽減を訴え飛躍したが、憲法改正など自民の反動的政策に同調するのであろう。 共産は党勢半減。消費税減税を主張し、財源は大企業や富裕層に負担を求める税制改革によるとしたが、共産は減税によって景気も回復するという。それは自民らの過少消費説と同じ理屈だ。労働者は常に資本の搾取の下、最底限の生活物資しか得られない。共産は、資本制はそのままでも、改良(減税)すれば、労働者も救われ景気も回復し資本も救われるとする。労働者を搾取する資本主義を根本から変革する闘いを真剣に提起しない共産は信頼されず、支持を広げることができなかった。 自維、中道と同様にこれらの政党も、労働者は全く信頼できない。 ◇開始される高市の反動政治高市は、衆院選後の9日の会見で、「政策転換の本丸は、責任ある積極財政だ」と強調。投資によって経済を活性化させるという「責任ある積極財政」は、失敗したアベノミクスの再現である。 消費税減税の公約でも、高市は「食料品消費税ゼロ」の年5兆円の財源を「補助金や租税特別措置の見直し、税外収入など」で確保し、「特例公債の発行に頼ることなどありません」と言うが、全く信用できない。これまで歴代政府は公債に依存しないと言いながら、結局赤字国債を発行し、国の借金は25年末で1342兆円も積み上げられた。 高市の「積極財政」は、財政悪化の懸念を強めて金利上昇や円安となり物価高騰を助長し、国民の生活困難をもたらす〝無責任〟な財政政策だ。さらに高市は消費税減税については「国民会議において検討する」として、自らの責任を回避。 そして高市は「政府のインテリジェンス機能強化」を取り組む。その政策の司令塔となる「国家情報局」創設の法律を、特別国会で成立させ、スパイ防止法の議論を始める(朝日17日)。スパイ防止法は、外国によるスパイ活動を対象とするにとどまらず、思想の自由を制限し、国民生活監視、言論統制で、労働者の政治活動を抑圧する現代版「治安維持法」である。 また高市は、安保3文書改訂も進め、トランプの軍事費増額要求を利用し、日本の軍事費増大を図り帝国主義化を進める。 高市はこれに関連して、「殺傷」能力ある武器輸出の拡大、軍事産業の国有化検討、外国人政策の厳格化、日本国国章損壊罪の創設、男系天皇維持のための皇室典範改正、夫婦別姓を阻む旧姓使用の法制化、そして戦力不保持を定めた9条2項の削除の憲法改正など、これまでの自民党反動派が企んできた国家主義的反動政治に着手しつつある。 高市反動政治の背景には、資本主義経済の行き詰まりがある。資本は労働者を抑圧し犠牲を強い、生き延びようとしている。 労働者は、このような抑圧政治に断固反撃するとともに、資本主義そのものを変革する闘いを発展させていこう。 (佐) 【1面サブ】「社会保障の消費税」から一変減税・廃止で消費不足改善という詭弁◇選挙買収策が横行26年衆院選では、各党は競って「消費税の減税・廃止」を公約に掲げたが、「飲食料品の消費税2年間0%」にすると謳った高市(自民党)が大勝した。自民党は88年に消費税を導入し、その後、時機を窺いながら増税してきたが、一転して、消費税減税の大合唱の輪に加わった。 高市は成長戦略を宣伝し、愛国心をくすぐり、加えて野党に対抗して消費税減税を打ち出し、高市への漠然とした「期待感」を醸し出すことに成功した。しかし、高市の消費税減税案は、財源を示さない選挙買収策であった。それゆえ、「26年度中の実施をめざす」との発言をもう修正し始めている。 ◇国家の社会保障と共同体の相互扶助そもそも、消費税導入は、社会保障の安定財源や税金の直間比率の見直し(所得税の累進制を骨抜きにして消費に広く課税)などを理由にして開始され、安倍政権になると、高齢者への給付を削減した「全世代型社会保障」という本末転倒が大手を振って闊歩した。 しかし、資本主義を前提にした社会保障を行うためには、莫大なカネが必要であり、国家財政が膨張するのは必然である。 なぜなら、国家による国民への社会保障は、国家が政権維持のために国民を買収する施策であると共に、民間福祉企業の利潤保障のためでもあるからだ。買収費を投じなければ、軍事強国化のために莫大な税金を投入することも、景気のためだと誤魔化して法人税を削減することも、金持ちのために証券優遇税制を断行することも摩擦なしには進まない。 社会保障は元来、労働者相互の扶助であり、それを国家が代行することは、先に述べたように、偽善策に堕すことになる。それゆえ、国家による社会保障の拡充は、軍需部門などの非生産的部門への政府投資と相まって、労働者への負担増大となって現れる。 実際、27年度末には、社会保障費は40兆円(予算の3割)、軍事費は11兆円になり、国債費は34兆円(政府の借金払い、利子だけで10兆円超)という膨大な金額になり、それだけ、負担が労働者に重くのしかかる! 労働者相互の扶助とは、資本の支配と賃労働を廃絶した「高次の共同体社会」を勝ち取り、各成員が可能な限り生産的労働に参加し、その上で、各成員が労働不可能になった人の介護などに参加することである。と同時に、教育・福祉の分野で働く成員に対しても、生活手段を労働に応じて分配し、共に支え合うことである(介護パンフや『プロメテウス』63号参照)。 労働の搾取を推進動機とする資本主義とは違って、共同体になれば働く成員の負担は極めて小さくなり、自由な時間は大幅に増え、共同体内の人々の連帯は格段に高まる。 ◇消費税減税で景気回復という詭弁高市と大半の野党は、消費税減税で人々の手取りが増え消費不足を改善し景気回復に繋がると息巻いた。 消費税が下がれば、買い手が支払う金額は小さくなるが、資本は下がった分を販売価格からそっくり引き下げようとはしない。さらに、減税対象の商品が高級品=高額品であるなら金持ちは相当に得をするが、労働者が買う必需品は大して下がらず、消費が増えたとしても平均的な量を大幅に超えることはない。従って、景気回復の起爆剤にはなりえない。しかも、財源は見当たらない。 それらを見誤って、資本の本性のままに投資の拡大に走るなら過剰生産を(信用不安も)準備するだけだ。 (W) 【飛耳長目】 ★電車で自宅へ帰る時、ホームで誰かが騒がしく叫んでいた。車内で耳をそばだてると、男がひとり地声で「高市は戦争を引き起こす」「高市に投票するな」と乗客に叫んでいた。同感と思いながら、そういう意思主張もあるのだと思った★残念ながら高市が圧勝した。常に国民は現状からの生活変化を求めている。それが、借金財政と国家主義、軍拡化への道だとしても、何か今の生活が変わるのではないかと淡い期待を寄せる。だから、「中道」などというどっちつかずの中正な立場を主張し、結局、現状維持の保守主義と見なされ見捨てられた★先の選挙では「手取りを増やす」という甘い言葉で誘惑した国民民主党が快進撃したが、その言葉も古臭くなり色あせて国民は離反した。参政党も議席を増やしたとは言え、前回程人々は街頭に集まらず、右翼保守層が自民に復帰した結果伸びは縮小した★人々の変化への期待感、特に若年層は真新しい「新種」のチームみらいに惹きつけられた。「テクノロジーで政治を変える」として、AIへの投資、それを利用した政治経済の効率化は、スマホが生活の中心を占める若者の支持を得た。しかし、結局は資本の利潤拡大の効率化に行き着く。労働者の政党が公然と立ち上がるのは今を措(お)いてない。 (義) 【2面トップ】「中道」の壊滅的敗北労働者の階級的政党の闘いが必要衆院選で自民は単独で過半数を大きく上回る316議席を獲得し、戦後最多記録を更新する圧倒的勝利を収めた。これに対して野党第一党の立憲民主と公明が合同した新党「中道改革連合」(以下、「中道」)は、議席を100以上も減らし惨敗を喫した。惨敗の原因はどこにあるのか、今回の選挙の教訓は何かについて真剣に追求しなくてはならない。 ◇「中道」の惨敗の状況まず、惨敗の具体的状況について確認しておこう。今回の選挙の立候補者数は小選挙区202人、比例代表234人(重複立候者200)計236人であった。しかし、当選したのは選挙区わずか49議席、立憲民主出身議員は144議席から、一挙に21議席に減少した。しかも、このうち6議席は自民党の比例代表での名簿不足により得たもの、さらに1議席はみらいからの同様な理由で得たもので、実質的には42議席にすぎない。小選挙区で比例復活なしで議席を得たのは、党代表の野田ら僅か7名でしかなかった。 これまで立憲民主の幹部として活動してきた共同幹事長の安住、外相経験者の岡田、代表経験者枝野、代表経験者海江田、共同選対委員長馬淵、政界の「重鎮」と呼ばれた小沢らは軒並み落選。 一方、小選挙区に立候補はなく、比例代表のみの立候補となった公明出身議員は、公示前の24から4議席増やして28議席を獲得。「中道」が得た議席数は比例と併せて計49議席にとどまった。 「中道」が壊滅的ともいえる敗北となった理由については、高市による「奇襲」ともいえる通常国会冒頭での解散で選挙に対応する準備ができなかったとか、公示日から投票日まで僅か12日の選挙運動期間で有権者に訴える時間がなかったとか、自民は多くカネをSNS・動画配信に使って大量のスポット動画を流したのに対して、大きな遅れをとったなどのことが言われている。確かにこれらのことは高市自民にとって有利になったことは確かである。また、非民主的な小選挙区制が票以上に自民に多くの議席を与えていることもある。 ◇「中道」の敗北の原因しかし、以上のことは「中道」が壊滅的ともいえる敗北を喫したことの基本的な理由を説明するものではない。 敗北の最大の理由は、「第二自民」とも言われ、26年間も自民と連立を組んできた公明が、自民との連立を離れたのを機に、一緒になって「中道」という新党を立ち上げ、選挙に臨んだことである。 しかも新党の名称とした「中道」をはじめ、党の綱領、選挙公約も公明の主張そのものであった。公明は「個人の幸福と社会の繁栄が一致する、大衆福祉の実現」「人間性の尊重を基調とした民主主義をつくり、大衆とともに前進する大衆政党の建設」をめざす党を看板にしてきた。また「生活者の暮らしと平和を守る」党だとも言ってきた。だがその実態は、1999年自民小渕第二次政権で連立し、国会で過半数をとって以来それを機に2025年10月高市総裁の成立で離脱するまで四半世紀にわたり、自民政治に協力してきた。 この間、公明は、小泉純一郎政権の「労働力の流動化」の名の下で、資本の都合で解雇自由な無権利・低賃金の非正規雇用制度拡大の容認、そしてさらに安倍政権の下では、国債を乱発し日本経済の長期停滞を助長してきた「アベノミクス」を認めてきた。 また安倍政権は、歴代政府が継承してきた集団自衛権行使を違憲とする憲法9条の解釈を閣議決定で変更。日本への攻撃時に限定していた自衛隊の武力行使を米国など日本と密接な関係にある他国が攻撃された場合に拡大した。その後の岸田政権の下での安保関連3文書の決定など一連の米国との共同軍事行動、日本の軍事力の拡大強化に道を開くことになったが、公明は事実上、これらを追認してきたのである。 彼らが自民と連立政権を組んできたのは、それに党派的な利益を見出してきたからである。創価学会という現世利益を唱える宗教集団を土台とする公明にとって、自民と組むことは大きな利益だった。彼らは国土交通相という大臣の椅子をあてがわれて、長い間利権をむさぼってきたのである。 そして公明が連立から離れたのは、そのまま連立を続けても展望が見出せなくなったからだ。公明は最高であった2005年の898万票から2024年には596万票へと34%も減少させた。このままではじり貧になるとして公明は自民との連立から離れ、立憲民主との合同に走った。 一方、立憲民主にとって公明と合同すれば、一選挙区当たり9000~2・5万票と言われる公明の組織票を手に入れることができる、自民をおい詰める可能性が広がると期待した。こうした両党の幹部の思惑のもとでつくられた新党は、名称の「中道」をはじめ、綱領、選挙公約も公明の主張そのものであった。 綱領は現状について、近年「右派、左派を問わず急進的な言動が目立ち始め、多様性を尊重し、共に生きる社会を築こうとする努力が今脅かされている。この現実を前に、政治が果たすべき責任は重い」として、「対立を煽り、分断を深める政治ではなく、対立点を見極め、合意形成を積み重ね、生活者ファースト政治を着実に前へ推し進める中道の政治が求められている」と述べ、その理念は「生活・生存を最大限に尊重する人間主義」だと謳っている。 選挙公約では、「中道」は物価騰貴に対して消費税は「食料品ゼロ」を掲げ、その財源として、年金基金など「政府ファンド」の一括管理・運用に基づく運用利益を充てるという経済官僚が頭の中ででっち上げたような提案を掲げたが、ほとんど注目されずに終わった。 また、平和外交にしても、沖縄普天間基地移転に伴う辺野古基地建設についても、「中道」はこれまでの公明と同様に賛成の態度をとり、自民を助けた。 公明が四半世紀も自民と連立してきたことについて、公明と立憲民主両党は、それまでの思想、運動の総括もなしに、「数は力」とばかりに無原則に統合したのであり、それは員数合わせのための〝野合〟であった。公明は自民との連立を解消したが、これまでの自民との連立について何一つ根本的な総括はしていない。綱領にせよ選挙政策にせよ、公明に全面的に依存した「中道」は選挙に負けるべくして負けたのである。 ◇資本の支配に反対する労働者の階級政党の建設を選挙惨敗の責任を取って、野田、斉藤の両代表が辞任、「中道」の大会は、新代表候補として旧立憲民主から小川淳也と階猛の二人が立候補し、投票の結果5票差で小川が新代表となった。代表選後の記者会見で憲法改正について小川は憲法改正論者ではないとしつつも「自衛隊の明記がありえないこととは思ってはいない」と語った。 小川は党内融和を目指して新執行部を作ると言うが、「左でも右でもない中道」という立場に立つ限り、彼らに未来はない。現在の社会が私有財産を土台として、労働の搾取による利益追求を原理とする無政府的な資本主義体制である限り、富める者と貧しい者との貧富の格差はなくならないからだ。こうした現実から目をそらさせ、「右でもなく左でもない中道」の立場を唱えることは、労働者、働く者の利益に反対し、資本に追随することである。資本の支配克服を目指す労働者の階級政党の闘いこそが求められている。 (T) 【2面サブ】トランプ「石炭はクリーンで
| |||||||||||