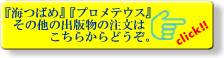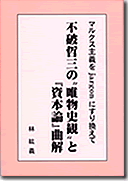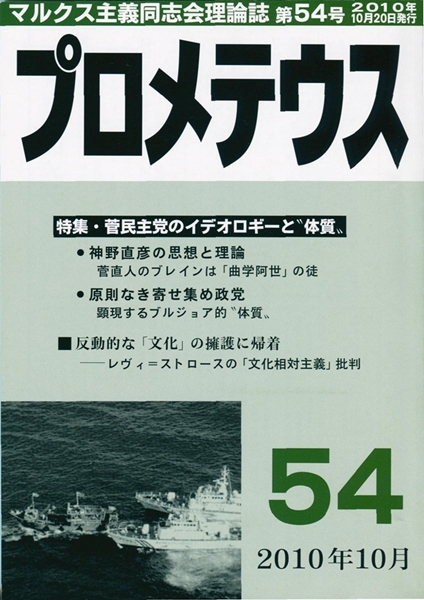|
||||||||||||||||||||
|
●1370号 2020年1月26日 【一面トップ】中東派兵と共産党――安倍のトランプご奉公 【コラム】飛耳長目 【二面〈主張〉】共産とはどうなる?――立・民 国・民に袖にされ 【二面サブ】60年安保と樺美智子――果たして死に値する闘いだったか ※『海つばめ』PDF版見本 ※注文フォームはこちら 【1面トップ】 中東派兵と共産党 河野は11日、P3哨戒機が、那覇空港から中東めざして飛び立つに際して、「世界の主要なエネルギーの供給源である中東地域、日本船舶の航行の安全を確保することは非常に重要である」と訓示した。こうした言葉がどこまで真実であり、どこまで建て前であるかはさておくとして、それは、米国の〝同盟国〟としての安倍政権の中東への軍隊派遣の公式の発言である。共産党などは勿論派遣反対を叫ぶが、一体いかなる立場から反対し、また闘おうとしているのか。彼らは本当に労働者・働く者の立場から闘っているのか、ただ口先だけで闘っているのではないのか、むしろ民族主義的立場などに転落して安倍政権を助けているのではないのか。我々は厳しく点検しなくてはならない。 共産党の観念論と的外れ もちろん日本の自衛隊が、今回あたふたと中東くんだりに出かけて行ったからと言って、中東の政治情勢を左右し、大きな影響を及ぼすことはありえず、ただのゼスチャー、単に米国の顔をたてただけといったことに終わり、1991年の湾岸戦争以来の関与や2003年以降のイラク戦争への実際的参加の〝構図〟を変えるものでない、つまりいまだ日本は本気ではなく、米国の〝目下の〟、二流の、腰の座らない帝国主義国家として、おずおずと米国の驥尾に付しているが、しかし立派に世界帝国主義勢力の一環を占め、米国への忠義立てに懸命である。 そもそも日本の自衛隊の今回の派遣が日本の船舶の〝護衛〟といった役割を果たすかどうかさえあやふやで、そんな意味で派兵の必要などほとんどないかもしれないのである。つまり派兵のための派兵、形でだけの派兵である。 米国にとっては、中東の石油はすでに絶対的なものではない。別の形で採掘される米国の石油資源は、したがってまたその採掘量はすでに世界でもトップを争うほどで、かえって輸出を可能ならしめるまでになっている。むしろ中東の石油に依存しているのは中国であり、そして日本である。だからペルシャ湾やホルムズ海峡の〝安全〟に死活の利害関係を持つのは米国というより、中国や日本である。日本の〝防衛〟にもっと日本はカネと犠牲を覚悟すべきと同様、中東の〝安全〟のために真剣になり、世界の憲兵としての役割から来る、米国の負担を減らせというのが、〝米国第一主義〟のトランプの議論である。 こうしたトランプの理屈に、少なくとも日本の〝安全〟や〝平和〟にどんな野党よりも熱心な共産党が、共感しないのはどういうことか。 そもそも共産党は15年の安保法(彼らが〝戦争法〟と名付けた法案)が自衛隊の海外派遣を野放しにするから反対だとデモを組織し、閣議決定は憲法違反だと強調し、その決定廃棄を訴えて来たのではないのか。法案閣議決定を取り消せと言い、またそのことを今後生まれるかもしれない野党共闘の共通政策と、したがってまた野党共闘の政府が実現すべき綱領として謳ったのではないのか。 とするのなら、共産党はいかなる法的根拠で、今回の安倍政権の調査や情報収集のための自衛隊派遣に反対するのか、この派遣は防衛庁設置法や自衛隊法等々によるものであって、閣議決定から出発した、国会決議だけの〝戦争法〟によるだけのものではない。国連憲章違反だ、憲法違反だと叫んでみても迫力もなく、安倍政権は蚊に刺されたほどの痛痒も感じていない。 もともと閣議決定を取り消せとか、15年の〝戦争法〟の廃棄だなどと言う闘い方はナンセンスで、無力なものである。共産党はこの間、安倍政権の帝国主義的政策と闘う中心に、この法案の撤回、つまり憲法違反の閣議決定の取り消しに備えて、それを野党共闘とその政府に向けての共同政策に盛り込み、参院選などを闘ってきた。 我々はそんな〝闘い方〟もしくは戦術はばかげたもの、無力なものと結論し、闘いの原則は、現在進行する安倍政権らの実際の帝国主義的策動と、まさに現実的、具体的に闘うところにあると強調して来た。 問題の根源は〝法律的な〟関係にあるのではなく、実際的、現実的な政治的関係であり、さらにはその根底にある経済的な利害関係である。 自衛隊の海外派遣が憲法違反だというなら、そもそも憲法違反の軍隊や、同様なものが組織されたときにまでさかのぼって問題にしなければならないだろう。自衛隊の海外派遣が憲法違反だというなら、そもそも憲法違反の自衛隊が生まれたこと自体が憲法違反であるから、そこにさかのぼって自衛隊を誕生させた法律が問題ということになり、否、むしろさらにさかのぼって、警察予備隊が問題になる、当時の自民党やその政府が警察予備隊を誕生させたときにさかのぼって法律違反を問題にせよといった、つまらない話になるだけだ。 現実の階級闘争や、政治闘争を何か法律問題に還元し、矮小化するのはばかげている。 戦前、戦中、戦後の労働者の階級的な闘いや、共産党などの政治運動がブルジョアや警察や天皇制軍部に、帝国主義者に負けたのは、単に治安維持法や、戦後は「団体等規制法」などのいわゆる〝弾圧法〟が作られ、さらにそれが改悪されて、単に運動が弾圧され、壊滅されたからではない。 法的なものは一つの契機であって、それ以前に、労働者がいかなる戦略や戦術で闘い抜いたかが重要である。共産党の混乱と思想的、政治的堕落と、戦術的な誤りこそが第一義的に問題であり、重要であって、批判的に検討されなくてはならないのである。 そして我々の立場からするなら、今回の中東への自衛隊派遣との断固たる闘いは、トランプの帝国主義的策動への安倍政権による加担との闘いとして、直ちに出てくるのだが、共産党の立場からは、直接には出て来ないのである、彼らはまず憲法の解釈改憲を止め、戦争法を〝撤回する〟闘いこそ第一義であり、優先されるべきだという固定観念で活動してきていたからであり、「派兵命令を撤回せよ」などという、珍奇な要求を並べ、話し合いで、平和的に解決せよといった、毒にも薬もならないような、ありきたりのことしか言えないからである。 共産党は、今回の中東への軍隊派遣に反対する闘いを、ブルジョアや安倍政権に対する重要な現実の階級闘争、政治闘争の重要な一環、彼らの帝国主義的膨張に対する真剣な闘いとして位置づけ、自覚していないからこそ、結局は関係各国が「外交的努力」を払い、「話し合い」や「イラン核合意の立場に戻る」ことによって解決せよ、国連の努力によれだとか、安倍政権はそういうことのために犬馬の労を取るべきだといった、帝国主義国家や政治勢力との闘いの代わりに、安倍やトランプといった悪党たちに幻想を持ち、お願いし、懇願するという無力で、空想的な立場、極反動的なおしゃべりに転落して行くのである。 共産党は外交をどう変える 共産党はこれまで、国際的力関係の変化に全く盲目で、中国を社会主義の大国と思い違いしていたのと同様に、日米関係についても、敗戦後の日米関係と今に至るまで変わっていないと考え、今なお米国に従属するだけの、〝半植民地国家〟と思っているかである。 中東に軍隊を出すのも、米国に言われてやむを得ず行くかに言うのだが、実際には、今回日本のブルジョアや安倍政権は、中東に自衛隊を送ることは余り意味がない、必要がない、日本の利益でもないと考えるのであり、最初から余り乗り気ではない。独立の国家としてはそもそも行きたくないのであって、日米の〝植民地的〟従属関係といったものはすでにないのである。 むしろ今後の経済交渉で、トランプに無理難題を押しつけられるのを恐れて、彼らのご機嫌を取っておこうかという思惑があって、形だけの軍隊派遣を言うのであり、本音は、「大義のない有志連合には加わりたくない、むしろ米国でもイランでもない立場に留まりたい、それの方が日本の経済的な利益だ」と考え、米軍駐留経費の増額や、通商交渉のきつい要求もあり、「今はトランプの顔を立てて、恩を売っておく必要がある」とケチな打算にふけるのである。もちろんこうした打算がトランプにどこまで通用するかは、神のみぞ知るであるが。 共産党は自衛隊を中東に送るなと言いながら、日本の国益を守れという。では日本の船舶が米国とイランの軍事衝突が起こり、激化したりして、イラン革命防衛隊の攻撃を受けるような事態になったとき、いかにせよというのであろうか。 日本のブルジョアは米国の大ブルジョア勢力と同盟することで、すでに立派に国際的な帝国主義の覇権争いの一角に位置するのだが、それでもトランプの後について漁夫の利を得ようと振る舞うのだが、それはちょうど1930年代から40年代にかけて、ナチスドイツ(ヒトラー)に追随し、迎合して、ヒトラーの世界覇権の野望のおすそ分けに預かろうとして破滅し、みじめな最期を遂げた、イタリア・ブルジョア(ムッソリーニ)の立場に似ている。 共産党は盛んに、米国とイランの双方とも戦闘状態を拡大する意思がないと分かってからも、「不測の事態が起こり得る」とか、「一触即発の危機が消えたわけではない」、「衝突が起こらない保証はない」等々、危機意識をあおり、依然として危険だ、自衛隊は行くべきではないなどと言いはやしている。 空想や願望だけで語ることを止めるなら――もちろん、現実に責任を持つ政党なら、このことは当然である――しかし共産党は依然として空想や願望について語って、話し合いで解決すべきだとか、派兵ではなく、米国に「核合意復帰を求めよ」とか語って、問題をすり替え、ごまかしているだけである。 もし共産党が国家主義的、民族主義的立場に立つなら、しかも中東で戦火が拡大するというなら――共産党もそのように現状を分析している――、どうして安倍政権は自国の船舶の安全やエネルギーを確保するために、中東に、あるいは必要なら、全世界に軍隊を送るということになることに反対するのか、できるのか。 もし不測の、「一触即発」事態が現実のものとなり、日本のエネルギー確保が危機的になるなら、安倍政権は中東への軍隊を何らかの形で増強するだろうし、そうしなかったら安倍政権は崩壊するしかないから必ずそうするだろう、そして共産党もまた安倍政権に賛成し、追随するのか、しないのかを迷うしかない。 ただ世界的な帝国主義勢力とその策動に反対して闘う労働者の党だけが、そんな状況の中でも一貫して闘い抜くことができるのである。 話し合いで解決路線の幻想 志位は帝国主義が新たに勃興する21世紀の世界の中で、「話し合いで解決」といった自由主義的、プチブル・インテリ的勢力と同様な立場を叫んでいる。 しかし今や帝国主義の発展する中で、彼らの見解や日和見主義はますます空疎で、非現実的なものと化しつつある。 中国の強大なブルジョア的帝国主義国家としての登場と展開は、現実的であり、その勢いは米国の後退ぶりと好対照に、21世紀前半の世界を象徴し、時代を画するものとなっている。 米国が日本に応援を期待するのは、米国が増々強大となっているからでなく、後退しているからであるが、この点で志位らは何事も見ていないし、評価もしていない。これまでは見る必要がなかったのである、というのは旧ソ連も、共産党支配下の中国も、社会主義国家であって、中国の専制主義も帝国主義も彼らにとって恐怖の対象でなく、根底においては、〝安全な〟、彼らの理想に合致した国家だったからである。 今やそんな幻想からようやく冷めた志位らは、今後国内の政治でも、国際的な政治・外交でも、どんな立場に立つというのであろうか。 社会主義の社会ではではないと遅まきながら、愚鈍にもようやく悟ったというなら、それでは旧ソ連は、昨日までの中共は、金王朝の北朝鮮は如何なる国家社会なのだというのか。話し合いで平和的な政策を採用するような〝物わかりのいい〟、理性的な国家だというのか、新左翼やトロツキストと同様に、〝労働者国家〟とか、無概念の〝過渡期国家〟とでも規定するのか。そしてそう規定したとして、中国や北朝鮮との〝外交政策〟はこれまでと同じなのか、根底から違うものになるのか。 愚かな志位はそんなことは知らない、どうでもいいことだとばかりに、平和主義的な決まり文句を叫べば、票が増えると勘違いして、野党のつまらない、そして確かな見通しもないような連合遊びにせいを出すだけである。 いずれにせよ、米国は強く、のぼり調子の、強い国家だから、日本を力づくでも米国の応援勢力として動員するというのではなく、後退する帝国主義勢力だから――もちろん相対的には、いまだ中国をも凌駕する世界最強の国家だが――、西欧や日本の勢力を動員しようというのであって、共産党が米国をこれまでのように日本を圧倒的に支配する帝国主義国家であると考えるなら、今後の路線問題で致命的な判断ミスを犯し、間違えることになるだろう。 ロシアは言うまでもなく、中国もまた社会主義国家でないとするなら、世界は今や権威主義的で、自国第一主義の支配する、ブルジョア帝国主義の時代に再び、三度人類は突入していると評価すべきである。 しかもかつてのようなヨーロッパ規模の、欧米規模の強国の争うかつての帝国主義ではなく、米中やロシア等々が絡んで、インドなども参入して、超大国同士が対峙し、争う〝超〟帝国主義――カウツキーが云うのとは違った意味でではあるが――の時代である。 元防衛大学学長のブルジョア評論家の五百旗頭(いおきべ)真は、志位と基本的に同じの観念を、次のように表現している。 彼の判断するところでは、日本は、中国に対しては、「南シナ海や尖閣諸島に対する強硬姿勢は国際社会に通用しないか」からやめよと言い、米国には「孤立主義に回帰する」のは良くないからやめよというべきだそうである。 具体的にどういうことか記者が尋ねると、ブルジョアの中の泰斗は、次のような支離滅裂の発言をするしかなく、ブルジョアの知恵の底の浅さを暴露し、志位=五百旗頭の知恵の破綻と、その実現がいかに困難なものであり、むしろ空中楼閣なようなものにしかなり得ないことを暴露してしまった。 「日米同盟プラス日中協商という基本が大切だ。米中の戦争は選択肢とはなり得ない。日本も確実に火の粉をかぶるわけだから。とはいえ、米中両大国だけでは、世界秩序の再編という前向きの合意は難しいように思う。第二次世界大戦時の秩序作りも米ソ両大国の間に英国が入ることで可能になった。今日では日欧が米中双方を動かさねばならない」(朝日新聞1月13日)。 ここにあるのは、まず米中という帝国主義に走るブルジョア大国に対する幻想であり、願望であり、さらに結論に至っては、まるで支離滅裂な論理に加えて、歴史的な知識の初歩的な混乱と混濁である。 「第二次大戦時の秩序作り」とは米英を中心とした〝自由〟資本主義勢力と、全く毛色の違ったスターリン主義専制勢力との同盟関係のことなのであろうが、そんなものは、独伊日3国の〝枢軸側〟(ファッショ国家の連合、同盟)を除いたものであって、二大陣営の対決の激化と、戦争開始と貫徹に行きつきはしたが、世界の〝平和〟や、「国際秩序」の再建と言えるようなものは何も残さなかった。 要するに自由主義派も、独善的セクト野党(共産党のことである)も、安倍政権とその中東政策反対して、何一つまともなことも言えなかったのであり、安倍政権はどんな強硬な、手痛い反撃に会うこともなく、大手を振って中東への軍隊派遣をやることかできたというわけである。めでたし、めでたし。 (林紘義) 【飛耳長目】 ★安倍の施政方針演説を丁寧に読んでみた。もちろん苦労なくては無理な、しんどい作業だ★それにしても、もっともらしい話を次から次へと並べ立てる才能だけは大したものだと勘違いしそうだ。これだけ並べ立てると安倍先生、実は多くのまじめな仕事を山ほどしてきたのかと納得し、安倍支持に走る連中も結構いるのもさもありなんと、妙な感心までしてしまう★「全世代型社会保障」について語ったところを読むと、この春から同一労働同一賃金が始まったとか(まるですでにそんな社会になったかである)、「70才までの就労機会を確保する」(確かな話なら結構だが)とか、「最低賃金も過去最大の値上げ」(「現行方式になってから」というただし書き付き)とか、「年金、医療、介護全般にわたる改革を進める」(いったいどんな改革であることやら)とか、「現役世代の負担上昇に歯止めをかける」(どれ位ですか、少しなら誰にでもできる)とか、きれいごとや、言葉だけの話、要するにうまそうな話をいくらでも並べている★要するに、八方美人的な話で、あらゆる階級や全ての人に心地よい、うまい話や約束の大安売りをし、そんな政治で長期政権維持を実現しようとするのだが、そんな矛盾した政治が長続きするはずはなく、全ての階級階層へのバラまき政治は全ての階級階層の不満や反感や怒りにさえ転化し、行き着くのである。(鵬) 【主張】 共産とはどうなる? 立・民と国・民の衆院選に向けての結婚話が、21日、最終的にとん挫した。 商業新聞は、立・民の昨年12月6日の合併要請を国・民が断ったからだというが、問題は単純ではない。 そもそも共闘か独自かは、17衆院選で現在国・民に所属する議員たちが、小池新党に雪崩を打って殺到し、野党共闘が解体した時、始めは動揺していた枝野らが小池から排除宣告を受けた後、やむを得ずに新党を立ちあげ、共産党などの主導する野党共闘路線に便乗したことから発している。 枝野は思いもかけぬ議席が得られたことに感涙し、支持率1%の国・民、何するものぞと増長し、立・民の洋々たる未来を幻想し、〝独自路線〟を誇った。 つまり〝独自路線〟を強調したのは枝野であって、国・民の玉木らではなかったのである。 そんな枝野が国・民との合併話を持ち出し、執心したのは、単に国民に不人気なのは、国・民だけでなく、立・民も同様だという、至極当然の真実がたちまち明らかになってきたからである。 狼狽し、当惑した枝野は〝左の〟共産党と、右の国・民の双方を懐柔し、手玉に取り、その真ん中でバランスを図り、野党を「一つの大きな塊にする」ことなしには――この言葉はもともと国・民の玉木の決り文句だったのだが――、玉木も枝野もともに破綻するしかないのを悟ったのである。 もちろんより傲慢で、自己中なのは、立・民である。 枝野は元来は〝別党コース〟をわめいていたことを忘れたかに、今や党合併を唱えるのだが、国・民は事実上解党して立・民に加われ、立・民の名前は譲らない、人事も立・民優位でやる、と言い放つのである。 他方、玉木は対等合併を謳うが、理念も路線も違い、すでに09年から12年まで政権を握りながら、労働者・働く者を裏切った「民主党」の名に戻れというのだから、そんな話に乗ったらすべてぶち壊しだと思っている立・民の連中が乗れる話ではない。 また立・民は国・民の謳う「改革中道」という路線を嫌ったが、それはただ周りの目を気にしてのことであって、実際の政治路線は国・民と大して違いがないのだから仲良くやればいい。 国・民の玉木は、今さら、「政策や理念のすり合わせもなく、表層だけで党を同じくしても、政権を担える大きな塊にならない」というが、労働組合のダラ幹の圧力を受けて、表層だけの一致の「大きな塊」を追求したのは玉木自身であった。 他方、かつては「表層だけの一致」を拒否していた枝野は、切羽詰まれば国・民や共産党に野党共闘を呼びかけるが、それは果たして「表層だけの一致」ではないのか。そもそも国・民や共産党と「表層」だけではない、真の一致が可能だというのか。 そして最後に、朝日などの自由主義的インテリ層の無節操とナンセンスを明らかにしておく。 彼らは09年の民主党政権の成立の最強のスポンサーであって、「まず大事なことは政権交代だ、内容はどうでもいい、ともかく民主党政権だ」と大キャンペーンを張ったが、今も野党共闘の成功に、「政治の緊張に期待した有権者がいたのではないか」とか、「政権交代の機会はそう遠くない時期に訪れる。……両党がお互いに信頼関係を醸成し、有権者の期待をかちとるしかない」などと書き立てているが、ここでいう「有権者」とは何のことはない、朝日新聞の野党取材キャップの村松等々のことでしかない。彼らは自分のつまらない、空虚な願望を「有権者」の名で語るべきでない、というのは多くの労働者・働く者は彼らよりはるかに賢明であり、空っぽで、結局は破綻するしかない野党共闘などは、ほとんど信用も期待もしていないからである。 【2面サブ】 60年安保と樺美智子 60年前の労働者、学生の日米安保条約に反対する〝激しい〟闘いとは、一体何だったのか。「日米対等」を謳った、新日米安保条約が批准され、成立したのは、60年前の1960年の5月のことだった。しかしあの闘いは、始めは少しも高揚した闘いでも何でもなく、社共や総評を中心とする「安保反対国民会議」が領導する、「日本の平和と民主主義を守るための」、平凡で、惰性的ともいえる闘いの一つで、スケジュール的にくまれたデモに参加した組合幹部らは、「重い、重い」とこぼしながらデモっていた位であった。安保改定の策動は、戦犯だった岸信介が政界に復帰し、57年に早くも首相になるや、「日米対等」を謳い文句に、占領下で有無を言わせず押し付けられた、便宜的で、〝不平等な〟旧安保を改正して手柄にしようとした野心から始まったものであった。もちろん背後には、52年に独立し、曲がりなりにも自立した国家になり、ブルジョアたちも自信を取り戻し、〝怒涛のような〟高度経済成長も始まったという歴史的な背景もあった。 闘争が〝盛り上がった〟のは、前年の暮、共産党を除名され、あるいは離党した学生党員によって全国的に組織された「共産主義者同盟」(通称、ブンド)――自ら共産党に代わる、世界で唯一の誇り高き、真実の〝前衛〟であると自称した――に結集した学生らの〝暴走〟が、大きな衝撃を与えてからであった。 ブンドの指導の下にあった全学連は国民会議の方針に反対し、それを乗り越えて、形式的な〝国会デモ〟ではなく、安保改定策動を現実に阻止する〝国会デモ〟を闘い抜こうと決意し、〝国会突入〟を策して、3方面から国会に向けて攻め上り、国会正門を突破し、議事堂前の広場に突入、数時間にわたって占拠するという〝大闘争〟に成功してからであった。 あの日の闘争は、国民会議の下に〝平穏裡〟にデモを行っていた、社共や、総評の影響下の労働者や学生まで巻き込み、数千人のデモ参加者の全員が国会前の広場でデモを繰り返し、議事堂の内部までも侵入して占拠する勢いを示し、岸政権は自衛隊の出動まで考えるなど、その心胆を寒からしめるに十分であった。 この闘いを契機に、社共や国民会議は全学連を「統一戦線」から排除する策動を強め、ブンドも彼らと一線を画して、共産党などと激しく対立しながら、独自の〝実力闘争〟に走り、翌年1月の岸渡米を阻止するための、羽田実力闘争等々を経て、4月、新入生のエネルギーも結集して勢いをつけ、4、5月の安保条約成立期のピークに向けて闘いを盛り上げていった。 そしてその闘いは安保条約の〝自然成立〟に抗議する6月19日の直前の、運命の15日のデモで頂点に達した。ブンドはこの日、前年の国会突入闘争の成功に味を占めてか、柳の下にまたドジョウがいると信じてか、国会構内抗議集会を勝ち取るためと称して、南門からの国会突入を図り、二度とそんな〝暴挙〟は官憲の沽券にかけても許さないと、南門をガチガチに固めた機動隊と正面衝突した。 そしてその時、あの痛恨の悲劇が襲ったのである。 南門での学生と機動隊の衝突の中で、ブンドの誰よりも誠実で、清廉な活動家、樺美智子が命を落としたのである。全人類の解放という理想のために、一生をかけても闘おうと決意していた、一つの余りに若い、尊い命が失われた。 彼女の命と引き換えに、というのはいくらかいい過ぎで、誤解を招くかもしれないが、結果として岸政権は、彼女の死の衝撃もあって倒れたが、安保条約の方は無事成立した。 安保条約の意義や安保条約が表現する日米同盟の性格も内容も時代と国際情勢の変化と共に変わってきたが、しかし安保条約に象徴され、示される日米同盟は60年間も続き、現在に至っている。 その評価は今ここで全面的に語り、展開することはできないが、筆者の感じることは、果たして安保反対闘争は、本当に彼女の死に値するような意義があったのか、ということである。 いかに不遜に思われようと、我々はこうした疑問を提出するし、せざるを得ない。 社共(現在は野党共闘派、野党の面々)やリベラルは、何か安保条約や日米同盟を特別なものとして重視し、それに賛成か反対かで長年争ってきた。 共産党などはソ連や中共を社会主義国家と評価し、一貫して米国等々ではなく、ソ連や中国と友好関係を結べと主張し、そんな政治を労働者・働く者に押し付けてきたが、今や共産党自身がそんな政治は間違っていたと、綱領をあたふた変えるといった醜態を演じている。 (林紘義) |
|||||||||||||||||||