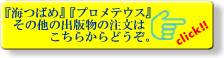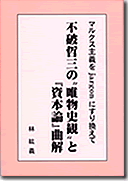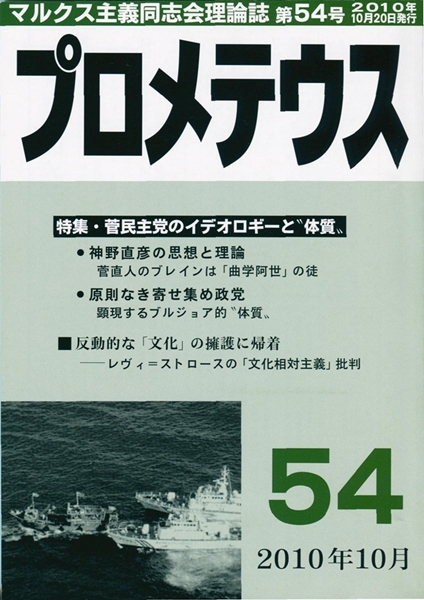|
||||||||||||||||||||
|
●1404号 2021年6月13日 【一面トップ】 中国への軍事的対抗強化の提案――国・民や立・民らの国防策 【1面サブ】 膨大な債務から目を逸らす――国の破綻は民間が負えと 【コラム】飛耳長目 【二面トップ】 マルクスは「脱成長」論者だったか――斎藤幸平によるマルクス主義の歪曲(下) ※『海つばめ』PDF版見本 【1面トップ】 中国への軍事的対抗強化の提案 中国公船による尖閣海域航行が続き、マスコミをにぎわす中で、今月2日、国・民と維新は共同で「自衛隊法及び海上保安庁法の一部改正案」を、立・民は翌3日に「領域警備・海上保安体制強化法案」をそれぞれ衆院に提出した。3月30日には自民党国防議員連盟が加藤官房長官に、中国公船の尖閣諸島周辺の領海侵入の対応強化のため、海上保安庁法や自衛隊法の改正を提言していた。それらは、外交の行き詰まりを軍事的対抗で解決しようとするものである。 ◇軍国主義化促進の国・民と維新の「改正案」 国・民らの提出した「自衛隊法及び海上保安庁法の一部改正案」の目的は、「領海等における公共の秩序の維持を図るため、自衛隊の部隊による警戒監視の措置及びその際の権限について定めるとともに、海上保安庁の任務として領海の警備が含まれることを明記する等の必要」のためというものである。 自衛隊が「必要な情報の収集その他の警戒監視」をすでに行っていることや、海上保安庁が尖閣諸島で「領海警備」していることを承知の上で、そうした任務を「明記」するための法案だと言いながら、大事なことを隠しているが、その狙いは自衛隊による「監視」の強化であり、海保による「領海警備」の強化にあることは明らかである。 自衛隊の権限を強化して、軍隊としての自衛隊の役割を正当化しつつ、「領海警備」の任務もさせようということであり、警察機関の海保を公然と軍事活動に動員し、軍事的な活動を強化しようということである。 国・民らの提案は「公共の秩序の維持」を名目に、国防のための監視を強めたり、海保の警察機関としての行政を軍事化することを公然と押し出したりして、軍国主義化を促進しようとするものであり、自民党の反動の後追いをしているだけである。国・民らは「公共の秩序」を権力者の都合で考えず、尖閣を巡る中国との軍事的緊張をいかに平和裏に解決するか考えるべきではないのか。中国公船の尖閣海域航行による緊張を外交的に解決しようとすることより、それを利用して軍備増強を企む菅政権を後押しして恥じないのか。 ◇立・民案は新設の自衛隊任務で形式的に区分け 野党第1党の立・民の「領域警備・海上保安体制強化法案」は、「警察機関及び自衛隊が事態に応じて適切な役割分担の下で迅速に行動できるようにするため」、「領域警備基本方針」を策定して(「5年ごと」の「計画的」に)海上保安体制を強化し、その上で自衛隊の任務に「領域警備」や新設の「海上警備準備行動」を加え、自衛隊が海保の活動を補完できるようにするものである。 「領海等及び離島等における公共の秩序の維持のための活動は、警察機関をもって行うことを基本とし、警察機関をもっては公共の秩序を維持することができないと認められる事態が発生した場合には、自衛隊が、警察機関との適切な役割分担を踏まえて、当該事態に対処する」というもので、国・民らの「改正案」と実質的な違いはなく、違うのは独立の法案として提出している(新設の「領海警備行動」や「海上警備準備行動」を現行の自衛隊による「海上警備行動」と分けたり、対応を区分けしたりしている)ぐらいと言っていいようなもので、自衛隊に海保の補完として領海警備をさせて中国と対抗しようというのである。 警察機関の海保でなく、軍隊である自衛隊に「領海警備行動」や「海上警備準備行動」をさせることは、軍事的緊張を高めることは必至である。それを承知で、自衛隊による情報収集についても、「領域警備区域における公共の秩序を維持するため」であれば、「不法行為の発生の予防及び不法行為への対処その他の必要な措置」と共に、できるものとしており、これまでの情報収集や監視を強化する内容であり、外交における対立は軍事的に解決するしかないという精神に貫かれている。それが軍国主義化に手を貸すものであるという反省がないのであろうか。 ◇軍国主義化に反対して闘おう 大差ない国・民や立・民らの提案が国会でどう扱われるかは分からないし、「成立の可能性は低いが、中国に絡む現実的な外交・安全保障政策を打ち出すことで、次期衆院選に向けて支持層拡大を図る狙いがありそうだ」(6/3朝日新聞デジタル)と言われてはいるが、2日に自民党の安全保障調査会と国防部会が菅首相に、「激変する安全保障環境に対応した防衛力の抜本的強化のための提言」を提出しており、中国公船の尖閣海域航行による緊張を利用して、軍事力の一層の強化で対抗しようとする動きは強い。 「中国が東シナ海や南シナ海などで繰り返している国際法違反の覇権主義的な行動は決して容認できません」(6/5赤旗主張)という我が共産党は、「中国に対しては国際法に基づく批判を強めて外交的に包囲するとともに、米国の覇権主義も許さない立場を取ることが急務」(同前)だと、相変わらずブルジョアジーの重宝がる国際法(歴史的・階級的評価をするべきだ!)を持ち出しているが、「外交的に包囲する」ということについて、8日付赤旗の「社会は変わるし、変えられる――志位さんと語る学生オンラインゼミ」で、空想的な「北東アジア平和協力構想」を唱えている。 これは、「ASEANのような話し合いのテーブルを本当に実現できるのか」という学生の質問に志位が答えたもので、「困難はあるのですが、私は十分に現実性がある」と、2011年11月の東アジアサミットで「バリ原則」が調印されたことを高く評価している。 「『バリ原則』を見ますと、武力行使の放棄、紛争の平和的解決など、TAC(「友好協力条約」のこと)が掲げている諸原則がそっくり入っている」と言って、ASEAN幻想を振りまいている。 その諸原則のひとつに「締約国相互での内政不干渉」が謳われているが、ミャンマーの軍によるクーデターに対してASEANが、「暴力行為の即時停止」を求めたのは内政干渉でないのか、それは否定すべきことか。志位は労働者の国際的連帯とブルジョア国家の「協力」の違いも分からない「共産主義者」でしかない。 覇権主義を強める国家資本主義の体制である中国の帝国主義的行動に対して、中国において習体制の強権的な支配と勇敢に闘う労働者と連帯を強め、軍国主義化を進める菅政権と闘っていこう。 (岩) 【1面サブ】 膨大な債務から目を逸らす 国の破綻は民間が負えと コロナ不況対策と称して世界中で大量な国債が発行されている。日本も21年3月末時点での国債残高は1074兆円となり過去最大を更新した。さらに21年度予算でも大規模な財政出動が打ち出され、さらに厳しい財政負担を背負い込もうとしている。だが、こうした財政負担から意図的に目を逸らす論者が増えている。 ◇世界最大の国債残高も何のその MMT派経済学に倣ってか、日本の借入が過大であっても弊害は生じていないと言うのは「みずほリサーチ&テクノロジーズ」の門間一夫である。門間は次のように言う。 「日本の国債残高が過去最大で他の国よりも大きいのは事実だが、その裏には民間では満たすことが難しい国民のニーズ、大規模な資金偏在、民間需要の弱さなど様々な要因がある。景気の過熱、金利の上昇、民間企業の資金調達の圧迫など、『国の借入が過大である』ことを示す現象も起きていない」 門間は民間の国債消化ができない理由に、「国民のニーズ」や「民間需要」や「資金偏在」を挙げている。同じ理由を並べた意味のない文中の行間を読むなら、政府・日銀による超低金利(マイナス金利)政策によって、民間が国債を買う利点は無くなり、国債は民間を経由して日銀に買われブタ積みされていると言うことであろう。 それでも、物価や金利上昇の兆しはなく、「国の借入が過大である」という兆候は皆無であると門間は楽観論を振りまいている。自国通貨を発行する国では、どんなに借金をしても問題は起きないと言いたいのであろう。 ◇債務不履行がまた発生 最近、石油産出国であるレバノンで債務不履行が発生した。レバノンは内戦の後遺症もあって経済的苦境に陥っていた。レバノンは自国通貨建の国債を発行してきたが、残高がGDP比で150%にも上り、物価上昇を招くなどして行き詰まり、国家信用を毀損させ、国債も通貨も暴落し債務不履行になった。今の日本と直接比較することはできないが、GDP比230%に達する日本の巨額債務に対する国際的な信用度は低下しつつある。ギリシャの破綻も些細な信用低下から始まったのだ。 債権者にとって国債はあたかも利子を生む資本のように見え、期限付き資本を有しているかに見える。国債を持てば、銀行資本の貸付と同じように、何の労働もせずに利子が手に入るからである。だが、国債で集めたカネは利潤を生む資本として投下されず、ただ歳出されるだけであり、1年も経てば無くなっている。 国債で集めたカネが資本投下されない以上、資本に見えても、国債は純粋に「架空資本」(マルクス)である。だから、国債は国の信用付借用証書であるから、信用を失うなどで売れなくなった瞬間にただの紙切れになる。そうなれば、国債がいくら日銀倉庫にブタ積みされていても救済されえない。この基本的なことを知らないから、門間らは無責任なことを言い放つのである。 さらに門間は、「国債残高は確かに膨大だが、民間金融資産の残高はそれ以上に膨大である」、「差引で見れば、将来世代の手元へ渡るのは債務ではなく財産である」と述べている。 債務と資産を差引きできるのは同じ家庭や同じ企業の中での話であるのに、門間は隣の家庭や企業の会計までひっくるめるという奇想天外な話をしている。その結果、門間は国の債務は民間の財産(預金や家や土地など)で担保できると述べる。要するに将来の国の破綻は民間が負うのだと述べているに等しい。この男ほど現代のブルジョアたちの本心を代表している者はいない。 (W) 【飛耳長目】 ★スーパーで冷凍した「キューブ魚」に出くわした。骨なしの魚の身を重ね、一口サイズにカットされていて、食品ロスも家事も減らせる〝優れモノ〟だ★大豆や小麦から作る植物肉や、植物工場製野菜など、工業的手法による食料生産の拡大は、自然環境に制約されない食料生産の拡大でもある。はたして飢餓を無縁のものにする手段となるのだろうか★50年前の世界の人口38億人は今では80億人、その内8億人が飢餓人口だ。だがそれは、食料や農耕地の絶対的不足の問題ではない。肥料や農薬、多収穫品種の開発といった科学技術の発展で農業と工業が結合し、生産力は飛躍的に増大しているのに、資本主義的農業は無政府的で、支払い能力のある需要にしか向けられない★価格維持のための生産調整は、飢餓に苦しむ人々には絶望的現実だ。加えてアフリカや東南アジアなどでは次第に資本主義的生産の発展が進んでいるが、今なお欧米や日本によってコーヒーや紅茶やパーム油脂などの単発農業を商業的に強いられ、さらに未だ続く内戦による生産と生活破壊と大量難民が飢餓を大量生産している★飢餓からの解放には。人類社会が私利と利潤の社会=階級社会であることを止め、発展段階を異にする二百以上の国が対立する分裂状態の解消が必要だ。 (Y) 【2面トップ】 マルクスは「脱成長」論者だったか ◇ロシア「農村共同体」の評価 斎藤はマルクスのアジア的生産様式の研究、とりわけロシアの「農村共同体」=ミールについてナロードニキのザスーリチへの手紙を挙げて、「ヨーロッパ中心主義」の態度を改めた証拠だという。 資本主義が発展する中でヨーロッパでは古い共同体は解体していったが、ロシアでは依然として広範に「農村共同体」=ミールが残されていた。それは構成員である農民が長老、役員を選び、役員が中心となって、共同所有である森林への伐採・入会権や森林や漁場・猟場を使用する権利を定める農民の自主的な組織であった。 ナロードニキは、ロシアでは西欧のように資本主義を経ないで社会主義に移行できるとしていたが、ミールについてのマルクスの考えを聞いた。これへの回答がナロードニキ=ザスーリチへの手紙の草稿である。 斎藤が引用しているのはマルクスの次の文章である。 「この新しい共同体は、原古的な原型から受け継いだ特徴的なおかげで、全中世を通じて自由と人民生活の唯一のかまど〔根原〕となっていた」(全集19巻389頁)。 これについて斎藤は、生産力の発展を基礎として将来の社会を展望していたこれまでの「進歩歴史観」の「大転換」を示しているとして、次のように述べている。 「ここで重要なのは、エコロジー的な問題意識である。この手紙から読み取れるのは、晩年のマルクスの認識はつぎのようなものだ。資本主義のもとでの生産力の上昇は、人類の解放をもたらすとは限らない。それどころか、生命の根源的な条件である自然との物質代謝を撹乱し、亀裂を生む、資本主義がもたらすものは、コミュニズムに向けた進歩ではない。むしろ、社会の繁栄にとって不可欠な『自然の生命力』を資本主義は破壊する。マルクスはそう考えるのに至ったのだ」(185~6頁)。 斎藤は、マルクスによるリービッヒの資本による農地の「収奪」の研究などを持ち出して、自然環境の破壊と社会の破壊をもたらす資本主義の発展した西欧よりも自然との調和のもとでのロシアの農村共同体の方が「優れた」社会組織であることを認め、将来の社会の基礎として認めるに至ったというのである。 しかし、これは自分の「脱成長」社会を目指すという問題意識に引き寄せてマルクスの思想を歪曲することである。 マルクスはこう述べている。 「ロシアは、共同体所有が広大な、全国的な規模で維持されている、ヨーロッパで唯一の国である。しかし、それと同時に、ロシアは、近代の歴史的環境のうちに存在し、より高次な文化と同時期に存在しており、資本主義的生産の支配している世界市場に結び付けられている。 それゆえに、この生産様式の肯定的な諸成果をわがものとすることによって、ロシアは、その農村共同体のいまなお原古的な形態を破壊するのではなくて、それを発展させ、転化できるのである」(同前、401頁)。 世界資本主義と市場で結びついているロシアでは、農村共同体の上に君臨する専制君主の支配を打倒し、イギリスなどヨーロッパ資本主義の「肯定的な諸成果を繰り入れる」ことによって社会主義に移行することができるとマルクスは述べている。ここが肝心なところである。 「(資本主義の)肯定的諸成果」とは高度な生産力の発展のことであり、それを「わがものにする」ことを前提にして、マルクスが社会主義に移行していくことが出来るといっているにもかかわらず、斎藤はこのことを無視してあたかも、資本主義の下での生産力の発展が環境を破壊し、人類存続の危機をもたらすということを反省した結果、農村共同体はそのまま社会主義へ移行の道(=脱成長・コミュニズム)を追求するようになったといっているのである。 前資本主義の農村共同体についてマルクスが評価しているのは、その下では生産手段(土地)の共有、協同労働が行われていることである。 将来の社会は、資本主義的発展から取り残されて存在している共同体組織がそのまま新たな社会として移行するのではなく、「より高い形態」として復活する、つまり、生活の糧を獲得するのための労働に縛られていた共同体は、「自由な活動」のためへの共同体としてよみがえるのである。 マルクスは、ロシア農村共同体の社会主義への移行の可能性に言及する一方で、引用文の直前では「ロシア社会の発展とともに(つまり資本主義の発展とともに─引用者)、死滅を宣告される宿命にあることは、少なくとも私の見るところでは、一点の疑いもない」と指摘していることを忘れてはならない。 斎藤はマルクスがナロードニキの主張に同調したようなことをいっているが、生産力の発展したヨーロッパの進んだ諸成果を自分たちのものにすることを前提にその可能性があるということであって、「脱成長」とは関係がないのである。 ◇「生産力重視」はソ連型社会主義を生み出した? ところが斎藤は、マルクスがロシアの農村共同体を社会主義への移行形態として評価したことは「生産力至上主義」を捨て「脱成長コミュニズム」へ転換したことを示しているという。 「伝統に依存する共同体では、資本主義とはまったく違う生産原理に基づいている。……共同体の内部には、強い社会的規制がかかっていて、資本主義システムのような商品生産の論理は貫徹してはいない。……/共同体では、同じような生産を伝統に基づいて繰り返している。つまり経済成長をしていない循環型定常経済であった」(192~3頁)。 つまり、若い時のマルクスは生産力の発展の彼方に社会主義を展望したが、それは人類生存の前提である自然破壊という問題を引き起こす、しかし晩年には「経済成長はしない安定性…平等な人間と自然との物質代謝を組織していた」ロシアの農村共同体のような社会組織が目指すものとされたというのだ。 こうして斎藤は、前資本主義の共同体では「経済成長しない安定性が、持続可能で、平等な人間と自然の物質代謝を組織していた」として、めざすべき社会は、「もっぱら自然に依存し、生活していたような資本主義以前の農村共同体、すなわち「経済成長はしない」(「脱成長」)、共同体だというのである。 斎藤が「脱成長」経済を主張する理由の一つは、経済成長を追求することは、専門的な高度知識や技術を必要とし、それは知識・技術を持った一部の専門家や官僚が特権的な地位を持った独裁的社会=「ソ連型社会主義」に行きつくということであり、それは「自治」「共同管理」の原則に基づく「参加型社会主義」に反することになると主張している(190頁)。 しかし、スターリニストの支配したソ連は社会主義ではなく、一種の資本主義=国家資本主義であった。革命ロシアが直接社会主義ではなく、国家資本主義に道をたどったのは、若きマルクスの高度な生産力の発展の下に未来社会(社会主義・共産主義)を展望したという理論的欠陥のためではなく、社会主義建設の前提としての生産力が未発展のためであった。革命当時のロシアは、農民が圧倒的な資本主義の未発展な国であった。 ドイツやイギリスなど先進国の革命は起こらず、期待された先進諸国の革命政権からの援助もなく、孤立した状況のもとでは、ロシアは経済を建設するために労働者、農民の生み出した富を国家に集中して、工業化を推し進めなくてはならなかった。こうしたロシアの後進性が、スターリンの独裁的国家を生み出した社会的背景である。 スターリンは国家資本主義の現実を「社会主義」だと主張し、独裁権力を正当化したが、それはスターリンの罪であって、生産力発展を基礎とする社会主義理論の誤りではないし、反対にマルクスの社会主義論の正しさを明らかにしているのである。斎藤はマルクスの社会主義についてなにも理解できず、スターリニスト共産党が言いはやしてた来たソ連=社会主義論に道徳的に反発しているに過ぎない。 ◇労働者の階級闘争については語らず すでにみたように、生産力の発展の意義を理解出来ない斎藤は、結局は遅れた、停滞的なアジアやロシアの共同体の美化に行きつく。 斎藤ら「脱成長」論者は、エネルギー源として石炭や石油などの二酸化炭素を排出する化石燃料を利用して経済成長を追求してきたため、地球温暖化をもたらした。だから今後は、化石燃料の利用を止め、かつての共同体のように、「経済成長はしない、定常的経済」をめざさなくてはならないという。 しかし、地球温暖化を防ぐために化石燃料の利用を止めることと、「脱成長」経済を目指すことは同じではない。資本はエネルギー源として化石燃料に変えて、太陽光や風力、地熱などを利用に転換しようとしている。とはいっても彼らは、「グリーン計画」などといって、それを新たな利潤獲得の手段にするためにすぎない。利潤目的の無政府的生産の資本主義の下では、資源の浪費、環境破壊は避けられない。 太陽光発電や風力発電には大量のパネル、風力発電機を設置するための広範な土地が必要であり、そのために環境を破壊するという新たな問題が生じているが、利潤追求の資本はこれを真剣に省みることはしない。 資本は電力多消費型の大型家電製品、個人用自動車、個人住宅を生産し、大量の廃棄物を生み出している。資源、エネルギーの浪費をもたらす大量消費、大量廃棄を資本は生み出している。 資本の支配を克服した社会主義のもとでは、自然の利用は社会全体のために計画的、意識的に行われるようになる。公的な交通・運搬手段、住宅の整備、製品寿命の長期化によって省資源、省エルギーが実現される。エネルギー源として現在では未解決の核融合による発電も可能となるかもしれない。 問題は誰のための自然の利用かということであって、生産力の発展自体が悪いことにはならない。ところが斎藤ら「脱成長」論者は、生産力の発展が悪いかに言うのである。 「脱成長社会」論者の描く将来の社会の具体的な例を挙げよう。 例えば、「脱成長論」の提唱者であるフランスの哲学者・経済学者セルジュ・ラトゥーシュは次のように述べている。 「低成長」社会は「可能な限り、経済的な自己自足、すなわちなんらかの封鎖経済に戻ることが望ましくさえある。輸送の外部費用、インフラクチャーの外部費用、汚染の外部費用(温室効果、気候変動)を内部化すれば、多くの活動が再ローカルされるだろう。 とはいえ、目指すべき目標はそんな封鎖経済ではない。…それでもやはり、商品交換は制限されるべきだし、同じ選択をして生産力至上主義を放棄したパートナーとなる地域との間で、可能な限り行われるべきだ」(白水社新書「脱成長」119~20頁)。 「特に農業部門では、(化学肥料や工業的農業など)人工的な生産性を部分的に手放して」有機農業に変えれば、雇用者を増加させ、失業問題の解決にも役立つ(同104頁)。斎藤もいう。 「労働からの解放をめざして、これ以上生産力を挙げていくことは、地球環境に壊滅的な影響を及ぼすことになる」といって、「労働集約型の(ケア労働などの)エッセンシャル・ワークを重視」せよという。それは人の力に依存することが多く、「経済を減速」させることになるからだというのだ。あるいは、地域NGOが協同組合を作り、農具などを農民に貸し出し、有機栽培を行う教育を行う「南ア食糧主権運動」などのワーカーズ・コープ運動が挙げられている。 要するに地域の特質に応じた小規模な自給自足的な共同社会を作ることが理想だというのだ。 それは都会の生活に打ちのめされて絶望のあまり将来の展望を見いだせず、かつての農村の牧歌的生活をなつかしんだり、あるいは生活に困らないブルジョアや小ブルの小金持ちが、息抜きのために郊外での牧歌的な生活を語るようなものだ。 斎藤は左翼ぶってエコロジストを資本の廃絶を主張しないで、資本主義の規制にとどまっていると批判する。しかし、「脱成長」コミュニズム実現のための運動について述べる段になると、有機農業や化石燃料使用に反対する運動など市民主義的な運動、資本主義の下での消費・生産協同組合運動について語っているだけであって、資本の支配の克服を目指す労働者の階級闘争については論じていない。彼の「コミュニズム」は口先だけにすぎない。 ここにこそ、斎藤の小ブルジァ的な本性が示されている。 (T) |
|||||||||||||||||||