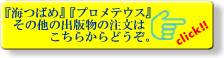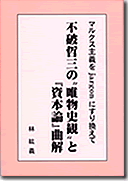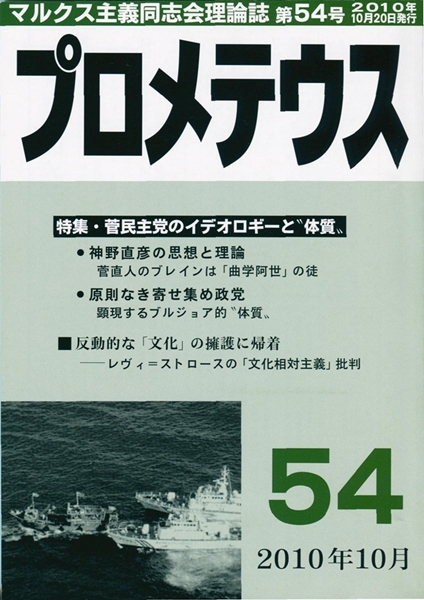|
||||||||||||||||||||
|
●1419号 2022年1月30日 【一面トップ】 資本の春闘方針を打ち破れ――経済成長の為と賃上げ許容に動く経団連 【1面サブ】 国・民と都民ファ合流の茶番劇 【コラム】飛耳長目 【二面トップ】 拡がる失望と反発――米バイデン政権発足1年 【二面サブ】 朝日新聞編集委員原真人の「脱炭素」の解説 「エコなバブル」を強調――既存電力資本の立場に配慮 ※『海つばめ』PDF版見本 【1面トップ】 資本の春闘方針を打ち破れ 22春闘の幕が開いた。今春闘に向けて、岸田政権が経営者団体に対して3%程度の賃上げを呼びかける中、経団連は春闘の基本方針を発表した。経団連は岸田政権の「新しい資本主義」に賛成するとして、賃上げ水準の改善を認めると言うが、それは何を意味するのか、また労働者は経営者らの賃上げ容認に対して、いかに考え、いかに闘うべきなのか。 ◇賃上げ容認は危機意識の現れ 経団連は去る18日(1月)、今春闘に対する基本方針を公表した。この内容は次の様であった。 コロナ禍で業績のばらつきが拡大している中、各社の実情に適した賃金決定を行うことが重要だと前置きした上で、「社会的な期待なども考慮を入れた検討」が望まれるとし、収益が拡大している企業の基本給については、「基本給を引き上げるベースアップの実施を含めた『新しい資本主義』の起動にふさわしい賃金引上げが望まれる」と言及。 また、収益の回復していない企業も「複数年度にわたる方向性を含めた検討を行うことも考えられる」、さらに中小企業の賃上げも重要だとして、大企業は取引価格の適正化を進めることで「賃上げを後押しする」ように述べた。 昨春闘の方針では、「基本給を引き上げるベースアップの実施は困難だ」と明記していたことに比べれば、大きな方針転換に見える。この新方針について、経団連の大橋徹二副会長(労働政策担当)は、「経営者の間でも全体として賃金水準を改善しなければいけないという危機感は強い。『持続可能な資本主義』ということを考えた時には、社会性の視座に立つことも大事だ」(NHK、1月18日)と、日本資本主義が先進国の中でも取り残されているという危機意識を露わにし、それを打破するために「賃上げ」を容認しなければならないと主張したのである。 ◇経団連の「千載一遇の機会」 要するに、経団連をはじめ経営者は、何よりもDX(デジタル変革)、つまりAIやIoTや半導体などの先端技術分野の「敗戦」から立ち直るためにと、賃上げや岸田の言う「人への投資」(『海つばめ』1418号参照)を行い、それらによって技術を持つ人材を確保しつつ賃上げによる個人消費拡大を期待するのである。 このように、賃上げと個人消費の拡大を先行させたいと願望する一方、十倉経団連会長は今がDXとGX(脱炭素社会変革)による変革期だからこそ、「国内投資を拡大し、賃上げの原資を生み出す企業の成長に繋げられる千載一遇の機会」だ、それが「ミソだ」(NHKの1月5日放送)と本音を語っている。 つまり、経団連にとっては、労働者の賃上げに配慮するが、何よりも世界に伍して闘える日本資本主義(共産党の志位がいう「強い経済」)の再構築こそが必要だと強調するのである。これを達成するためにと、経団連は国内投資や賃上げのための財政的支援(22年度政府予算案を見よ)を要求し、かつ賃上げが消費に回るための方策――「将来の暮らしの不安を解消するための社会保障制度の構築も急務であり、それが出来なければ成長は成し遂げられない」(十倉会長)――を注文するのである。 ◇賃上げと物価上昇の相互作用が好循環? 経団連の本音は別にしても、賃上げによる個人消費拡大と経済好転という理屈は、安倍政権が打ち出した「インフレ年2%」(物価上昇)による消費や投資の刺激策と同じものであり、どちらも、個人消費の拡大によって生産の拡大が進むというものである。 しかし資本主義は、私的資本が労働者の労働を搾取することによって、生き血を吸うドラキュラの如くに利潤を増大させる生産様式であり、この利潤追求こそが唯一の生産の動機や衝動なのである。それゆえに資本主義的生産は、利潤確保のためには、労働者の強力な闘いや労働者不足が深刻にでもならなければ、決して簡単に賃上げを認めないのである。資本主義は、資本と労働者が対立する社会であるがゆえに、共同体社会のような、人々の欲望や消費に牽引された生産活動にはなり得ないのである。 経団連は労働者の賃上げが必要だ、格差是正も必要だと言うが、くち先三寸に過ぎないのだ。仮に賃上げが進むなら、資本の利潤は小さくなり、投資は先細りになることを知っている。だから、資本は賃上げを認め、かつ利潤も確保するのなら、賃上げ以上の価格を商品に転嫁せざるを得ない。しかし、それは名目GDPを増やすのが関の山であり、労働者の実質賃金は変わらず、資本による搾取率も変わらず、従って実質的な資本価値の増大もない。こんな循環が仮に成立したとしても、一時であるに過ぎず、資本主義の本性とは違い長続きすることはないのだ。 ◇御用組合幹部や共産党も同じ穴のムジナ 賃上げによる景気回復という経団連やMMT派や岸田らの理屈は、あまりにもお粗末で話にならないが、これは、経団連や政府だけではなく、連合や全労連という労働組合に巣食う御用幹部たちの、また共産党らの春闘に対する態度でもある。 長い間、労組の御用幹部共や共産党は、大幅賃上げで不況脱出や経済回復を叫び、さらには地域経済の活性化を実現するかに幻想を振りまいてきた。彼らは資本主義経済の不況脱出に協力するのであり、実際に経済回復に片棒を担ぎ協力してきたのだ。そして、彼らは労働者の資本との闘いを経済回復の枠内に導き、逸らせ、資本との協調を促し、労働者の賃金闘争をぶち壊してきたのである。 さらに、リベラルマスコミの雄である「朝日」もまた、「賃上げで経済を支えよ」(1月20日)との社説を掲げている。今後の物価上昇を考慮するなら「家計への悪影響を防いで消費を支える」ために、企業はしっかりと賃上げし、消費不況からの脱出を図れと宣うのである。 しかし、労働者は消費の不足を改善するために、または景気回復を図って資本の利潤を増やし、そのおこぼれを頂戴するために賃上げ闘争を行うのではない。労働者の賃金闘争は、生活を支えるための闘いではあるが、しかし同時に、搾取の廃絶をめざす労働者の政治的理論的闘いと結合していく必然性を内に秘めているのである。 (W) 【1面サブ】 国・民と都民ファ合流の茶番劇 国民民主の玉木代表は今月12日、支援団体である連合の本部を訪れ、今夏の参院選に向けて、東京の地域政党である「都民ファーストの会」と統一候補を擁立する考えを芳野会長に伝え、13日には記者会見で都民ファとの選挙協力の連携を強めることを表明した。20日には都民ファとの合流に向けた1回目の協議を行っているが、すでに昨年12月15日に都民ファの特別顧問を務める小池都知事と玉木は都庁で会談し、合同で勉強会を開くことに合意していた。 玉木は、17年総選挙の際、小池が立ち上げた「希望の党」に、支持率低迷の民進党から合流してきたが、小池が「排除の論理」で安保法制を容認する政策協定への署名を要求したことに対して、安保法案を「戦争法案」と呼んで反対していたにもかかわらず、「署名」の踏み絵を踏んだ人間である。 希望の党は「排除」発言で失速し、総選挙ではモリカケで窮地にあった安倍自民を圧勝させ、小池は11月に代表を辞任。その後釜になったのが玉木であった。 12月17日に都内で国民民主議員と都民ファの都議計30人を集めた合同勉強会が行われたが、21年度補正予算、特に「10万の現金給付が認められる基準について」や「マイナポイント第2弾など行政のデジタル化」、オミクロン株の水際対策についての省庁からのヒアリングなどの内容だったという。 都民ファは昨年の衆院選直前の10月3日に、国政進出に向けて急きょ新党「ファーストの会」を立ち上げながら、公示前の10月15日に立候補を見送った。自民がガタガタと岸田を新総裁に仕立て総選挙に臨もうとしていた矢先であり、国政への進出を狙って都民ファが策動したわけだが、「異例ともいえる戦後最短の日程で公示日が早まったことなど」(ファーストの会HPより)で、「次の国政選挙にむけて取り組」む(同前)こととなり、その狙いは持ち越されていた。 一方の玉木は芳野会長に、「都議がいない国民民主と、国会議員がいない都民ファの利害が一致している」と説明したという(1・13朝日)。参院選東京選挙区(改選数6)での議席獲得を狙うだけでなく、大票田の東京での比例代表の得票数上積みの算盤を弾いているのである。 連合は維新との過度な接近に慎重な立場であり、芳野会長は20日の会見で「労働法制をはじめ考え方が違う」との見方を崩さなかった(1・21産経)と報道されている。口先では「党が決めることで、基本的に口をはさむことではない」(同前)と言いつつ、国民民主の動きを注視している。 国民民主では前原誠司が選対委員長に就任しており、「今一番大事にすべきなのは維新との協力」で、「優先順位は間違えない方がいい」(1・14産経)と主張しており、玉木と足並みの違いはあるが、自民に次ぐ第2の保守勢力を作ろうとしている点で違いがないことは明らかである(勉強会の内容を見よ。ブルジョア政権を補完するためのものであって、問題の本質を隠し、本当の解決を困難にするものだ)。 労働者はブルジョア政権を補完するような動きを支持できるものでない。労働者はブルジョア的な政治から自立して階級的な利益のために団結を固めて闘うことで、歴史を切り拓いていく。 (岩) 【飛耳長目】 ★オミクロン株が猛威を振るっている。重症化率が低いとは言え、その感染力は爆発的だ。岸田は「水際対策を徹底する」として外国人の訪日を禁止したが、落とし穴があった。在留米軍から感染が始り、その周辺に拡大していくとは思ってもみなかったことだろう★国内には米軍専用基地が81(自衛隊と併用では130)ヶ所あるが、被害が甚大だったのは沖縄県と山口県で、それぞれ嘉手納基地や岩国基地がある。未曾有の感染に県民の怒りは収まらない★立憲や共産党は盛んに日米地位協定の改定を要求している。米軍関係者は「外国人の登録及び管理に関する日本の法令の適用から除外される」条項の「管理」に検疫も含まれるとし、その改正を要求。だが地位協定の改定で済む問題か★かつて沖縄は本土防衛と称し、その実、軍部と癒着した財閥や支配階級の為の天皇制(国体)維持の捨て石とされ、20万人もの犠牲者を出した(沖縄戦全記録NHK参照)。沖縄の基地化はその継承である★130もの軍事基地が日米の大資本と支配階級の、強いては日米資本主義の防衛の為のものであり、決して「国民の命と暮らしを守る」ものでないことは、沖縄や310万人の命を奪ったあの戦争が教えている。我々は、一切の軍事同盟の破棄を労働者の国際連帯と共に要求する。 (義) 【2面トップ】 拡がる失望と反発 共和党トランプ政権に代わって、人種差別反対、「中間層」の復興を掲げた民主党バイデン政権が発足して1年が経過した。しかし、なおトランプの影響は根強く、物価騰貴などをめぐって、有権者の政府への失望と反発は広がりつつあり、今年11月の中間選挙を控え、バイデン政権は大きな困難に直面している。 ◇「より良い再建」法案の後退 困難を象徴するのは、新型コロナ対策、子育て支援、気候変動対策を盛り込んだ法案が与党民主党内紛で大幅な削減を余儀なくされたことである。 「より良い再建」(ビルト・バック・ベター)と名付けられた歳出法案は、新型コロナ対策、インフラ投資法と合わせ、教育・子育て支援、低所得者向け政策を含み、当初総額3兆5000億ドル(約400兆円)規模で、昨年中成立の見込みであった。ところが半分の1兆7500億ドルへと削減したにもかかわらず、民主党のたった一人の議員の反対で成立の見通しが立たたず、年を越した。 議会の勢力は、下院は民主党が221人、共和党が213人とわずかに上回っているものの上院では50対50と同数である。賛否が同数の場合、ハリス副大統領の賛否で決定される仕組みになっている。このため歳出法案成立を急いだバイデン政権は、歳出規模を半減し、法案成立を狙った。 削減された中には高齢者用処方箋の薬価引き下げ、介護休暇などの有給保障、コミュニティカレッジの学費無償化、財源としては法人税の引き上げ、富裕者の増税が含まれていた。 法案には、民主党内でもサンダース派らの議員は社会福祉投資法案とセットでなければインフラ投資法案に賛成できないとの態度をとっていたが、バイデンは法人や富裕者への増税をとりさげることによって野党共和党議員の取り込みを策し、法案成立を目指したのである。こうして法案は昨年11月、下院で可決された。 しかし、上院では、ウェストバージニア州の民主党マンチン上院議員の「反対」表明で、法案は暗礁に乗り上げた状態になっている。もともとマンチン議員は、自ら「中道保守」と名乗り、財政拡大や増税を嫌う共和党に近い。ウェストバージニア州は石炭産業で栄えた地域であり、かつては民主党を支持する州であったが、石炭産業の斜陽化とともに共和党トランプ支持に替わった。マンチン議員も、石油、ガス、石炭などエネルギー業界からの献金が上院議員でトップを占め、共和党寄りの議員である。 マンチン議員の「反対」で看板の歳出法案実現の見通しは現在立たず、バイデン政権は窮地に立たされている。 ◇格差拡大、物価上昇で労働者の生活圧迫 バイデン政権発足以降、米国経済は巨額の財政支出によって新型コロナウィルスの被害から比較的短期間に立ち直ったかに見えた。 株価は、バイデンが打ち出した1兆9000億ドル(約220兆円)規模の経済対策や中央銀行にあたる連邦準備制度理事会の大規模な金融緩和によって上昇を続けた。 コロナワクチンの普及によって、経済活動は回復の兆しを見せ、ダウ平均株価は一時3万6000ドルを突破、バイデン政権発足から1年間で14%も値上がりした。 雇用数も急速に回復、失業率は昨年末には3・9%と、新型コロナ禍直前の20年2月以来2年弱ぶりに3%台に低下した。政府は「コロナの流行に直面しているが、労働市場は力強く回復した」と強調した。 しかし、物価上昇率は昨年1月の1・4%から上昇一途。昨年12月の消費者物価指数は前年比7・0%と11月の6・8%からさらに進んで、1982年6月以来(7・1%)39年6カ月ぶりの高水準に達した。 物価上昇はガソリン・電気・ガスをはじめ、食品から家賃に至るまで幅広い項目におよび国民の生活を直撃している。 物価上昇の原因の背景は、一つはコロナ禍による生産の縮小、輸送困難によるものであり、ガソリン価格の上昇率は11月から8・5ポイント鈍化したものの49・6%となお高い水準にとどまり、値上がりが続く食品も6・3%上昇、物価騰貴を受けて家主が引き上げている家賃などの住居費は4・1%高くなった。世論調査でも物価騰貴は「深刻」との答えは8割を越えた。 記録的な物価騰貴が困窮者の生活を直撃する一方、富裕階級は株式など資産を増加させている。例えば電気自動車(EV)テスラのイーロン・マスク最高経営責任者は、1年間で株価高騰によって資産を約7割増やしたと言われる。 コロナ禍の1年半で、上位1%の富裕階級の資産は約31兆ドル(約3500兆円)から約44兆ドルに増加した。これは資産全体の3割を占める。 資産増加は、バイデン政府が気候変動対策やコロナ禍対策として多くのカネを散布した結果である。国家の巨額の財政支出は、経済活動が停滞しているにもかかわらず、ハイテク株を中心に記録的な株価上昇をもたらした。株価上昇といっても、利益を得たのはごく一部の富裕階級であり、彼らは「持たざる者」の苦境をよそに資産を増加させたのである。 ◇再構築される軍事同盟 対外政策としては、バイデンは外国からの輸入規制等による産業保護、TPP不参加など貿易面ではトランプの自国第一主義の継承している。その一方では、最大の「競争相手」中国への包囲網の構築を行ってきた。 インド洋、南シナ海への中国の進出への対抗策としての米・豪・英の新安保体制としてのオーカス(AUKUS)、「専制主義国家」への対抗策としての「民主主義」国家を集めた世界会議の開催などはその表れである。 バイデンのこうした一連の政策は、経済的、軍事的にも米国一国では対抗しえなくなった米国の弱体化の結果であり、バイデンは新たな軍事同盟・協力関係を構築することによって、世界の盟主としての地位を維持しようとしているのである。 こうした状況の下で、中国に隣接した経済大国=日本にも大きな期待がよせられている。日本の軍事力の一層の強化、日米同盟の強化がそれであり、岸田政権も経済安全保障のための2プラス2の会議の新設、日・米・豪・印4カ国の会議(Quad)開催合意、敵基地攻撃の検討、軍事費の増加など積極的に同盟強化に応じようとしている。 ◇拡がり、深まる社会の矛盾 バイデンが大統領に就任してから1年、発足当初55・8%であった支持率は、1月20日時点では40・5%と不支持率(55・3%)を大きく下回る。それは低所得者の生活支援、「格差」是正、コロナ禍の克服と景気回復を訴え政権を獲得したバイデンへの失望の表れである。 ワクチンの接種は進まず、世界最多数の感染者を出し続けている。物価上昇の下で貧しい者と裕福な者との社会的〝分断〟は克服されるどころか、一層拡大した。 バイデン政権は、「労働に報いるパラダイムシフト(枠組みの転換)」、衰退した経済再建・強化を訴え、賃金引上げ、生活困窮家庭への支援、温室効果ガス削減のための大型投資による雇用拡大を訴え大規模な財政出動と金融緩和を行った。 しかし、〝自由競争〟、〝自己責任〟を謳うトランプの新自由主義による「小さな政府」から、バイデンの国家の支援を謳う「大きな政府」への転換を、国民生活を重視する政治として評価することは出来ない。 バイデンの生活困窮者支援策は、資本の支配の下で貧しい生活を余儀なくされている状況を打開していくためのものではなく、困難を緩和する一時的、部分的なものでしかない。バイデンの「大きな政府」は、労働大衆の資本に対する不信や不満をわずかな〝改良〟で緩和し、資本の支配の安定・強化を目指すためなのである。 バイデンにとって、後退した米資本主義を〝再建〟し、強化することが課題であり、国民生活の安定、向上もそれに依存しているのであり、そのための「大きな政府」なのである。 しかし、バイデンの「大きな政府」は物価上昇、格差拡大など矛盾を拡大、深化させていることを見過ごしてはならない。 (T) 【二面サブ】 朝日新聞編集委員原真人の「脱炭素」の解説 朝日新聞編集委員の原真人が「脱炭素の原動力 欧米の金融界が描く、エコなバブル」という解説記事を書いている(同紙1月17日付)。彼はこの中で、COP26での「1・5℃目標」決定の推進力となったのは各国が「国益を超えた地球益にめざめた」からでも「グレタ・トゥンベリさんらの努力が実った」からでもなく「欧米の金融パワー」であるとして、「ネットゼロのためのグラスゴー金融同盟」(GFANZ)について書いている。 GFANZは、カナダ銀行総裁、イングランド銀行総裁を歴任したマーク・カーニー(現国連気候変動問題担当特使、COP26では金融顧問を務める)らが中心になって昨年4月に作られ、「45カ国から銀行や保険会社、資産運用会社など450機関が参加。世界中の投資資金を脱炭素に集中させるための運動を進めよう」というものである。日本からも主だった銀行や生保会社、投資会社等が参加している。総資産は130兆ドル(約1京4800兆円)にもなり、2050年ネットゼロ目標達成に必要と見積もられている資金100兆ドルの大半を融通するものと見られているというのだ。 その背景になったのは、「08年に起きた世界金融危機の後、主要各国は超金融緩和と大規模な財政出動を繰り返してきたが、以前のような成長軌道には戻れなかった。そこで世界経済を押し上げる新たな需要、新たな投資機会を求める声が高まり、浮上したのがグリーン(環境にやさしい)投資だった」と原氏は言う。 確かに、脱炭素を押し進めていくには巨額のカネが必要であり、誘導政策的な政府支出を別とすれば、その資金を調達できるのは金融機関しかないのだから、金融危機以後有力な投資先を探しあぐねていた世界の金融機関にすれば渡りに船であったことは確かであろう。そのことは欧米各国の政策当局にとっても同様で「グリーン・ニューディール」とか「グリーン・リカバリー」とか言われていること一つとっても明らかである。 原氏は、こうした金融界の動きを一種の「バブル(エコなバブル)」として非難する一方、COP26の「1・5℃目標」については過激で性急過ぎる目標であるかのように書いている。例えば、今般の石油価格の上昇についても、化石燃料産業に対する投資の減退も関連している、今後GFANZのような活動が性急に進められればそうした混乱が避けられず、「インフラ切り替え期に安定したエネルギー供給」が不可能になってしまうなどと言っているのだ。 しかし、こうした立場は、COP26終了直後に電気事業連合会会長の池内弘(九電社長)が「火力発電への投資を急にやめれば電力の安定供給ができなくなる」「ブラックアウトや計画停電を招く」等と言っていたのと同じである。諸資本の競争を基本とする資本主義である限り、政府のよほどの計画的介入がない限りそうした齟齬が起こってくるのはある程度避けられないだろう。しかし、「1・5℃目標」が過激すぎるとか、技術的に不可能だとか言うのは既存電力資本や既得権者の論理でしかない。 原氏は電気の値上がりやガソリン高騰は「所得の低い人ほど打撃が大きい」などと国民や弱者に寄り添うかのような言い方をしているのであるがそれを徹底できず、実際には再エネ化をできるだけ遅らせたい既存エネルギー資本やその意を受けた政府の立場に接近しているのだ。 (長野、YS) |
|||||||||||||||||||