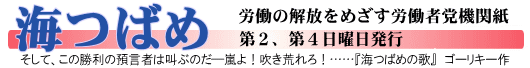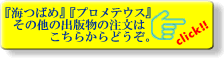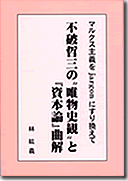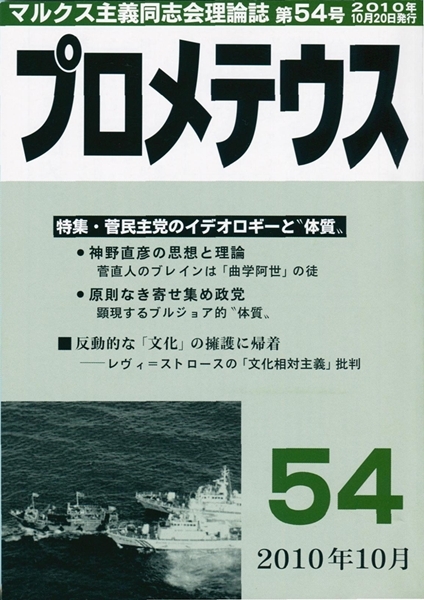●1454号 2023年7月9日
【一面トップ】 加速する共産党の衰退
――鈴木らの異議申し立ては党退廃を象徴
【コラム】 飛耳長目
【二面トップ】 円安再加速に苦渋する政府
――円安もインフレも現象で捉える蒙昧な政府・日銀
【二面サブ】 オオカミ少年のごときJアラート
――なりふり構わず沖縄諸島ミサイル部隊配備
※『海つばめ』PDF版見本
【1面トップ】
加速する共産党の衰退
鈴木らの異議申し立ては党退廃を象徴
共産党の衰退が止まらない。一昨年の衆院選と昨年の参院選で議席を減らし、今年4月の統一地方選では全国で135の議席を失う大敗を喫した。こうした中、開かれた中央委員会総会は、選挙の総括を行ったが、それは共産党が労働大衆から遊離し、信頼をますます失っている原因から目をそらせた開き直りともいえる志位指導部の政策を正当化する言い訳に終わっている。
◇連敗続く選挙と党員、機関紙購読者の減少
まず、共産党の衰退の状況を見よう。21年10月の衆院選では10議席と2議席減らし、22年7月の参院選では4議席と2議席減らした。比例区の得票数は19年の448万票から361万票へと大きく減少した。
これに続く今年4月の統一地方選では、選挙前に有していた議席を全体で135議席減らし、議席占有率は前回の8・08%から7・28%に後退。
党勢の衰退も著しい。党員数は1990年の50万人から2020年には27万人と半分ちかくに減少。党活動の主な収入源である機関紙「赤旗」は1980年に355万部だったが、3分の1以下の90万部にまで減少した。
◇「政治対決の弁証法」の詭弁
4月に行われた統一地方選の大敗について、6月に開催された第8回中央委員会総会は、「共産党の封じ込めをはかる大逆流との生きた攻防のプロセスの中でとらえる」ことが大切だと総括した。そしてこうした総括の視点は、「政治対決の弁証法」と呼ぶことができ、「共和制」を実現した1848年2月革命から、支配階級の反撃によって共和制が崩壊し、階級闘争が下降線をたどる50年10月までの状況を分析したマルクスの『フランスにおける階級闘争』で明らかにしたことだと言うのだ。志位は次のように言う。
「マルクスは、革命というものは『結束した強力な反革命』を生み出すこと、それとたたかうことによって革命勢力が『ほんとうの革命党』に成長しすることを強調しました。弁証法というのはなによりも発展の科学だということを強調したいと思います」。
つまり、21年の総選挙で共産党が市民と野党との共闘体制をつくり上げ、自民党政府に正面から対決し、重要な成果をあげ、「支配勢力を恐怖に陥れるまで攻め込んだ」。これに対して、自民党ら支配勢力は反撃に移り、「反共攻撃」が強められ、野党共闘が進められなくなった、また、共産党100年創立に絡めて、共産党は「閉鎖的」「非民主的」など、メディアから大々的なキャンペーンが展開された。選挙での党の後退は支配勢力の攻撃が強まった結果であって、それを打ち破っていくことこそ共産党が革命政党として発展していくことが出来ると言うのだ。
しかし、志位の言う「政治対決の弁証法」とは本当にマルクスと同じだろうか。
『フランスの階級闘争』の序文でエンゲルスは次のように書いている。
「奇襲の時代、無自覚な大衆の先頭にたった自覚した少数者が遂行した革命の時代は過ぎ去った。社会の完全な改革ということになれば、大衆自身がその改革に加わり、彼ら自身が、なにが問題になっているか、なんのために彼らは肉体と生命をささげて行動するのかを、すでに自覚していなければならない。このことこそ、最近50年の歴史はわれわれにおしえてくれたのだ。だが大衆はなにをなすべきかを理解するため、──そのためには、長い間の根気づよい仕事が必要である」(国民文庫、23頁)。
2月革命を成し遂げたのは革命的な労働者ではなかった。労働者はまだ未成熟で、階級的な自覚に欠け、労働者の窮乏は競争にあるとして「国民作業所」を設けるなどで解決するとしたルイ・ブランらの小ブルジョア社会主義の影響下にあった。資本の体制のもとで「国民作業所」で労働者の窮乏を解決できるかのようなブランの計画は破綻し、労働者はブルジョアジーの反撃の前に敗北した。
マルクスが『フランスの階級闘争』で明らかにしたのは、支配階級の反撃が強まり、労働者の革命党がそれに反撃できなかったから敗北したということではなくて、労働者がまだ未成熟で、その運動は観念的な社会主義者の影響下にあったこと、労働者が資本の軛(くびき)から解放されるためには、資本主義的生産を根底から変革しなくてはならないこと、そのためには労働者の革命的権力を樹立し、生産手段を社会の手に移す必要があること、こうした労働者の階級的な闘いを推し進めていくために、労働者の階級的団結を促す革命的組織による粘り強い働きかけが必要だということである。
階級闘争が発展すれば、支配階級の攻撃が激しくなること、そしてそれと闘うことによって革命政党が成長するなどということは、マルクスを持ち出さなくてもわかることである。だが、志位はこんなことをマルクスが『フランスの階級闘争』で明らかにした「政治対決の弁証法」などと呼び、これを学ぶ必要があると党員に説教しているのである。
志位がインチキな「政治対決の弁証法」を唱える意図は、共産党の敗北の本当の原因を覆い隠そうとすることにある。
◇共産党の後退の原因
共産党が選挙で敗北を重ね後退したのは、共産主義の党を名乗りながら労働者の階級的な立場に立つことなく、ブルジョアジーや小ブルジァーに迎合してきたためである。
共産党は共産主義を掲げてはいるが、それは遠い将来のことであって、当面の課題は生活の安定・改善、平和な日本のために資本主義の「民主的な改革」を目指して闘うことであるとして、市民主義者や立・憲など野党との共闘で自民党政府に替わる連合政権を樹立することだとしてきた。そして選挙では、社会保障・福祉めぐって自民党と予算のバラマキ合戦を繰り返してきた。
また、自衛隊について、2000年の党大会で、解消を目指すが、急迫不正の主権侵害、大規模災害などで必要の場合には自衛隊を利用すると、「自衛隊の利用」論を打ち出した。さらに進んで22年5月、朝日新聞のインタビューに答えて、志位は共産党が参加する政権の下では、自衛隊は「合憲的な存在」であると言い切った。
志位は共産党の選挙での敗北について、自民党をはじめする資本の勢力の攻撃が強まったためであるかに言うが、それは、志位の言うような支配階級の攻撃のためというよりは、労働者の階級的な立場を放棄し、ブルジョアや小ブルジョアに媚びた日和見主義、改良主義のためである。共産党は労働者の不信を買う一方、党員の中からも積極的に活動する気にならないという消極性を拡大してきたのである。
政策は正しいが、支配勢力の「反共攻撃」を跳ね返すための「地力」がなかったために後退した、したがって、攻撃を跳ね返して行ける党を建設していかなくてはならない、として提起しているのは、「130%の党」づくりである。「前回時比で党員91%、日刊読者87%、日曜版読者85%でたたかったことが、議席後退の最大の要因になった」として、党員、赤旗読者を増やし、活動を活発にすることが課題だと言うのだ。
こうして、党の後退してきた原因は党員のやる気の問題にすり替えられ、志位らの「党勢回復」の掛け声は空回りするだけである。
◇共産党頽廃の落とし子、鈴木元
地方選を前にして、今年1月、3月、共産党は、現在の党は「異論を許さない閉鎖的」だとして批判し、委員長公選制を訴える著作を出版した鈴木元、松竹伸幸の2人の古参党員を除名した。松竹は党の中央委員会に勤務、政策委員会・安保外交部長を務めた党員であり、鈴木は京都府委員会常任委員として、京都府での党活動や平和団体はじめ様々な団体で中心的活動を担ってきた党員である。
2人に共通する立場は、共産党の綱領は現実からかけ離れており、現実に適合した政党に生まれ変わらなくては、衰退の一途をたどるばかりだということである。
鈴木の主な主張は以下のとおりである。
共産党は綱領に共産主義を掲げているが、それは200年、300年後のことであり、現実の世界において政治闘争を行い、改革を提起する政党の目標にならない、(『志位和夫委員長への手紙』かもがわ出版、138頁)、まずは「北欧型福祉国家」プラス「南欧型協同組合運動」を追求すべきである(同202頁)、したがって共産党という党名も「革新共同党」などに改名する方がよい(同225頁)。
共産党は統一戦線で団結し、国民の多数の支持を得ながら一歩一歩社会を変える方針をとっている、そうすると多くの進歩的革新を願う人々と共通項を見出し、いかに統一を実現していくかを模索していかなくてはならない(同230頁)。運動は「資本と労働」という関係にこだわりすぎず、国や自治体への要求運動・市民運動をもっと重視すべき(同220頁)。
安全保障政策については、政権に就こうとする限り「安保容認・米軍の出動要請、自衛隊合憲・活用の立場」に立たざるを得ない(同50頁)。
共産党は鈴木らの主張は党を解体に導くと激しく非難している。しかし、現在の課題は「大資本偏重、米国従属」の「二つの歪み」を正し、国民生活重視・改善のために「資本主義の民主的改革」だとし、社会主義については将来の国民の選択の問題とする共産党の改良主義的な退廃の進化が鈴木らを生み出したのだ。
社民化の道を選んだ西欧の共産党の後追いでしかない鈴木らは、志位共産党のブルジョア的頽廃の落とし子である。
◇資本の搾取克服をめざす労働者の
階級政党こそ発展させよう
共産党の現状は、共産党に頼っていては資本の搾取からの解放をめざす労働者の闘いは前進しないということを明らかにしている。共産党は社会主義を将来の国民の選択の問題に棚上げし、資本主義の「民主的な改革改良」に捻じ曲げ労働者の階級闘争を解体してきた。
資本主義の改良ではなく、資本の支配の根本から変革し、搾取からの解放を目指す労働者の革命政党の建設とその闘いの発展こそ、労働者の課題である。 (T)
【飛耳長目】
★大坂の陣で名を馳せた真田幸村は、豊臣方の家臣ではなかった。現代風に言えば傭兵であり、六文銭の旗印で戦った幸村の軍勢はワグネルということになる★冬の陣で豊臣方は、秀吉が残した金銀を軍資金に、関ヶ原の戦いで没落した武士や、カネ目当ての浪人を多数集め、9万の軍勢で20万の徳川幕府軍を苦しめた。負けはしたが、取り潰しは免れた★用済みの傭兵は放り出される運命だった。だが、戦乱こそ稼ぎの場と心得る輩は居座り、講和条件にない内堀まで埋められたことへの家臣の怒りを煽り立て、夏の陣へと突き進み、豊臣氏は滅んだ★政略婚や人質交換、陰謀や謀反が当たり前の、血生臭い戦乱の時代は終焉に向かう。歴史は進んで二つの世界大戦と東西冷戦を教訓ともして、人類の存亡に関わる地球規模の難問に対処すべき時代にあって、古めかしい汎スラブ主義を旗印にする「プーチンの戦争」は、歴史書にいかに刻まれるべきだろうか★そこにヒョイと「プリゴジンの乱」が〝傾奇者(かぶきもの)〟として登場した。辞書曰く「ことさら人目につくように常軌を逸した風俗・精神・言動をとる者を言う。関ヶ原の戦いから大坂夏の陣前後の時期には特に多くの傾奇者が横行した」★労働者階級の旗印は、階級国家の止揚と一切の軍備の廃棄である。 (Y)
【2面トップ】
円安再加速に苦渋する政府
円安もインフレも現象で捉える
蒙昧な政府・日銀
昨年秋、日銀は為替介入し剛腕で円高に誘導した。その後、米政府の金利引上げも1年以内に終息に向かうという見通しの下、円相場は好転するかに言ってきた。しかし、円安の流れが再び強まっている。何が起きているのか。
◇円安が小康状態の理由
昨年の9月と10月、財務省は日銀に指示して、為替市場に単独介入した。
日銀は1ドル=145円台半ばになった為替相場を円高に戻すために介入し(9月)、2・8兆円規模のドル売り円買いを行った。翌月の10月にはさらに同規模の介入を行い、その後、為替相場は今年の5月末まで1ドル120円台から130円台を推移していた。
円相場が140円台へと動き出したのは6月に入ってからである。
植田が日銀新総裁になった後も超低金利政策は維持され、欧米との金利差は拡大し、貿易収支の赤字もずっと続いていたことを考えると、もっと円安が進んでもおかしくはなかった。だが、円安が一気に進まない要因があった。
その一つは、3月に相次いで起きた米国銀行の経営破綻である――物価高騰を抑えるために政策金利を引上げてきたことを〝引き金〟に発生した(『海つばめ』1448号参照)。
二つ目の要因は、政策金利の引上げによって、不動産の貸付ローンや使用料が上がったため、ビルテナントに入っていた営業所や店舗などが相次いで撤退し、商業用不動産は破綻の危機に陥っているからだ。しかも、多くの中小銀行が商業用不動産に融資していて、今後、銀行の中には大きな損失を被るところもあると言われている。
こうした銀行の相次ぐ破綻や商業用不動産の危機によって、米国への投資は減退し(米国の金融機関や中小企業の株価が下落)、投資家のカネはEUや日本の株式市場等へ流れた。円為替は大して下落せず〝小康状態〟が保たれていたのである。
◇再び円安が急進
ところが、再び円安が進みだした。
それは、米FRBが6月の金融政策会合にて、政策金利引上げを見送り、現在の5%~5・25%の金利幅を維持することを決めたが、他方で、年内に2回の利上げを行うことを明らかにしたからだ。
政策金利引上げを見送った理由について、FRBのパウエル議長は「金融不安がもたらす影響をわれわれは完全には分かっていない」からだと述べ、「米国経済は未だに金利引上げによって引き起こされた信用不安」の渦中にあることを吐露した。
FRBが政策金利引上げを見送ったのは、物価高騰が沈静化する見通しを描いたからではなく、信用不安の波及を避けようとするためであった。だからパウエルは「物価目標の2%までの道のりは遠い」と述べ、年内にさらに利上げを行う可能性を強調したのである。
つまり、FRBが予想していた年内の「インフレ低下」は外れた。
この米国政府の予想について、日本政府も共有していたから、植田も岸田もかなりショックであったろう。なぜなら、昨年の秋にやったような国家による為替介入という〝中国並みの反自由主義〟を再び断行することになるかも知れないからだ。
◇動揺する政府日銀
6月初めから再び進み出した円安は、先に紹介した米国(欧州も)の信用不安にも拘わらず、日米や日EU間の金利差を利用した円売り、ドル・ユーロ買いが進んでいることや一向に改善しない日本の貿易収支の巨額の赤字を反映している。
さる6月30日、財務相の鈴木が記者会見で、6月に入って円安が再加速し、1ドル=145円の相場になったことを踏まえて、さらに円安が進むなら為替介入を辞さないとほのめかした。
だが、政府・日銀が為替介入をしても、一時的な円安防止にしかならず、また、日銀が所有する外貨準備も限りがあり、永続できるものではない。為替介入は、円安を抜本的に止めることができない故に、国家の権力に頼るのであり、それは政府・日銀の弱さの現れである。
日銀は鈴木の緊急会見に先立って、6月の15、16日に、植田新総裁のもとで2度目となる「金融政策決定会合」を開いた。この会合で参加委員から相次いで、物価上昇率が今までの見通しよりも「上振れる可能性がある」、「物価上昇の持続性を過小評価している可能性がある」と発言があったようだ。
希望的観測で物価上昇率を低く見積もるのだから、ブルジョアから見ても役立たずだが、希望的観測を出し続けるのは金利を簡単に引き上げられない理由がある。
本紙の1453号でも述べたように、物価高騰を鎮めようと金利引上げを図るなら、政府の歳出予算の「国債費」は増加する、その上、日銀が大量に保有する国債価格は下落し、日銀資産の「含み損」はさらに増え日銀信用に傷が付くからだ。
◇「価値法則」は貫徹する
ここで円安を理解するために為替相場について具体的に見ていく。
外国為替市場は、今日では、外国との貿易における輸出入の代金決済(多くが後払い)を行う場であるが、派生商品である金融商品の売買や外貨との両替(両替は歴史的には古い)を行う場になっている。これらの決済や両替を仲介するのは銀行であり、それゆえに銀行は為替取引の中心的な役割を担う。
この市場で形成される為替相場は、国家間に分裂した各国政府の貨幣の交換比率(本質的には、商品の価値を尺度する貨幣の交換比率)である。
しかし、外国貨幣との交換・売買という面だけを見るなら、貨幣に対する需要と供給によって相場が形成されるように見える。例えば、ドルの需要が高まり円を売るならば、ドル高円安の相場となるように。
それゆえ、貨幣資本(家)は為替変動を利用して為替差益を得るが、商品を輸出する企業もまた、貨幣の交換と同様な為替差益を得るように見える。かつて、安倍や黒田らリフレ派はこのように考えて恣意的に金利を引き下げ円安策動に精を出した。
だが実際には、為替変動があっても商品交換における「価値法則」は貫徹しているのである――仮に、1ドル=100円の為替相場の時に米国へ商品を輸出し、その後円安が進み1ドル=125円になった場合、輸出した100円の商品は米国で0・8ドルと表示される。この表示価格で商品が売られ、後日0・8ドルの為替手形が日本に入ってくれば100円と交換される。
要するに、為替相場が変動するなら円とドルの交換比率は名目的に変動するのであり、輸出した商品の価値は何ら変わらない。上記の場合、輸出した商品は米国でより多く売れるだろうが、輸入原材料を使っているなら円安で相殺されてしまう。
他方、米国でインフレが発生し、ドルの価格標準が下がる(「ドル価値」が下落)場合にはどうなるか。
上記と同じ為替相場にて100円の商品を米国に輸出した後に、米国でインフレが進みドルの価格標準が半分に下落するなら、日本から輸出した100円の商品は2ドルで売られる。そして、後日この2ドルの為替手形が日本に入ってくれば100円と交換される。
米国のインフレ発生によって、ドルは名目的に下落しただけで、商品を生産した労働時間は変わらず、従って商品の価値は変化していない。
◇味噌も糞も一緒にする
ブルジョアは商品価格について、商品価値の貨幣表現であることさえ知らず、単なる記号ぐらいにしか認識しない。
それゆえ、為替変動があっても商品価値は変わらないことに気付かない。
インフレについても、過剰発行された紙幣や紙幣化しつつある円やドル(信用貨幣)が流通過程で価格標準を切り下げて過剰発行を解消する動きであることを知らない。
日銀の黒田や植田はもちろん、大学で高給を得て優雅に暮らすケインズ学者も皆、インフレを供給過小(需要過多)から発生する物価上昇のことだと説明する。つまり、インフレは需要供給による価格変動の一側面だと言うのである。
第一次大戦直後のドイツは、敗戦による賠償金を英仏らから科せられて金が枯渇し、止む無く金と兌換の無い国家紙幣を大量に発行した。その結果、インフレが爆発し、あらゆる商品の価格が1兆倍も上昇した。
このドイツのインフレについても学者共は需要供給で説明するのである。
味噌も糞も一緒にする経済学に呪いあれ!
新左翼急進派が崇めた宇野弘藏もまた、価値と価格を科学的に区別できない典型的な俗流学者であった。
宇野は需要供給による価格変動の平均値が価値だと言った。労働による価値の規定に反対してマルクスに対抗した宇野学派が労働価値説から離れていったのは必然であった。 (W)
【二面サブ】
オオカミ少年のごときJアラート
なりふり構わず沖縄諸島ミサイル部隊配備
◇北朝鮮のロケットでミサイル騒ぎ
2月に、北朝鮮が「軍事偵察衛星」を打ち上げると発表した。それは、米韓軍事演習を繰り返すアメリカに対抗してのものであるが、日本の岸田政権(防衛省)がそれに直ちに反応して、それは「ミサイル」の発射だと強弁して、その「破壊処置命令」を下した。
そして、ロケットの発射コース下にある沖縄諸島に自衛隊の地対空ミサイル部隊(PAC3)を大騒ぎして配備した。防衛省は、あたかも「弾頭」を搭載したミサイルが発射されるかのごとく騒ぎながら、他方では、小声で、部品などの落下に備えてのミサイル配備だと滑稽にも二枚舌でつぶやいた。
5月31日の衛星ロケット打ち上げ直後にJアラートが稼働されると、テレビやラジオの通常放送は中断され、「ミサイル発射。ミサイル発射。北朝鮮からミサイルが発射されたものとみられます。建物の中または地下に避難してください」と繰り返した。あたかも戦争が始まったかのようではないか!それは、打ち上げが失敗して黄海に落下した事が分かるまで続いた。
まるでそれは「オオカミが来たぞ」と騒ぎ立てて村人を脅しつけたオオカミ少年と同じだ。
爆発する「弾頭」を搭載したミサイルと「衛星」を搭載したロケットはまったく別物である。当然、こうした疑問も想定して、「大陸間弾道ミサイルの技術を使ったロケット」だと言い張るが、それは自公政権・防衛省が恣意的判断をしているということに他ならない。
彼らの目論見のためには、「国民」向けにはあくまでも「ミサイル」であり、ミサイルが落下して爆発すると思わせる必要があるのである。そうすることで、通過が想定される沖縄諸島に「迎撃ミサイル部隊(PAC3)」を配備できるのである。
◇軍隊は大衆を愚昧とみなしゴリ押し
北朝鮮は過去5回人工衛星を打ち上げ、そのうち2回衛星を軌道に乗せている。今度の「軍事偵察衛星」の打ち上げは、いわば本番だったが、第2ロケットの不具合で黄海に落下して失敗に終わっている。
25日には韓国も人工衛星を打ち上げ成功させた。飛行コースは同じく沖縄上空だったが、韓国の衛星発射に対しては何の警戒態勢を敷いてもいない。だが、韓国(や日本)のロケットであろうと不具合が起きて落下する可能性はあるのではないか?
北朝鮮がやることだからという御都合主義以外に、ここには大きな誤魔化しがある。通常は、人工衛星発射の際に迎撃ミサイルを配備などしない!
「災害出動」などで「国民」の認知度が上がってきたことに舞い上がったのか、防衛省(自衛隊)は軍隊の本性を露わにし出し、大衆を愚昧とみなして、ゴマカし、無知扱いして物事をゴリ押しするのが当たり前になっている。
真の目的は、「国民保護」などではなく、沖縄諸島にミサイル部隊を配備することである。
それは岸田政権・防衛省が「仮想敵国」とみなす中国に対抗して「尖閣諸島(釣魚台)」の存在する東シナ海や南シナ海で覇を唱えるためのものに他ならない。
◇岸田政権は米軍に対抗する北朝鮮の行動を軍拡に利用
このミサイル騒動に乗じて、与那国では台湾有事を想定して保守派の町長や議員が建て替える庁舎に強固な地下室をつくるとか、各戸に地下シェルターを作れとか迎合しているが、その上の建物は破壊されてもいいというのであろうか?
それに台湾有事を日本有事にするなと要求する知恵もなさそうだ。小さな離島の土建屋政治家を丸め込むなど自公政権にとってはたやすいことなのであろう。
姑息な自公政権は、米軍に対抗する北朝鮮の行動を利用して、自らの軍備拡大に利用してきたのである。だが、人はいつまでも無知でいると思うのは大間違いだ! (沖縄 S)
|