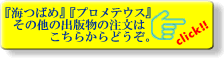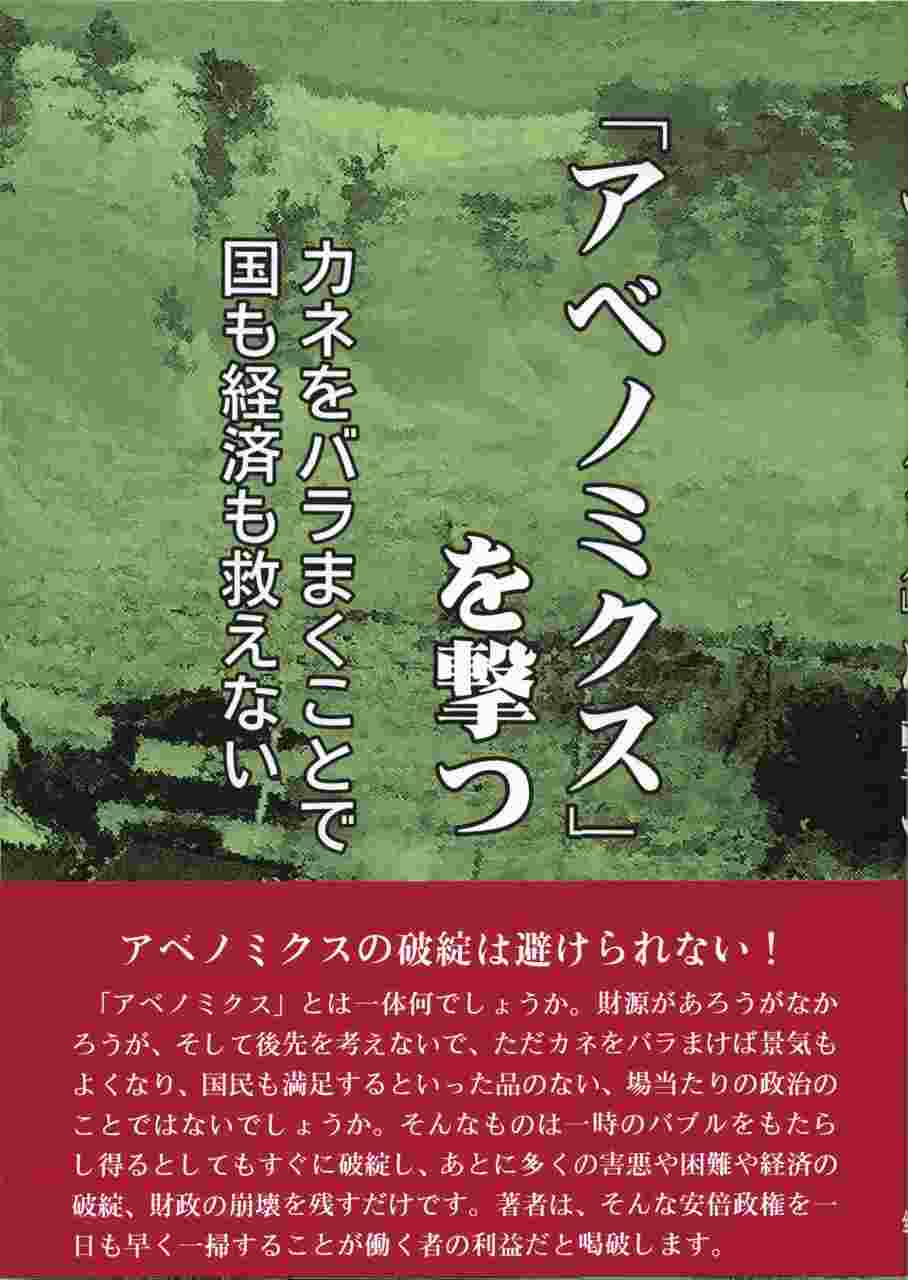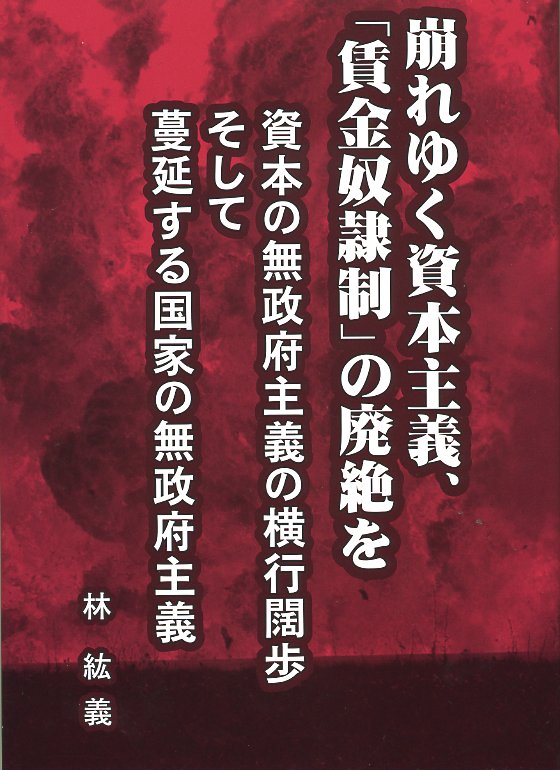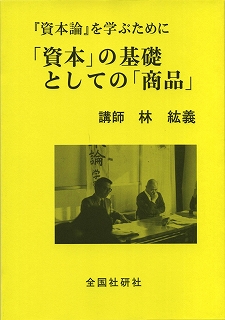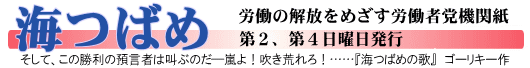 |
||||||||||||
| 購読申し込みはこちらから | ||||||||||||
|
●1494号 2025年3月9日 【一面トップ】 米価高騰の真の原因は何か ――零細農業を温存し減反政策を続けた末に 【一面サブ】 自公政権を助ける維新 ――高校無償化で3党合意 【コラム】 飛耳長目 【二面トップ】 中国はグローバルサウスと連携し米国トランプ政権 に対抗する! 【二面サブ】 トランプの帝国主義的外交 ――決裂したウクライナ資源開発交渉 ※『海つばめ』PDF版見本 【1面トップ】米価高騰の真の原因は何か零細農業を温存し減反政策を続けた末に物価高騰が止まらない。その中心に主食の米が躍り出た。今年の1月、米価は前年比で+70%、2月には+78%に急騰(消費者物価指数・東京都区部)。米価上昇率は「過去最大を5ヶ月連続で更新」。政府は当初、米の生産量は増えているから「秋に新米が出回れば値段は下がる」と脳天気に構えていたが、当てが外れて非難が殺到した。 ◇集荷数量の減少を投機のせいに米価高騰の原因について、政府は米が投機に使われているからだ、投機を抑えるために3月末に備蓄米21万トンを放出すると宣言。しかし、一部投機筋の買い占めが原因であるなら、備蓄米放出の表明後に少しは下がっていいはずだが、びくともしない。 そこで、政府の説明を追ってみよう。 毎年12月頃になると、新米が流通に出回り「集荷数量」は増える。この12月段階の「集荷数量」について、政府は前年比で20・6万トン減少したと発表していた(23年産236・3万トン、24年産215・7万トン)。 さらに、今年1月末段階での「集荷数量」は前年比で23万トン減少(10・7%減少)したと訂正し、この減少の原因は投機的ブローカーが買い占め、また、農家が売り渋っているためだと言い逃れた。 昨年春頃から「今年の米収穫量は少ない」という情報が流れ、さらに8月に発生した九州の地震が南海トラフと関連があるという情報も流れたために、それ以降、米の売り惜しみ・買い占めが発生したと政府は説明する。果たして、そうか? ◇収穫量は増えた?「集荷数量」が減った原因を投機のせいにする政府にとって、米の生産量または「収穫量」が減っているとは、口が裂けても言えず、政府は「収穫量については増えている」と強弁する。 昨年夏の異常気象によって、米の白粒化や育成不良などが発生し、「収穫量」は減ると誰もが直感したが、政府は逆に24年産米は23年産米より「収穫量」が増えていると、次のように説明する。 24年12月10日に農林水産省の大臣官房統計部が発表した「作物統計調査」によれば、24年産の「主食用」米の「収穫量」は前年より18万トン多い679・2万トンである。昨年の「水稲の収穫量(子実用)」は734・6万トンで、「子実用」には主食用の他に米粉用、加工用、備蓄用があり、そのうちの「主食用」が前述の数字である。水稲はその他に「青刈り」という飼料用などがあり、陸稲を含めた稲生産総量は年1千万トン程。 24年10月に、政府は「主食用」米の「収穫量」が前年比で22万トン多い683万トンと発表していながら、2ヶ月後の「統計」で少なく訂正するのだから、政府の発表は当てにならない。 要するに、政府は米の需要が減っている中で「収穫量」が20万トン程も増えているから米は余る筈だ、それにもかかわらず、米価格が高騰したのは、農家や流通で「売り惜しみ」「買い占め」が行われているからだと言いたいのである。 だが、22年以降の輸入物価高騰によって、小麦価格が上がる中で、米は値頃感があった上に、昨年は特に訪日外国人が大幅に増えたことが加わり需要はかなり増えていた。政府はその見通しを誤ったが、そうとは言えない。政府は米の需要が毎年10%程度減少しているという〝科学的予測〟(先入観?)に基づいて、政府の需要見通しに合わせた減反政策を農家に強いてきたからだ。 実際、22年産の米は670万トンであり、23年産の米は9万トン少ない661万トンだ。24年産米は増えたと強弁しても、猛暑の中で何故増えたのかは皆目わからない。 今年の「主食用」米の「収穫量」が増えたという政府の発表は、猛暑を考慮に入れるならば、眉唾物だろう。白粒化や生育不良になった米は「主食用」から「飼料用」や「加工用」などに転換された可能性があるのだ。もしそうであるなら、「主食用」米の需給が逆転し価格高騰を招くのは必然であろう。 ただ言えることは、需要が増えるということを見通せず、必要生産数量が足りなくなり、それが直接の原因となって米の価格高騰を招いたのである。投機屋はそこに付け込んだに過ぎない。 ◇騒動の原因は減反と小規模農業米の需要は年々に減少すると見込んでいる政府は、米価格維持のために、農家に対して米生産量の引き下げを強要してきた。いわゆる減反政策である。 その目的は、日本の小規模農業を守りながら、米価の安定や米需給の均衡を図ること、さらに、米を他の作物に転作させることである。減反政策は1971年から開始され2018年に廃止されたが、それは減反が自由競争を建前とするTPP参加と矛盾した存在であり、海外政府に配慮するためであった。しかし、減反政策は形を変えて生き続け、むしろ強化されてきた。これまでの「米生産目標」に代わって「米適正生産量」なる指標を農家に押しつけ、かつ、大幅に増やした補助金によって減反を達成させていった。補助金は、「主食米」から麦・大豆への「作付け転換」や「水田から畑地化促進」などとして3千億円も注ぎ込まれてきた。 その結果、「平成の米騒動」に続いて、今回の「令和の米騒動」を招いたと言えるのだ。 米価高騰の責任は共産党にもある。なぜなら、共産党も自民党と一緒になって、「家族経営農業」を死守してきたからだ。労働者は小経営農業に対する自民党の補助金バラ撒きによって税金の負担増を強いられ、また、減反政策によって高価な米を食べさせられてきた。 それだけではない、小農業を後生大事に保護し温存し死守することに進歩的な意義は無い。 小農業保護と結びついて行われる減反政策は、規模拡大と合わせて行われる科学の応用(豊かな土壌改良で米の成長を促すことなど)や自動化による少人数で運営できる合理的な生産と対立する。ただ農業を衰退させる反動的なしろものなのだ。今回に限らず、米価高騰の真の原因はここにある! 労働者は、未来のためにも小規模農業・零細農業の保護と温存に反対する。小農が保有する多くの小土地を合理的に再編・統合し、科学や技術を応用して少人数でも米の必要生産量を維持し拡大できる基盤をつくるべきだと主張する。 (W) 【1面サブ】自公政権を助ける維新高校無償化で3党合意自民・公明と維新は2月25日、維新の提唱する「高校授業料無償化」などの実施に向けて、2025年度当初予算を修正することで合意した。維新は「公約の実現」が大事だと成果を誇るが、膨張する国債費・軍事費を増大させる予算案であり、労働者大衆へ犠牲を強いる予算成立に協力する反労働者的な維新を如実に示すものだ。 ◇教育改革にもならない「高校無償化」「高校授業料無償化」は、現在国が支援する高校授業料の「就学支援金制度」の対象を拡大するものだ。現在の国の支援金額は、公立高については年収約910万円未満の世帯に授業料相当額の年11万8800円、私立高は年収約910万円未満の世帯に同額、年収590万円以上910万円未満の世帯には年39万6千円まで(授業料との差額は各世帯で負担)を支給するとなっている。これを「年11万8800円」について25年度から所得制限を外し、私立高に対する「年39万6千円」についても26年度からは所得制限を外し、支給金額も「年45万7千円」に引き上げるものだ。その他、低所得者向けの奨学給付金の拡充、給食無償化などを明記した。 しかし所得制限なしの私立高を含む「高校授業無償化」は、高所得者にも恩恵を分け与え、有権者の支持を拡大しようとするものだ。すでに今年度から公立・私立とも段階的に所得制限を撤廃した大阪府では、私立高の人気が高まり公立高が定員割れし、府立高が再編整備の対象となり、行きやすい近くの公立高校に行けないなど、所得による教育格差助長の新たな問題が生じている。高所得者優遇の所得制限撤廃よりも、教員待遇や設備充実など私立と公立の是正を優先すべきなのだ。 教育改革は、何よりも私的利益獲得を目的とするものではなく、社会的共同体の成員として科学的知見の獲得、社会的人間性の育成を目的とするものでなければならない。 ◇3党合意で労働者に敵対する維新3党合意で、維新が予算案に賛成する条件としたのが高校授業無償化と社会保険料の引き下げである。維新は合意文書では社会保障改革による国民負担軽減を実現するため3党の協議体を設置するとし、「国民医療費の総額を年間で最低4兆円削減し、現役世代1人当たりの社会保険料を年間6万円引き下げることを念頭に置く」と記した。 維新は「社会保険料を下げる改革案」として、「OTC類似薬(処方箋医薬品ではないが公的保険の対象となっている医薬品)の保険適用の除外」「応能負担の徹底」「医療産業のDXによる成長産業化」などを挙げている。医療に関する科学技術の適用は当然であるが、維新はこの改革で「現役世代の社会保険料引き下げ」を主張することに見られるように、その真意は働けなくなった「退役世代」に負担を求めるものにほかならない。しかしそもそも社会保険は、働けなくなった退役世代を現役世代が助ける、労働者の相互扶助から生まれたものだ。労働者の「退役世代」に負担増を強いる維新の改革案は、許されるものではない。 医療費の軽減にしても、医療が利益を得るための経営として資本主義的に行われていることが問題なのだ。医療・介護は、資本の制約を止揚した労働者の共同体社会の下でこそ、真の相互扶助として社会的に解決が可能だ。 結局、維新の「教育無償化」と「社会保障改革」は、若い世代に媚びを売るような大衆受けする政策を提案して支持を獲得し、その実は、労働者大衆を行き詰まった展望のない資本主義社会に縛り付ける役割をするものだ。しかも維新は、「教育無償化」の25年度に必要な約1千億円の追加財源は示し得ないのだ。 維新は3党合意で次年度予算成立を助け、金権腐敗の自公政権の延命を図り、労働者の階級的闘いに敵対する。 (佐) 【飛耳長目】 ★「令和の米騒動」は備蓄米21万トン放出発表によっても終息せず、2月のスーパー店頭価格の全国平均は5キロ3892円(数値は農水省)で、昨年2月の2千円程と比べ90%以上の高騰だ★23年産米の作況は平年並みで量は足りていたが、高温障害で精米歩留まり(玄米から白米になる量)が悪く、実際の作況は100を切っていた。そして8月8日、日向灘でマグニチュード7・1の地震が発生。「南海トラフ地震臨時情報」で需要が急増★逼迫はコメを投機商品に変え、買い占め売り惜しみで店頭から消えた。だが、生産や流通の問題以上に、減反政策廃止(18年)後もコメ生産を抑制して価格維持のため、転作に応じた農家に手厚い交付金を出すなど、コメ需給を不安定にしてきた責任が追及されるべきだ★23年産のコメ生産は、661万トンに対し需要は705万トンと上回っていた。政府輸入米(国内農家保護策に義務付けられた買い入れ)77万トンの内10万トンの主食用を加えても足りない★民間の輸入にはキロ当たり341円もの従量税が掛かる。25年1月の国際価格は1キロ75円弱と驚くほど安い。実際、中国の高級スーパーでもキロ8元(約168円)で売られている。小規模農家の保護ではなく、農地の集約と機械化による大規模経営こそ必要なのだ。 (Y) 【2面トップ】中国はグローバルサウスと連携し米国トランプ政権に対抗する!中国は、グローバルサウス(GS)、EU諸国に今年初めから活発に働きかけを行っている。中国外相は1月5日~11日、14日~17日に、35年連続新年最初のアフリカ8ヶ国訪問を行った。2月12日~18日には英・独・米・南アを訪問。電話会談を含めて25カ国の首脳や外相と意見交換し共同声明を出した。 ◇GSのリーダーを自負する中国25日、中国外務省は「激動の世界で、中国が安定の要だとみて、世界的課題の対処に中国が役割を果たすよう望む国が増えている。私たちは、重い責任をより痛感している」との声明を発表。 中国とGSに属する国々との経済的、政治的関係は急速に深まっているが、新年早々35年連続でアフリカを訪問先に選ぶ理由は、アフリカ各国(54ヶ国)との政治、経済関係を深めて相互の人的交流、貿易取引、市場の確保、希少鉱物資源などを手に入れる事であり、インフラ建設を通じて中国に依存する国を囲い込むことである。それは国連における中国賛成国に仕立て上げることで、中国が意図する国際秩序への道筋をつけようとする取り組みの一環でもある。 こうした取り組みは、ウイグル自治区におけるウイグル人に対する民族浄化作戦に対する国連人権理事会において、「45~69ヶ国のグローバルサウスの国々が中国擁護の声明に署名し、中国への懸念声明に署名する国家を圧倒している」ことに表れている。 米国はこれまで、国連安保理における偽善的立場を繰り返してきた。ロシアのウクライナ侵攻にはロシアを批判する決議案に賛成するが、イスラエルによるガザのパレスチナ人のジェノサイドには拒否権を行使し、イスラエルを擁護した。 かつて米国や西欧はアフリカや中東、東南アジア、南米を収奪し傀儡国家を造り経済的、軍事的に支配し収奪して来たが、今中国は、中国も西洋列強や日本に侵略され植民地化された苦難の過去から今日の中国を作り上げてきた、新興国・発展途上国を代表するリーダーであると自負している。 ◇米中は攻守の所を変えるこれまで世界のルールは、G7など米国を盟主とする欧米資本主義国が作り上げてきたが、GS(国連の定義では中国を除くグローバルサウスG77。世界に占めるGDP16・4%で中国にほぼ匹敵する。G7は46%)の経済力は今後さらに発展することが予測され人口は2050年には世界の約7割をGSが占めるなど多極化はさらに進む。 24年11月にブラジルで行われたG20サミットに出席した習近平は、「平等で秩序ある世界の多極化」を訴えた。トランプ政権発足を見越して、経済は協力、金融は安定、貿易は開放などの構築を呼び掛けた。 トランプの保護貿易の追加関税を否定し、「互いに相手国をライバルではなくパートナーとし、国連憲章の趣旨と原則に基づく国際関係の基本準則を順守」(人民日報11月19日)を訴えた。世界の安全保障においても「G20は国連及び国連安保理がより大きな役割を発揮することを支持し、危機の平和的解決に資するあらゆる努力を支持する必要がある」(同)とした。 中国は、バイデン政権が主張する〝権威主義国〟対〝民主主義国〟の対決という構図を打ち破るために、国連憲章に基づく国際関係の構築を繰り返してきたが、第二期トランプ政権の政策と立場は、米国がトランプ独裁の〝権威主義〟国家に転落したことを自ら暴露した。 米国の〝自由〟や〝民主主義〟は、移民排除、白人優位の人種差別、プーチンのウクライナ侵略を不問に付し、黄金のトランプ像が立つ「トランプ・ガザ」(AI動画)がガザ問題の解決と考える。愚かで無責任な大統領とそれを取り巻くリバタリアンや金儲けに余念がないブルジョアがワシントンを支配する社会である。 トランプ政権は、国務省のHPから「中華人民共和国」という正式国名を「中国」に表記を変更し、「CCP」(中国共産党)と言う悪意ある名称も用いている。トランプ政権や米国は、米国の衰退によって維持できなくなった帝国主義的権益を侵食し、飛躍的な発展を遂げてきた中国に対して「パートナー」はおろか「ライバル」と見る余裕すら失っている。 米国は、一強体制が崩れた後に訪れたGSの台頭に対応することが出来ていない。なぜなら、米国の帝国主義的な支配こそが、GS諸国に苦難に満ちた国家建設を強いて反米感情を生み出したからである。 GSと連携し米国に対抗する中国は、積極的に中国の立場を発信し、中国に賛同する国際的な世論形成を意識的に行っている。これは中国共産党が15年ごろから主張してきた「話語権」(「中国式現代化」などを積極的に発信する)の行使に他ならない。しかし、GSとの連携は主張とは裏腹な関係である。 ◇GS連携の内実は収奪する中国GSとの連携を掲げる中国は、GSの一員として信頼できるパートナーを自称する。その実態は中国の圧倒的な経済力と政治力を背景に、中国に依存させ収奪する連携である。貿易収支は一貫して中国の黒字が続いている。10年は中国のGS諸国との貿易黒字は1344億ドルであったが、23年には5375億ドルと4倍に拡大した(ASEANは8・5倍)。安い中国製品が大量に輸入されることによって、それらの国の産業発展が阻害され雇用が悪化している。 中国が貿易額のトップを占める国は122ヶ国に及び中国抜きに経済活動の維持は困難である。23年以降は中国からの輸出単価は低下し、数量は増大する傾向にある(代表は鉄鋼、太陽電池)。コロナ終息宣言を発出し経済活動が一気に動き始めてからである。それは国内で消費できない過剰生産品を安価で輸出し、相手国の産業育成を阻害する〝近隣窮乏化政策〟に他ならない。中国は自国の困難を他国に押しつける〝不公平〟な政策をとる。貿易だけではなく中国はGSに対する公的債務最大の貸し手であるが(1812億ドル)、中国の影響力が強いアフリカ諸国のデフォルトリスクが最も高い(約6割)。米国と覇権を争う中国はGSの一員を自称し帝国主義的野心を隠すが、ASEAN諸国は中国の領土拡張の軍事圧力と対峙している。 GSも一枚岩ではなく、インドは中国に対抗して23年1月に「グローバルサウスの声サミット」を開催した。印中が対抗するのは、GSに属する国々が今後、飛躍的に経済発展を遂げる可能性が高いからである。 世界はかつてない激動を迎えている。日本、世界を労働者党と共に考え共に闘おう。 (古) 【2面サブ】トランプの帝国主義的外交決裂したウクライナ資源開発交渉2月28日、米国大統領公邸で行われた、ウクライナの希少鉱物資源の開発をめぐってのゼレンスキーとトランプの会談は両者の意見が合わず決裂に終わった。会談はトランプの帝国主義的外交を明らかにしている。 ◇ウクライナは米国支援を期待ウクライナが国内の鉱物資源の共同開発を米国に提案したのは、米国の支援継続を期待したからであった。 ウクライナには、電気自動車(EV)のバッテリー製造に使用されるグラファイトが約1900万トンの確定埋蔵量があるという。その他航空機、自動車部品などで用途が広いチタンも豊富で、同国は欧州における供給量の約1割を占めている。バッテリーに使うリチウムの埋蔵量も欧州の3分の1を占めている。さらにウラン、マンガン加え、武器や電子機器に欠かせないレアアース(希土類)の鉱床も確認されている。米国が産業用に使用するチタン40年分の埋蔵量がある(以上、「日経」3・1)。 これらの鉱物資源は、ロシアの侵攻で荒廃したウクライナの復興に役立てられるものであった。しかし、ゼレンスキーがこの資源開発利権を与えることをトランプに提案したのは、不利な停戦となるのを避け、停戦後のロシアの再侵攻を防ぎ、〝自国の安全〟を維持するために米国の支援は欠かせないとゼレンスキー政権は判断したからである。 ◇鉱物資源獲得がトランプの目的トランプは、ウクライナとの「協定が成立すれば、1兆ドル(約150兆円)規模になるかもしれない」と得意満面に国内にアピールした。米国の企業が資源開発に参加することで、大きな利益が転がり込んでくるというのだ。 しかし、協定締結のための会談は、ゼレンスキーがトランプの外交姿勢を問い正したことで、ウクライナと米国の思惑の相違が表面化した。 ゼレンスキーが、鉱物資源を与えるこの協定文書は「ウクライナの安全保障の第一歩」であり「プーチンの(侵攻を)止めるには十分ではない」と安全保障の具体的政策をトランプに質した。そして、ロシアは停戦協定を破り、2014年のクリミア、ウクライナ東部を占領したにもかかわらずオバマ、バイデン、トランプの歴代政権はこの蛮行を止めようとしなかった述べた。 どのようにプーチンの再侵攻を防ぎ、ウクライナの「安全」を守るのかという問いにトランプはまともに答えようとせず、米国の政策について「私たちを指図する立場にはない」といきり立ち、「あなたは(停戦交渉の)カードを持っていない。我々がいて初めて交渉のカードを手に入れのだ」、「今、君は数百万人の命を使って賭けをしている。第3次世界大戦をめぐって賭けをしている」「あなたは勝っていない。私たちのおかげで、無事に済む可能性が非常に高いのだ」、「あなたのしていることは「この国(米国)に対して非常に敬意を欠くことだ」と非難、「鉱物資源をめぐる協定に合意するか。我々が手を引くか、どちらかだ」と凄んだ。 ウクライナに勝ち目はないのだから停戦に応じろ、文句を言わずにさっさと協定文書に署名しろというのがトランプの言いぐさだ。 ◇安全保障について「話したくない」記者からの「安全の保証は提供してもらえるのか」という質問に対しては「まだ安全保障について話したくはない。私はこの取り引きを成立させたい」「この取引が成立すればそれで終わりになるだろう」と答え、また「米国の権益がある場合、その地域から軍を撤退させるようにプーチンに言うのか」という質問にたいしては、「まず様子を見てみよう」と言い、「ロシアが侵攻してきたらどうするのか」という問いにも「そんなことは起きないだろう」と曖昧に答えるのみである。 トランプはウクライナの「安全保障」についてまともに考えていないことは明らかであろう。ゼレンスキーが協定書に署名しなかったのは当然である。 ◇偽りの「平和の実現」交渉決裂後の3月3日、トランプはウクライナが欧米による「安全の保証」などを条件にしていることを理由に軍事支援を停止することを指示した。これで喜ぶのはプーチンである。トランプの言う「平和の実現」が口先だけであることが暴露された。 トランプにとって自国の利益が第一(米国第一主義)であって、ロシアの侵攻によって計り知れない犠牲を被っているウクライナのことなどかまいはしないのである。 軍事力を背景にウクライナの苦境に付け込んで鉱産資源の利権を分捕る、これがトランプの目的である。トランプ外交は、帝国主義外交そのものである。トランプは自国の利益のためにプーチンのウクライナ分割を認めようとしているし、中東ではイスラエルの領土拡張を認めた。こうした力による利権の獲得や領土拡大が認められるとするなら、中国はじめ他の国もそれに習うだろう。国際社会は軍事力拡大の時代、弱肉強食の様相を色濃くしている。 こうした状況を突き破り、国際社会の平和、協力を実現していくことが出来るのは、帝国主義、資本の支配に反対し、搾取のない社会、世界的な協力と融合を目指す労働者の闘いである。 (T) | |||||||||||