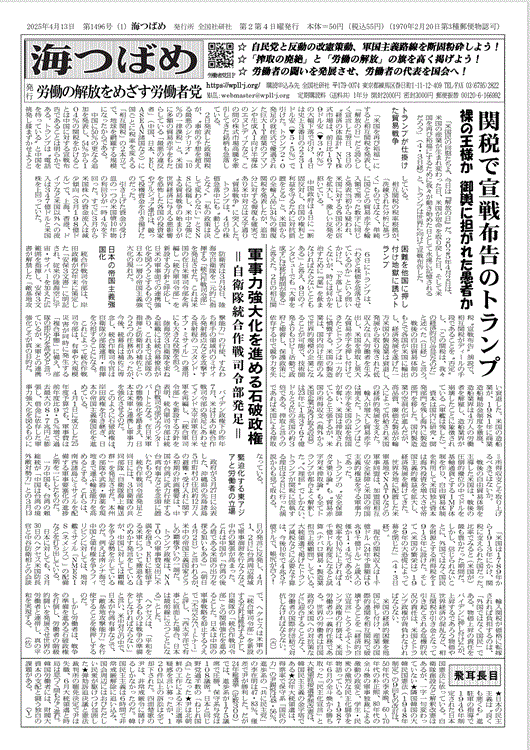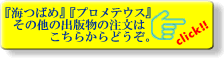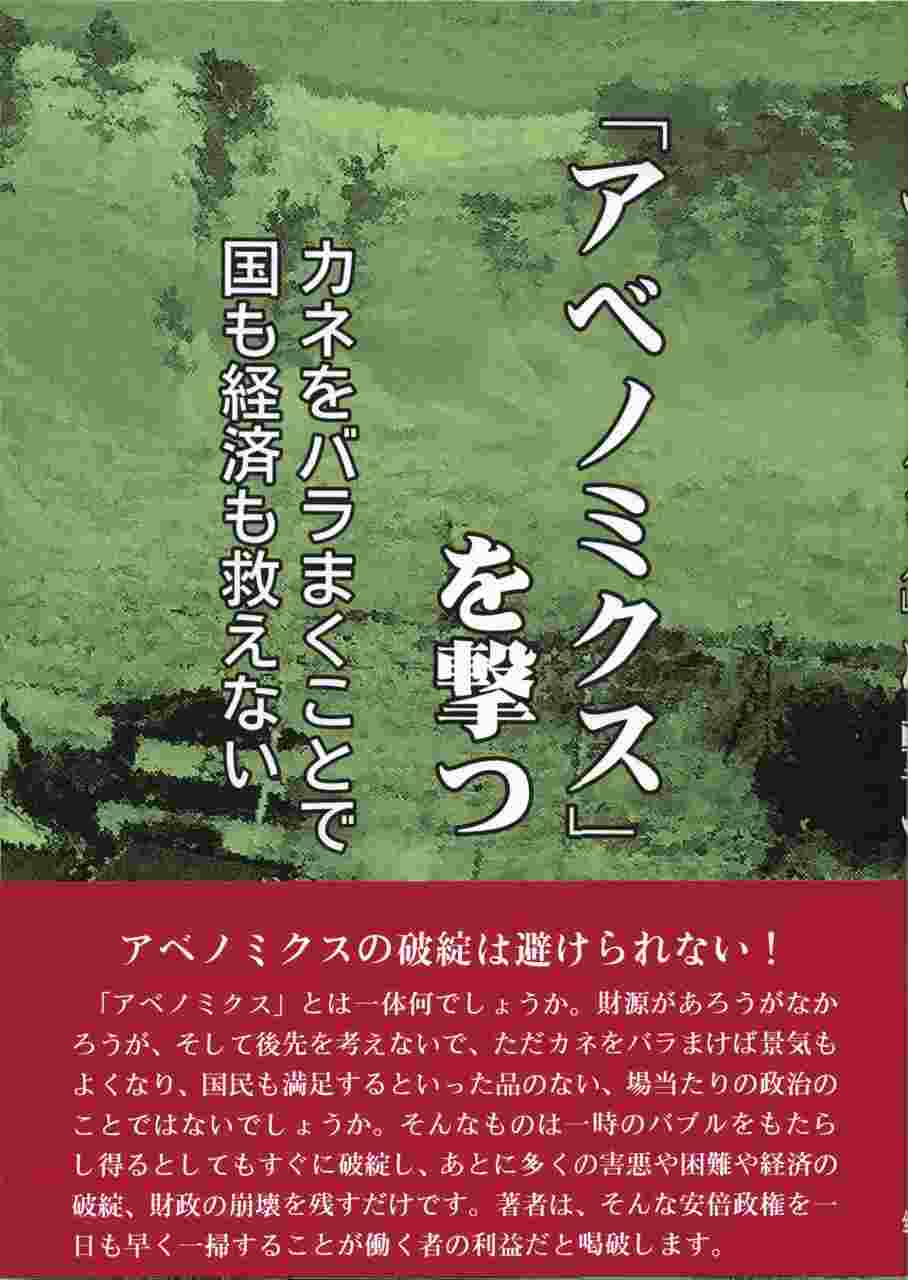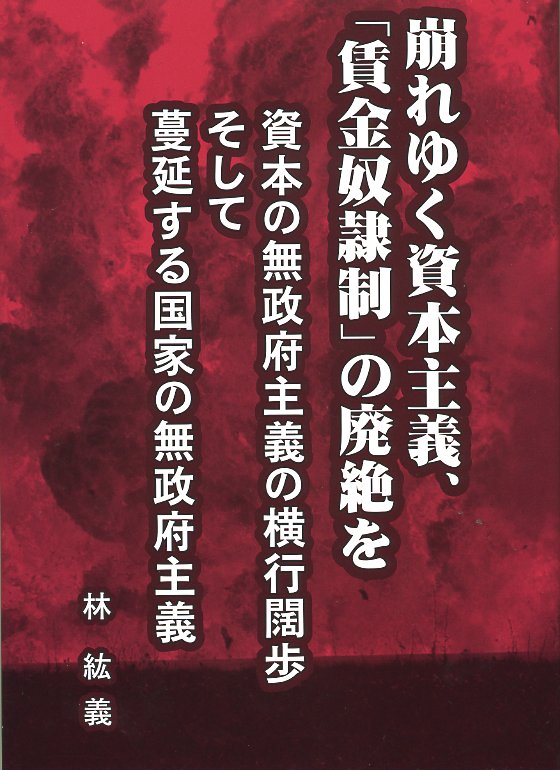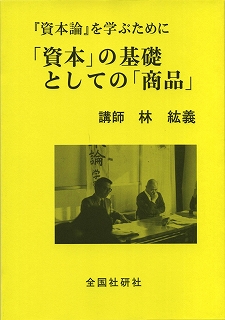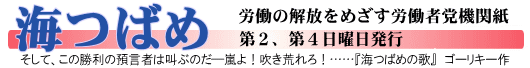 |
||||||||||||
| 購読申し込みはこちらから | ||||||||||||
|
●1496号 2025年4月13日 【一面トップ】 関税で宣戦布告のトランプ ――裸の王様か 御輿に担がれた愚者か 【一面サブ】 軍事力強大化を進める石破政権 ――=自衛隊統合作戦司令部発足= 【コラム】 飛耳長目 【二面トップ】 国債削減計画の矛盾 ――金利低下傾向は国債保有によるのか? 【二面サブ】 トランプ関税、輸出産業を直撃 ――日本は国内総生産にマイナスの予測も ※『海つばめ』PDF版見本 【1面トップ】関税で宣戦布告のトランプ裸の王様か 御輿に担がれた愚者か「米国民の同胞たちよ、今日は『解放の日』だ。2025年4月2日は、米国の産業が生まれ変わった日、米国が宿命を取り戻した日、そして米国を再び裕福にするために我々が動き始めた日として永遠に記憶されるだろう」(4・3日経)と、トランプは世界に向けて宣戦布告した。 ◇トランプが仕掛けた貿易戦争「米国を再び裕福」にすると相互関税を発表し、「解放の日」だと誇らしく宣言した翌日、3日の〝経済の体温計〟NY株式市場は、前日比1679ドル安(▼3・97%)の大幅下落で引け、4日は史上3番目の2231ドル安(▼5・5%)で引けた。トランプ2・0発足の就任式で優遇された巨大IT産業のアマゾンや生成AI向け半導体のエヌビディアなど、この間の株式市場高騰を牽引してきた銘柄も急落している。 2日発表した政策関税が、〝事前の予想を超える最悪のシナリオ〟「10%の一律課税」と、米国に多額の貿易赤字をもたらしている「最悪の違反者」(中国、日本、EU、ASEAN諸国など)に国ごとに税率を変える「相互関税」の2本立てで、地球を網羅する規模になったからである。 中国に50%の更なる追加を発表し、54%から104%の関税をかけることは中国に対する宣戦布告であることは明らかである。トランプは〝電話を待っている〟と中国を挑発し膝まずかせようとしている。 相互関税の税率根拠が、「洗練された分析に基づく」ものではなく、単純に国ごとの貿易赤字を輸入額で割った数字に同じと発表当初から疑われ、米国に対する各国の不信を拡大し、激しい反発を招いている。 中国政府は4日に「断固反対し、自国の権利と利益を守るために対抗措置をとる」と、米国からの全輸入品に34%の報復関税を発表したが、追加分に対する報復も確実であり米中対立は文字通り〝貿易戦争〟に突入した。 トランプは、4日の株価急落中にも〝動じることなく〟「私の政策は決して変わらない」とSNSに投稿し、米中2強による貿易戦争の始まりが世界経済に与える悪影響を恐怖した各国の投資家やブルジョア連中は、競って投機資金を引き揚げたのだった。 引き上げた資金の受け皿の一つの米国債10年物の利回りが一時4%を下回った。すでに3月から米国株への資金流入は減少傾向(3月198億ドル)で、上海、香港、ドイツなど米国以外への流入は347億ドルと米国株を上回っていた。 ◇困難を他国に押し付け地獄に誘うトランプ6日にトランプは、「わざと株価を急落させているのか」という問いかけに、「下落してほしくないが、時には何かを治すために『薬』を飲まなければならないこともある」と答え、9日のインタビューでも「大事を成すには移行期間が要る」と答えた。2日の相互関税〝宣戦布告〟演説で、相互関税がディールの手段であることを〝否定〟し、「この関税は、我々の経済的自立宣言なのだ」と述べた(日経)と言う。 戦後の自由貿易体制のもとで各国が米国に輸出し、経済発展を遂げた一方米国の製造業は衰退し、発展から取り残された低収入な白人労働者を生み出し、米国を搾取し莫大な貿易赤字を押し付けてきたとトランプは一方的に憤慨する。米国の製造業は、国内向け生産のみで世界的規模の企業になることが可能で、技術開発よりもロビー活動で政府と癒着し、保護政策に依存する中で競争力を失い衰退した。米国の造船業が、1981年に商業造船補助金制度を撤廃、造船業界は4万人の労働者を解雇し、造船業界が崩壊したことに象徴されている(軍艦は残した)。 資本は国内に研究・開発部門を残し海外に製造部門を移した。国内製造業の空洞化が進んだが、高品質、廉価な製品が輸入によって供給され米国の経済的発展を支えた。 輸入が増大し貿易赤字は増えた。トランプはこの赤字を米国の富を他国が奪い、米国は搾取されていると主張するが、米国の所得収支(海外から米国企業が受け取る収益)は23年に1兆3767億ドルと2位の英国の約3倍である。搾取と言うのであれば米国による搾取=所得収支こそ取り上げるべきではないか。 戦後の自由貿易体制を主導した米国は、戦後の圧倒的優位の中でドルを基軸通貨とするIMF体制を作り、自由貿易体制を利用して米国独占資本は海外投資を増大させ帝国主義的権益を拡大し、経済発展を続けてきた。 世界各地に配置した米軍基地やNATOなどの軍事同盟は、加盟国相互の安全保障と米国の帝国主義的権益を守る軍事力であった。 トランプの〝安全保障タダ乗り論〟も〝貿易赤字対米搾取論〟も全てトランプが都合よく解釈した〝へ理屈〟でしかない。トランプが関税に固執する理由は2日に行った演説からも見て取れる。 「米国は1789年から1913年にかけ、関税に支えられた国だった。比率でみると(米国が)最も豊かだった期間だ。しかし、信じられないことに、外国ではなく国民を財源とする所得税を1913年に設けた。そして(米国の繁栄は)1929年の大恐慌によって幕を閉じた」(4・3日経)。 現在の関税収入は1千億ドル(24年予算額は6兆9千億ドル)と歳入の僅か1・4%であるが、税率を10%に上げれば4千億ドル程度になると試算(ナバロ貿易・製造業担当上級顧問)している。大統領選で掲げたトランプ減税などに必要な予算は、今後10年で4兆5千億ドルで、帳尻が合う! 輸入関税が価格に転嫁されれば負担するのは、「外国ではなく国民」である。物価上昇の責任をバイデンに押し付けたが、上昇するであろう物価や世界経済の混乱など、相互関税が引き金となって引き起こされる危機的状況の責任は、米国とトランプ政権が背負わなければならない。 米国の経済的困難を他国に押し付け、産業の国際的連関を相互関税で破壊することを「経済的自立宣言」とうそぶくトランプ政権の打倒は、米国労働者の一義的任務である。世界の労働者は自国政府の米国への対抗策などに迎合することなく、労働者の国際的団結で対抗しなければならない。 (古) 【1面サブ】軍事力強大化を進める石破政権=自衛隊統合作戦司令部発足=防衛省は3月24日、陸海空自衛隊を一元的に指揮する「統合作戦司令部」を発足させた。これは米国の在日米軍司令部を再編し「統合軍司令部」を新設する方針と呼応し、日米の軍事面での連携強化を図ろうとするもので、日本の一層の帝国主義強大化の現れだ。 ◇日本の帝国主義強国化統合作戦司令部は、岸田政権が22年末に策定した「安保3文書」に明記され、従来の陸海空に宇宙・サイバーを加えた広範囲を指揮し、安保3文書が解禁した「敵基地攻撃能力」の行使、すなわち相手の領域内のミサイル発射拠点などを攻撃する長射程の「スタンド・オフ・ミサイル」の運用にも大きな役割を担う。 陸海空3自衛隊を束ねる組織には統合幕僚長があり、これまでは部隊の指揮と防衛相の補佐という2つの任務があったが、今後、統幕長は補佐に専念し、統合作戦司令官は自衛隊の部隊運用・指揮を分担することになる。 これによって統合作戦司令部は、有事や大規模災害が同時に発生する「複合事態」に備え、部隊の即応力を高めると言っているが、米軍との連携強化こそが真の目的だ。 バイデン政権下の昨年7月、米は日本の統合作戦司令部の発足にあわせてインド太平洋軍在日米軍を再編し、「統合軍司令部」を新設する方針を表明、統合軍司令部は統合作戦司令部のカウンターパートとなる。在日米軍の態勢強化を踏まえ、日本は米軍と連携し軍事力を強化させるのだ。 このように石破政権は、岸田政権を引き継ぎ、日本の帝国主義強国化を進めている。 4月1日に成立した25年度予算でも、軍事費は前年度比9・5%増で過去最大の8・7兆円と膨張し、借金に依存した軍事力強大化を図るものになっている。 ◇緊迫化する東アジアと労働者の立場政府が3月27日に公表した、沖縄県の先島諸島5市町村の住民約12万人の避難・受け入れに関する初期の計画概要は、中国が台湾に武力行使する台湾有事などを念頭に置いたものだ。 統合作戦司令部発足と同日には、3自衛隊の共同部隊「自衛隊海上輸送群」を発足させた。本州の部隊や武器・弾薬を現地まで運ぶ輸送能力を高めるとする。これらは、南西諸島にミサイルを配備する軍事要塞化の進捗と期を一にしたものだ。 一方中国も、台湾の頼総統が「中国は台湾の境外敵対勢力」との3月13日の発言に反発し、4月1、2日に台湾周辺海域で軍事演習を行なうなど、中台の緊張が高まった。これは中国が「台湾の後ろ盾である米国の出方を探る狙いもある」(朝日4月2日)と言われるが、米中の帝国主義国家どうしの覇権争いの一端だ。 トランプ政権は、NATOへの軍事費支出に不満を抱き、EUに駐留する米軍について撤退をほのめかす発言をしているが、中国に対しては覇権を争う姿勢を示しているのだ。例えば南シナ海で中国と領有権を争うフィリピンに対しては、地対艦ミサイル「NMESIS(ネメシス)」の配備などを打ち出している。 日本に対しても、3月30日のヘグセス米国防長官と中谷防衛相との会談で、ヘグセスは米軍の「統合軍司令部」を新設する方針は維持するとし、自衛隊の「統合作戦司令部」との関係強化を進めるとした。日本は中国の軍事戦略を抑止するうえで「不可欠なパートナー」と評し、「西太平洋で有事に直面した場合、日本は最前線に立つことになる」とした。 ヘグセスは、「平和を欲するものは戦争の準備をしなければならない」と言い、米中対立の中で、日本が台湾有事などで、「敵基地攻撃能力」を行使することを後押しするのだ。 しかし労働者は、戦争の準備を進める石破政権を打倒し、労働者の階級的闘いを発展させ世界の労働者と連帯し、真の平和を実現する。 (佐) 【飛耳長目】 ★日本の民主主義は〝良くも悪くも〟進駐軍の指導で1946年制定された日本国憲法に依っている。自衛隊創設など解釈改憲はあるが、一字一句変わっていない★隣国韓国の大韓民国憲法(1948年制定)の9回もの改訂は、50年代の李承晩、60~70年代の朴正煕、80年代の全斗煥の軍事独裁による激動の政変と、学生・民衆の激烈な民主化闘争を物語っている。1987年6月の全斗煥から勝ち取った「民主化宣言」と大統領直接選挙制改憲は、韓国民主主義の金字塔である★22年大統領選は、得票率で保守系「国民の力」の尹錫悦は48・56%、進歩系の「共に民主党」の李在明は47・83%、僅差で尹が勝利した。だが24年総選挙(定数300)では、進歩系が175議席で圧勝、保守系与党は108議席。日本と同じ野党過半数の「ねじれ国会」となった★尹は北朝鮮の工作による不正選挙疑惑を言い募ったが、120件以上の訴訟は全て却下された。四面楚歌の尹は、非常戒厳令に賭けるしかなかったのだ。韓国民主主義は6時間で非常戒厳解除に追い込み、国会周辺にはおびただしい民衆が駆けつけ包囲した★弾劾訴追決議と憲法裁判所の罷免決定で尹は失職、6月大統領選と時局は息つく間もなく進む。韓国労働者には、財閥大資本の支配と闘う独自の課題がある。 (Y) 【2面トップ】国債削減計画の矛盾金利低下傾向は国債保有によるのか?昨年(24年)7月末の「金融政策決定会合」で、日銀は長期国債買い入れの減額と保有国債の削減計画を発表した。その理由は「大量な長期国債を保有し続けることは、長期金利を押し下げる方向に働くメカニズム」を生み出し、日銀のこれからの金融政策の妨げになるからだと言う。 ◇卑俗な日銀分析黒田日銀と安倍の金融緩和策により日銀の国債残高が増えるに従って、長期国債(10年物)利回りはもちろん、平均利子率も連動して下がったように見える。 なる程、長期国債利回りは急落し16年から23年まで0・0~0・2%に沈んだ。 植田は「国債保有」の増大が「流通での残高を減らし」、「債権市場の機能低下」を招き長期金利を下落させてきたと言う。日銀が国債を爆買いしたのだから市場が機能しなかったのは当然であり、こんな卑俗な分析を披瀝して、国債削減計画を正当化している。 しかし、国債の金利は、貸付資本の利子と連動し、安倍政権よりずっと前から、80年頃から上下しながらも一貫して下落してきたのではなかったか。 植田は日銀の国債保有残高が13年から始まる第二次安倍政権以降、120兆円から5倍増になったことを問題にしているが、それ以前の50兆円~120兆円の時代でも金利は下がり続けたのだ。植田日銀の見解は早くも破綻している。 金利の長期下落は別のところにある。以降、それを見ていく。 ◇利潤率と利子率の低下国の債務証書である国債が資本として売買される時、その金利は貨幣の貸付利子率によって制約され、実際に、長期国債の流通利回りは銀行の貸付平均利子率と連動して動いてきた。そこで、まず貸付利子率(以下利子率)はいかに形成されるのかを検討する。 もちろん、利子率は市場で変動するが、本質的な制約は別にある。利子率は利潤獲得を競う総資本の運動の結果である一般的利潤率の規制を受けて形成されると論じたのはマルクスである(『資本論』第3巻など)。 資本主義は労働者から労働を搾取し、剰余価値を生産する。そして、各資本は剰余価値から借入れた利子の支払いを済ませ(経営者報酬や地代なども一緒に)、資本の再生産に投下する。それでも余れば、余剰資金としてまたは「内部留保」としてプールし、預金などで運用する。 この資本の循環過程で、借り手企業(産業資本)が利子付きで貨幣を借りるのは剰余価値を生産するためであり、借り手は実現した生産物価値(前貸価値+剰余価値)の中から貸し手に元金(貨幣)と利子を返えす。 但し、貨幣貸付けの場合、貸し手は期限付きで貨幣を貸しただけであり、借り手側に貨幣の所有権は移らない。借り手側では、貨幣は価値増殖する資本として機能する。つまり、借り手は剰余価値を生産し、平均的な条件の下では平均利潤を生産する。この価値を増殖するという貨幣の使用価値が商品となり、借り手はこの特殊な商品を買い、その対価である利子を貸し手に渡す。 利子は剰余価値=利潤から分割された一部分であることが明確になる。 従って、利子(平均した利子)は、基本的に総資本の利潤(平均的利潤)を上回ることはできないのである。この時、分割される比率が利子率になり、これに市場での変動が加わる。 次に、利潤率と利子率との関係を検討する前に、資本の利潤率を見ていこう。 資本の生産が拡大し、剰余価値Mよりも生産資本(不変資本C+可変資本V)が増えた場合に利潤率は下がり、または、剰余価値率(剰余価値M/可変資本V)よりも資本の有機的構成(C/V)が高まった場合に下がる――後者は利潤率の分子と分母の両方をVで割れば算出できる。 価値増殖を目的とする資本は常に資本の拡大を図る。そのために利潤率は傾向的に下がっていく。他方、利潤率が高い産業部門へ移動する資本間の競争があり、総資本の中に一般的利潤率が形成される。そうなれば、利潤の大きさは一般的利潤率によって規定され、利潤からの分割比率である利子率も一般的利潤率によって制約されることになる。 しかし、産業資本にとって、利子率は障害物であり、できれば借入を減らそうとする。貨幣の蓄積が進み、自前で投下資本を準備できるなら、借入は減り利子率は低下する。こうした状況が生まれるなら、利潤率が上がる局面でも利子率は下がったままになる。 例えば、60年代以降90年代半ばまで、一般的利潤率の傾向的低下と共に利子率も低下した。ところが、バブル崩壊後の90年代後半から様相は変わる。それまで続いていた一般的利潤率の低下は反転し、2020年くらいまで、ジグザグしながら上昇している。だが、利子率の方は以前と同様に低下したままであった。 利潤率の上昇は、バブル崩壊後、総資本は合理化(資本の再編・整理・縮小)や海外投資・海外生産委託や生産手段の自動化・効率化を進め、また、賃金削減(労働者の非正規化・賃金差別)を強行したためである。 他方、総資本は資本準備も合理化した。借入と利払いを削減し、自前の資本力を強化するために「内部留保」に努め、わずかな預金利子さえも獲得していったのである。利子率が下がったのは必然であり、これに連動した国債利回りも下落した。 ◇金融緩和策との関係こうした資本の運動について、日銀は全く理解しておらず、この間の低金利の原因を「国債保有」のせいにするのみだ。 もちろん、「アベノミクス」に呼応した黒田日銀によって国債大量購入が図られ、長期国債利回りは「ゼロ」になり、しかも16年と19年には一時「マイナス」になった。このように、日銀による金融緩和策によって2%程あった利回りが強引に「ゼロ」に誘導させられたことは事実であるが、必要なことは経済の内在的分析である。 ◇国債削減の矛盾日銀は国債保有残高を削減するというが、矛盾している。金利を引き上げるなら、国債の「含み損」は増加し、日銀収支の破綻(債務超過)が待っているからだ。 植田は昨年7月の日銀会合で日銀保有の国債削減計画を発表し、8月から実施すると述べたが、国債残高は減っていない。日銀の計画によれば、四半期ごとに約4千億円減額し、26年1月~3月期には約3兆円の残高削減を実現することになっている。ところが、昨年9月末時点の国債残高は583兆円であったが、今年3月末時点の残高は減るどころか、逆に587兆円へと4兆円も増えている。いったいどうしたことか? 10年物国債の利回りが2月下旬に1・46%に上がり、3月に入ると1・52%になった。1・5%台にのせるのは実に2009年6月以来である。 日銀は長期金利が上昇しだし、住宅ローン固定金利や長期貸出金利が相当に上がったことを見て、あわてて国債買いに走ったのだ。 ◇信用と金融の動揺・瓦解が進むところが、トランプの関税強化策が発表されるや日本のみならず、米国やEUでも国債が買われ、金利が急落した。投資家が経済失速と株暴落を警戒して国債買いに走ったからである。 さらにEUでは安全保障の懸念が強まり、国家の借金制限を緩和する動きが出ているが、そうなれば金融緩和に繋がる。 しかし、金融や信用制度は資本主義的生産にとって不可欠な調整弁や潤滑剤であるかに見えるが、いつでも、過剰信用を契機に過剰生産や過剰取引を作り出す歯止めの効かない添加剤に転化する。 もし、国債の大量発行が続き、また中央銀行の危機によって国債の信用及び価格が下落するなら、通貨の国家信用の崩壊につながり、さらには、信用貨幣であっても紙幣化が進む。 第一次世界大戦後、「政府紙幣」を大量に発行したドイツでは、また戦時中に国債を大量に発行し通貨をバラ撒いた日本では(特に敗戦後)、共に激しい「インフレーション」(貨幣価値の下落)が発生した。労働者とその家族が多大の犠牲を受けたのは誰もが知るところである。 労働者にとって何よりも必要なことは、こうした歴史を学び、資本主義の限界と矛盾を知り、かつ、その克服の方法を学び、金融も信用制度も必要としない、生産手段の社会的共有を基礎にした「喜びをもって働き労働に応じて自由に生活手段を受け取る社会」、つまり「共同労働社会」に向かって進むことである。 (W) 【2面サブ】トランプ関税、輸出産業を直撃日本は国内総生産にマイナスの予測も4月2日、米トランプ大統領は、世界各国からの輸入品に対して「相互関税」をかけると発表した。各国に一律10%の関税を課したうえで、さらに約60カ国・地域に対して、米国に対して相手国が輸入を阻害している状況=「非関税障壁」に応じて異なる税率の関税として「相互関税」を上乗せする仕組みだ。 主な国を見ると、中国34%、韓国26%、欧州連合20%と高率の関税が続く。日本については24%である。この「非関税障壁」には、例えば安全性確保ための規則や検査制度、環境対策としての独自の基準などが含まれており、それを米国からの輸入を阻む「障壁」と見做し、これに対抗して関税を引き上げようとするトランプの政策は、自分勝手そのものである。 しかし、トランプの政策はこれにとどまらない。 トランプが「相互関税」を導入したのは、1・2兆ドル(約185兆円)を超える貿易赤字や国内産業の空洞化を「国家の緊急事態」として、その解消のために貿易相手国に対して高関税を課そうという考えに基づいている。トランプにとって貿易赤字は、国内産業を圧迫し、雇用を奪っていることを意味しているのであり、高関税をかけて輸入を減らし貿易赤字を削減すことは国内産業を再建し、雇用を取り戻すことである。 トランプの高関税政策は、1930年のフーバー政権下での保護関税政策であるスムート・ホーリー法を思い出させる。第1次大戦後農産物が過剰生産に陥ったのを契機として、保護主義政策をとり、米国は農産品をはじめ広範な生産物に対して高関税を課した。これに対抗して欧州など各国も保護主義をとり、世界恐慌は沈静化するどころか、かえって悪化し、世界経済がブロック化する端緒となった。トランプの身勝手で横暴な高関税政策も、米国経済の助けにもならず、世界経済の混乱、停滞をもたらすだろう。 2024年の日本の対米輸出額は、前年比5・1%増の21・3兆円だった。これは日本の輸出額の全体の20%を占め、内訳では、輸送用機器が7・6兆円と全体の36%を占める。うち自動車が6兆円超と対米輸出の首位にある。自動車関連に次いで米国向け輸出シェアが高いのは半導体製造装置などの一般機械で、対米輸出の23%にあたる4・9兆円である。全体を見ると日本の対米貿易は685億ドルの輸出超過で、米国にとって日本は7番目に貿易赤字が多い国である。 日本にとって24%もの「相互関税」は、大きな打撃である。例えば昨年の日本の対米輸出額21兆円の約3割を占める自動車は、関税引き上げで、米国での販売や利益の大幅な減少は必至である。自動車産業は部品などの取引先は日本国内にとどまらずベトナムなど東南アジア諸国を含む供給網(サプライチェーン)を形成している。今回の関税引き上げではベトナム46%、タイ36%、インドネシア32%と日本よりも高率の関税を課せられた。これらの国に生産拠点を置き米国に輸出する企業も大きな影響を受ける。野村総合研究所の木内登英エグゼクティブ・エコノミストは、自動車や自動車部品の25%の関税が上乗せされると「日本経済にとってかなりの打撃で、国内での生産、雇用の縮小を促し、空洞化を後押しすることになるだろう」と指摘する(朝日、3・28)。また第一生命経済研究所の試算では、EUなどの報復措置の影響も含めて、日本全体では実質国内総生産(GDP)は0・4%程度低下するとの予測もある。 石破政権は日本は米国の友好国であるから、トランプの高関税適用を免れるのではないかと高をくくっていた節がみられるが、その淡い期待は打ち砕かれた。石破は急遽野党党首を招き、「言うならば国難、政府のみならず、野党も含めて、超党派で検討、対応する必要がある」として、挙国一致の協力を求めた。これに対して立・民の野田は「トランプとの直接談判を」と言っている。しかし、一方的に高率関税を課すというトランプの大国主義的な横暴に対して、自分の国は例外として見逃してほしいというのでは、政府の尻押しをすることになる。 トランプによる関税問題を米国と課税された国の対立とのみ見ることは出来ない。トランプの高関税政策は、米国資本主義の衰退の反映である。利潤目的の生産である資本主義の国際的な競争関係こそ、大国主義を振り回し、自国の利益のために他国の犠牲を省みない「アメリカ第一主義」のトランプ政権を生み出したのである。国境を越えた労働者の融合と協力の社会の実現こそ、労働者の理想である。 (T) | |||||||||||