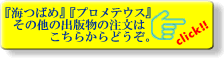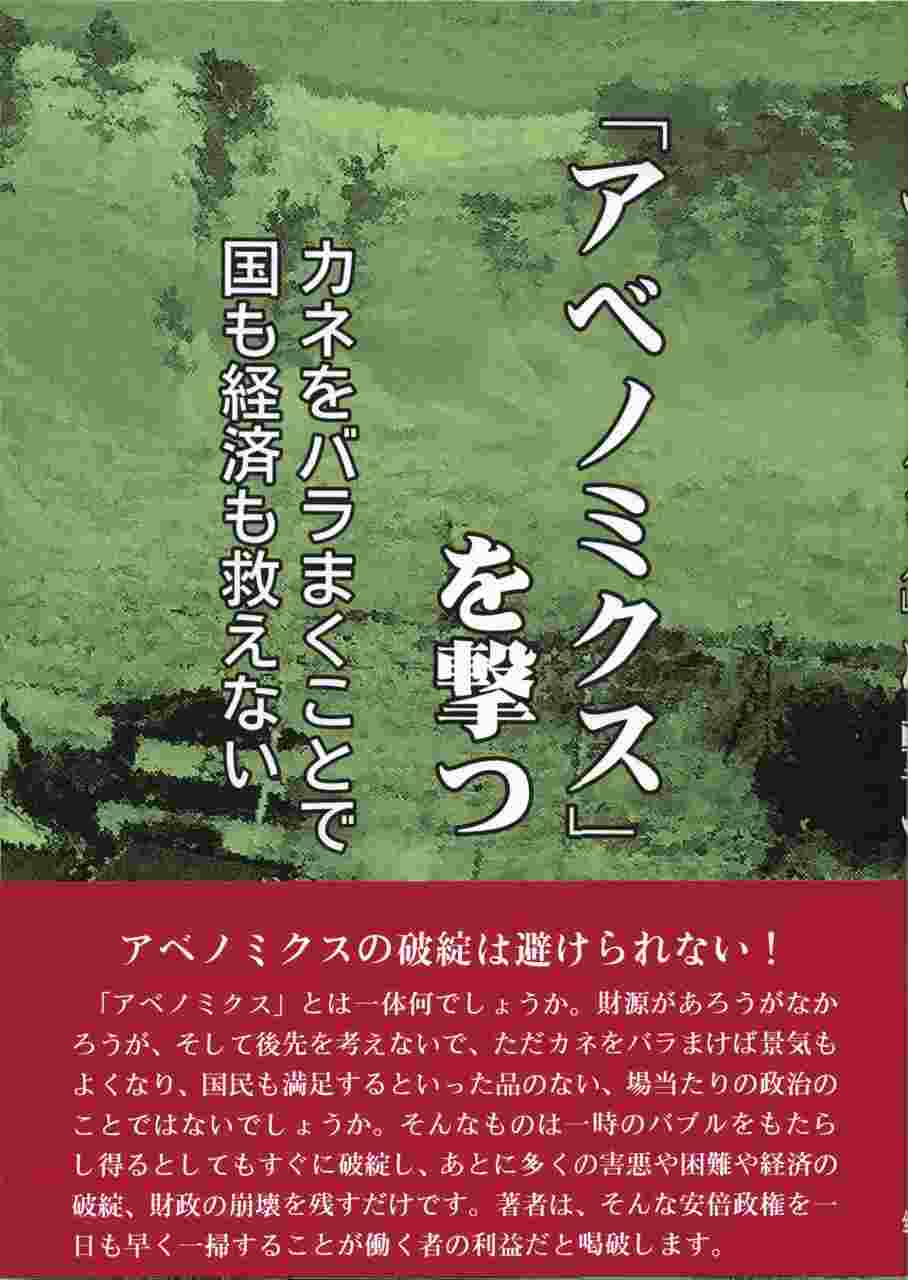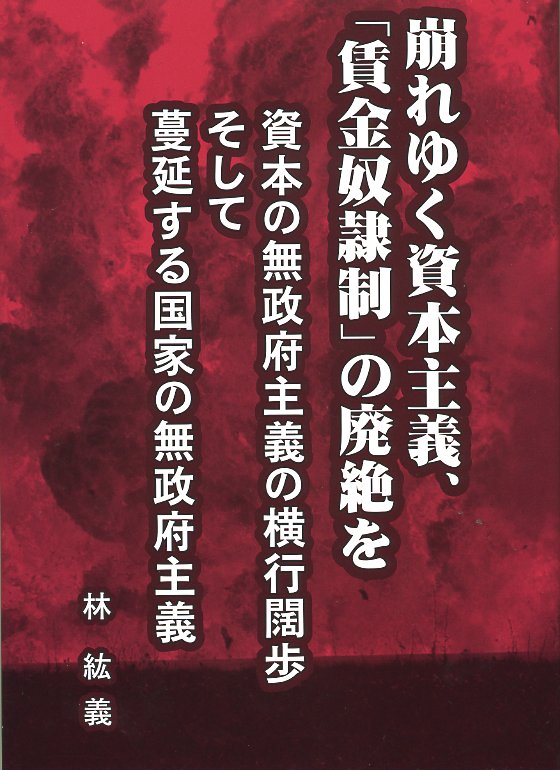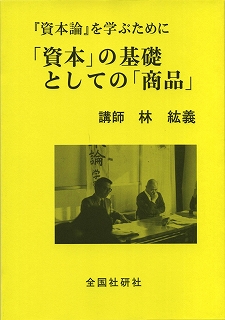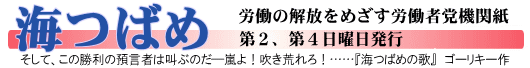 |
||||||||||||
| 購読申し込みはこちらから | ||||||||||||
|
●1508号 2025年10月12日 【一面トップ】 総裁選 先祖返りして高市選んだ自民党 ――風雲急を告げる自公・国 【一面サブ】 自民に擦り寄る維新 ――「副首都構想」で党勢復活を目す 【コラム】 飛耳長目 【二面トップ】 低賃金・極少賃上げに呻吟する医療・介護労働者 ――大企業の増益と〝高水準〟5%賃上げの陰で 【二面サブ】 攻撃兵器・原潜導入も ――防衛省有識者会議の提言 ※『海つばめ』PDF版見本 【1面トップ】総裁選 先祖返りして高市選んだ自民党風雲急を告げる自公・国4日に行われた自民党の総裁選に、高市、小泉、林、茂木、小林の5名が立候補し、予想に反し高市が選出された。決選投票で麻生派が党員票の多かった高市(党員票4割獲得)支持に回ったからであると言われ、「解党的出直し」を叫びながら旧態依然の派閥政治を印象付けた。そして、47都道府県のうち36都道府県支部が右翼高市を選んだ。自民党は参政党に票を奪われ「自民党は左傾化している」という疑念を右翼高市によって払拭しようとしている。 ◇麻生が牛耳る高市新執行部参院選で自民党の岩盤支持層、保守層を参政党に奪われた危機感が、選挙戦の最前線である都道府県支部の高市支持となって表れ当選を決定づけた。「参院選大敗で地方を中心に、リベラル寄りの石破政権によって保守支持層の自民離れが起きたとの危機感が高まり、保守回帰のうねりが起きていた」(10・5朝日電子版)。 高市は自らの「基本理念」で「日本を、守り抜きます! 高市早苗は、国の究極の使命は、『国民の皆様の生命と財産』『領土・領海・領空・資源』『国家の主権と名誉』を守り抜くことだと考えます」(高市のHP)をトップに掲げ、真正「国家主義者」であることを隠そうとはせずに、安倍路線継承を訴えてきた。 24年衆院選、7月の参院選で争点となり自民敗北をもたらしたのは、移民・外国人問題、〝カネと政治〟裏金問題だった。派閥解散の申し合わせを無視し派閥を維持し続けてきた麻生派(43名)が、決選投票で高市支持に一本化したことが高市当選の切り札になった。麻生の高市支持は、高市政権で〝キングメーカー″として影響力を示すことにあった。それは、7日に発足した新執行部人事で明らかになった。 党四役人事で「幹事長」は、麻生の義弟の鈴木俊一(72)が就任。麻生(85)より〝若く〟麻生引退後に身内での利権継承の思惑もある。「総務会長」は参院比例選出の有村治子で、支持団体は選択的夫婦別称、女性宮家創設に反対する「神道政治連盟」である。高市の立ち上げた政策勉強会に初回から参加している。有村は、石破退陣、総裁選前倒しの流れを作った8月8日の両院議員総会で、会長として仕切った。「政調会長」は総裁選の決選投票で高市支持に回った小林鷹之。「選対委員長」は総裁選で高市推薦の代表者の古屋圭司。古屋は右派団体である「日本会議国会議員懇談会」、「日華議員懇談会」(親台湾派)の会長を務めている。麻生は「副総裁」に就任。裏金議員・萩生田光一は「幹事長代行」に起用した。〝石破降ろし〟と〝高市担ぎ出し〟の「論功行賞」とも言うべき人事に他ならない。 ◇安倍路線継承謳うアベノミクス高市高市は安倍らが97年に設立した「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」に参加。安倍と当選同期であり、伝統的な価値観―男女平等に異議、家父長的家族観や歴史修正主義、国家主義的立場(高市は刑法で「外国の国旗損壊等」は刑罰の対象なのに「日本国旗損壊等」について何の規定もないと、「刑法改正案」の再提出を企む)、安倍が殺害されてからは、安倍路線の継承を訴え、総裁選でも憲法9条改正、スパイ防止法制定、国家情報局設置、排外的移民対策、皇室典範改正、安保三文書見直し(軍事費GDP2%強)を掲げた。 総裁就任後の記者会見では、積極財政主義で、自治体への交付金拡大(交付金は一時金ではなく、地方の中小企業の賃上げ助成や地方の公立病院の赤字補填など恒常的なものになる)、ガソリン暫定税率廃止、所得税基礎控除引上げ、「給付付き税額控除」の制度設計の着手などを表明した。 財源については今後の検討課題と先送りしたが、これらの政策を実現するためには多額の財政支出が必要だ。積極財政主義、利下げ(アベノミクス)の高市の登場で7日の株価は3日連続で最高値更新、為替は1ドル150・57円の円安にふれた。 「責任ある積極財政」の財源が赤字国債の際限なき拡大であれば、無責任なアベノミクスの二番煎じでしかない。すでに債券市場では、10年物国債利回りが6日に17年ぶりの高水準1・680%をつけた。「高市トレード」(高市政策の思惑取引)の急激な株価上昇はいつまでも続くことはない。高市政権の政治的混乱(連立の枠組みや自民党内の対立)がその引き金になるかもしれない。 高市は「日本のサッチャー」を目指すと公言しているが、高市の政策はサッチャリズムの「財政支出削減」と真逆の積極財政である。高市自民党の誕生で、排外主義的ポピュリズムを競い合う政治に拍車がかかる。労働者は断固反対しなければならない。 ◇きしむ自公連立、高市になびく国・民高市自民党と公明党とは、かつてない緊張関係にある。高市は「自公連立は基本中の基本」の立場で、就任直後、公明党の斎藤代表と会談し連立政権継続を呼びかけた。しかし、斎藤は「連立は政治理念と政策の一致が大前提。現状ではそれがすべて満たされる状況ではない。今後の対応を見守りたい」と、「靖国参拝が外交問題に発展したこともある」「政治とカネの問題」「外国人との共生」の三点について懸念を抱いていると述べ、「その解消無くして連立政権はない」と態度表明している。 7日に行われた公明党の緊急常任役員会では、政権離脱論が相次いだと報じられている。離脱論が大きくなったのは、2回の国政選挙と都議選での公明党の敗北は、自民党の〝カネと政治〟が公明党に対する不信につながり敗北したと考えるからであり、軍事大国化・軍事費GDP2%を掲げ、中国と対峙する路線を進もうとする高市政権と、「福祉の党」と「平和の党」を金看板とする公明党の立場が大きくズレてきたという事であろう。 斉藤から釘を刺されたのに対して、自民党新執行部は国・民との連立・連携協議で対抗している。 5日には高市、玉木が〝極秘会談〟を行った。自民党が少数与党である以上、野党との連立・連携は不可避である。公明の議席は衆院24参院21議席で、国・民の議席は衆院27参院25議席である。 ◇高市政権と闘う労働者の闘いを準備しよう労働者を搾取し支配する資本の国家である日本を守り抜くことが国の使命と考える高市政権打倒のために、団結して闘うことが労働者に課せられた使命であると我々は考える。労働者党に結集し共に闘おう! (古) 【1面サブ】自民に擦り寄る維新「副首都構想」で党勢復活を目す日本維新の会(以下、維新)は自民党総裁選中、「副首都構想」で党勢復活を図ろうと、総裁候補の本命と言われた自民・小泉に擦り寄った。しかし総裁選で小泉を破り勝利した高市は、維新に対して小泉ほどの熱はない。 ◇維新の退潮傾向去年10月の衆院選で、自公は大きく議席を減らし、過半数に18議席足りない少数与党に追い込まれた。維新も告示前の44議席を6議席減らし党勢の翳りが見られた。馬場代表と藤田幹事長は、選挙の責任を取って退任、吉村が代表、前原が共同代表に選出された。 さらに今年7月の参院選で、自公は合わせて47議席、非改選の75議席を合わせても122議席で、参院でも過半数に3議席足りない少数与党に追い込まれた。維新は改選5議席に対し7議席、非改選を合わせて2議席増の19議席となった。前回22年の参院選で得た12議席に比べると伸び悩み、比例の得票数は前回の約785万票から約438万票に激減。参院選不振の責任を取り8月、前原共同代表ら執行部は辞任、吉村代表は続投、藤田が共同代表に選出され、新執行部が発出した。 自公政権が衆参で少数与党に追いやられる中、国民民主が躍進し、参政党や保守党など自民党以上に反動的なポピュリズム政党が進出。維新の退潮傾向は顕著だ。自公政権が労働者大衆の支持を失っているのは、大衆の生活苦の深刻化と裏金事件で露呈した自民の腐敗政治に対して怒りが向けられているからだ。「第2自民でいい」と表明し、自民となれ合うと見なされる維新も当然、大衆から見放されているのだ。 ◇反動化する自民に加担しかし維新は去年12月、「総合経済対策」の裏付けとなる24年度補正予算案に自公、国民民主と共に賛成。今年2月には「高校授業料無償化」、「社会保険料を下げる改革」などを決め自公維3党合意し、維新は3月、25年度当初予算案に賛成した。与党寄りが顕著だ。 25年度予算は115・5兆円、当初予算としては過去最高、歳出は国の借金の返済である国債費、軍事費は共に過去最大だ。労働者大衆が、物価高の中で実質賃金が下がり生活苦に陥る中で、財源もないまま借金を増大させ、それを当てに不生産的な軍事費を膨張させる、反労働者的な階級性が如実に現れた予算であったが、維新は予算案に賛成して、石破政権に擦り寄った。 維新は総裁選の最中、提言「21世紀の国防構想と憲法改正」を発表。そして「スパイ防止法」の中間論点整理を行なった。また「副首都から起動する経済成長」と謳う「副首都構想」の法案骨子案をまとめ、維新独自の立場を押し出そうとした。 憲法改正は、自民党と連携を見据え、日本の軍事増強への道を後押しするもの、「スパイ防止法」はこれと軌を一にし、排外主義を煽り、国内の反政府的な政治活動を抑圧するもので、これらに関し国民民主や参政党なども法制定などの排外主義的な動きを見せている。 「副首都構想」は、過去2回の住民投票で否決された「都構想」の実現が前提だ。維新吉村は、連立政権入りの協議を打診された場合「協議するのは当然」、公約の社会保険料引き下げと「副首都構想」実現の協力が条件だとした(9月26日)。 関西万博をどうにか無難に終えるとみる維新は、自公政権と組んで「副首都構想」実現を進め、党勢低迷からの復活を目した。大衆の支持を失いつつある自民に頼り、党勢を回復しようとするのだ。 維新は「大阪都構想」で経済が発展するというデマゴギーで労働者大衆の幻想を煽り、労働者に犠牲を強い抑圧し、生き延びる資本の体制の維持を図ろうとする。労働者は自民に加担する維新を暴露し新しい労働者の闘いを切り開く。 (佐) 【飛耳長目】 ★年度の折り返しの10月、価格改定や制度見直しなど多くが変わる。コメは備蓄米放出の効果は失せて5㌔4千円台。食品3024品目の値上げも食卓を襲う★3年前の10月、一定所得以上の後期高齢者の医療費負担1割を2割にした軽減措置の上限月額3千円がなくなり全て2割に。現役世代の負担軽減を名目にするが、後期高齢者の労働者は現役時代、税や社会保険料を源泉徴収され、応分の負担はしてきた。そのカネの使い方を不問に出来ようか★負担軽減策で、柔軟に働ける環境づくりのため、事業主に3歳から小学校入学前の子を持つ労働者に時差出勤や短時間勤務、年10日以上の支援休暇などから2つ以上の対応が義務化された。そして25年度の最低賃金が全国平均で前年度比66円のわずかなアップで1121円になり、10月から都道府県ごとに順次適用される★政府は20年代に1500円台を目指すとするが、ニッセイ基礎研究所の金明中氏は「国際的な基準の平均を大きく下回っています」と断じる(『毎日』9・18)。EUでは「22年に採択された指令で、最低賃金は労働者の賃金中央値の6割とすべき……。22年時点で仏国と韓国は中央値の6割を超える一方、日本では45・6%」に過ぎないと言う★賃上げは労働者が資本家から闘い取るもの、「政府に期待する」のは〝お門違い〟だ。 (Y) 【2面トップ】低賃金・極少賃上げに呻吟する
| |||||||||||